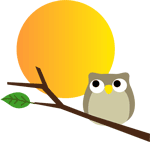あらすじ
美食倶楽部
大正時代のことです。
美食倶楽部という美味しいもの大好き人間が集まるクラブがありました。
彼らにとっては人生で一番大事なことは、美味しいものを食べることでした。
彼らのポリシーは
料理は芸術の一種であって、
少くとも彼らにだけは、
詩よりも音楽よりも絵画よりも、
芸術的効果が最も著しいように感ぜられたからである。
彼らは美食に飽満するとー、
いや、単に数々の美食を盛ったテエブルの周囲に集まった一刹那 の際にでもー、
ちょうど素晴らしい管絃楽を聞く時のような興奮と陶酔とを覚えてそのまま魂が天へ昇って行くような有頂天な気持ちに引きあげられるのである。
美食が与える快楽の中には、
肉の喜びばかりでなく霊の喜びが含まれているのだと、
彼らは考え ざるを得なかった。
五人の会員は皆美食の為にでぶでぶ。
身体中が脂肪過多のお蔭ででぶでぶに肥え太り頬や腿のあたりなどは、
東坡肉の材料になる豚の肉のようにぶくぶくして脂ぎっていた。
という状態です。
ほぼすべての会員が胃拡張。
五人中、三人は糖尿病です。
それでも全然気にしません。
と笑いあっています。
彼らはほぼ皆、有閑階級で構成されていました。
毎日のように集まってはごちそうを食べます。
彼らは東京の有名な料理はすべて食べつくして、喰い飽きてしまいました。
そこで、わざわざ美食のためだけに、遠方に出かけます。
すっぽんを食べに京都へ。
鯛茶漬(たいちゃづけ)が喰いたさに大阪へ。
ふぐ料理が食べたさに下関へ。
秋田名物の鋼(はたはた)の味が恋しさに北国の吹雪の町へ。
しかしだんだん彼らはどんな料理を食べても飽き足らなくなります。
追い追いと彼らの舌は平凡な「美食」に対し麻痺してしまって、
何を舐めても、何を啜っても、
そこには一向彼らの予期するような興奮も感激も見出されなくなって行った。
もう何を食べても面白くない。
これは美食のために生きているといっても過言ではない、彼らにとっては大問題です。
また、彼らには
という功名心もありました。
そこで会員たちは、競って東京中のあらゆる食べ物をあさりまわります。
会員の一人は銀座四丁目の夜店に出ている今川焼を喰ってみて、
それが現在の東京中で一番うまい食物だということをいかにも得意そうに、
発見の功を誇りがおに会員一同へ披露した。
またある者は毎夜十二時ごろに烏森の芸者屋町へ売りに来る屋台の焼米(シュウマイ)が、
天下第一の美味であると吹聴した。
といっても屋台や今川焼やシュウマイではB級グルメといったところでしょう。
どこかに本当においしいご馳走を出す店はないでしょうか?
こうなって来ると、どうしてもえらいコックを捜し出して、新しい食物を創造するよりほかにない。
われわれはもっと大規模な饗宴の席に適しい色彩の豊富な奴を要求するんだ。
さて、会員の誰が、会員たちが満足できるような美食を見つけ出すことができるのでしょうか?
G伯爵
会員の一人にG伯爵という、若い貴公子がいました。
G伯爵は倶楽部の会員のうちでも、
財力と無駄な時間とを一番余計に持っている、
突飛 な想像力と機智とに富んだ、
一番年の若い、そうしてまた一番胃の腑の強い貴公子であった。
もちろん彼もおなかはたぽんたぽん、美食に対する執着心は並ではありません。
伯爵の頭の中には、
いろいろの料理に関する荒唐無稽な空想がしきりなしに浮んでは消えた。
寝ても覚めても伯爵は食物の夢ばかりを見た。
G伯爵が十日間も美食の夢を見続けた、ある晩のことです。
G伯爵はいつもながらの、美食倶楽部の宴会のごちそうを味わった後、ふらりと仲間を置き去りにして、散歩へでかけました。
G伯爵は
こうして散歩をすればそれにぶつかるのではないか
と考えたのです。
時刻は寒い冬の夜の九時頃。
G伯爵は街の景色や、往来の人たちなど、他のどんなことにも興味を持ちません。
しかし食い物屋の前を通るときは、それがどんな小さい店でも鼻が鋭敏になります。
G伯爵の鼻は非常に鋭敏で、匂いを嗅げばその料理のうまさ加減がだいたいわかってしまうのでした。
不思議な中国人たち
G伯爵が寂しい道を歩いていると、向こうから二人の中国人が楊枝をくわえながらやってきて、G伯爵とすれ違いました。
通行人にはまったく関心のないG伯爵ですが、二人の中国人から紹興酒の匂いがしたので、ハッとします。
するとこの辺り新しく中華料理屋ができたのかな?
その時どこか遠くで奏でているらしい、中国音楽の胡弓の響きが聞こえてきました。
伯爵はじっと一心に耳を澄ませて胡弓の音色を聞いていました。
まもなく伯爵は胡弓の音色がどこから聞こえてくるか探り当てました。
胡弓の音色は一ツ橋の方角の、人通りの少ない、ひっそりとした路地の奥から聞こえるのです。
胡弓のメロディーがやむと、十人以上の人間が一斉に拍手喝さいをするのが聞こえます。
そしてその席上で中華料理を食べているのだ。
また胡弓が始まりました。
G伯爵は胡弓の響きのするほうへ歩いていきます。
戸を閉ざした一般家屋の間に、たった一軒、電灯を煌煌と点じた三階建ての木造の西洋館がありました。
胡弓の音はその三階から聞こえてきます。
中国の音楽のことは何もわからないG伯爵ですが、その音色に耳を傾けていると、さまざまな中華料理のイメージが沸き起こります。
胡弓の糸が急調を帯びて若い女の喉を振り搾るような鋭い声を発すると、
それが伯爵には何故か竜魚腸の真赤な色と舌を刺すような強い味いとを想い出させる。
それから忽ち一転して涙に湿る濁声のような、
太い鈍い、綿々としたなだらかな調に変ずると、
今度はあのどんよりと澱んだ、
舐めても舐めても尽きない味が滾々と舌の根もとに滲み込んで来る、
紅焼海参のこってりとした糞(あつもの)を想像する。
そうして最後に急霰のような拍手が降って来ると、
有りと有らゆる支那料理(中華料理)の珍味佳肴が一度にどッと眼の前に浮かんで果ては喰い荒されたソップの碗だの、
魚の骨だの、散り蓮華だの杯だの、
脂で汚れたテーブルクロースだのまでが、
まざまざと脳中に描き出された。
G伯爵は食欲がムラムラ沸き起こってきます。
もうとてもじっとはしていられません。
とにかく、自分が今夜胡弓の音に 引き寄せられてこの家を捜しあてたのも 何かの因縁に違いない。
その因縁だけでもこの家の料理を是非とも一度は試して見る値打ちがある。
それに、自分の直覚するところでは、何かこの家にはかつて経験したことのない珍らしい料理があるように感ぜられる。
G伯爵はつかつかとその家に入ろうとしましたが、中からは鍵がかけられています。
この家の門には「浙江会館」という看板がさがっていました。
にぎやかで灯りが眩しいのは三階だけ。
一階、二階はひっそりとしていて扉が閉じられています。
どうやら日本に在留する浙江省出身の中国人の倶楽部のようです。
いくらG伯爵でも、そこにだしぬけに割り込んで、彼らの仲間にいれてもらう勇気はありません。
G伯爵があきらめがたく、鎧戸にぴったりと顔を寄せていると、料理の匂いがただよってきます。
G伯爵はここが中華料理屋ではないことを知ってから、ますますこの家の料理を食べたいと思うようになりました。
中国人が集まって宴会をしているわけです。
ということは、ここの料理は、日本風に改良された和風中華ではなく、純中国式の中華料理でしょう。
G伯爵は以前から、本場の中華料理は日本で食べる中華料理よりもはるかに美味しいものだ、と聞いていました。
G伯爵は、かねてから本場の中華料理にあこがれていたのです。
またG伯爵は中国でもとくに浙江省付近は、もっとも料理の材料に富む場所であることを知っていました。
浙江省といえば東坡肉(トンポーロー)の本場です。
中国人たちの宴
G伯爵はどうしても諦めがたく、「浙江省会館」の軒下に三十分ほどもたたずんでいました。
家から一人の酔っ払った中国人がふらふらと出てきて、伯爵の肩にぶつかりました。
やあ。どうも失礼しました。
いや、私こそ大そう失礼しました。
実は私は非常に中華料理が好きな男でしてね。
あんまり旨そうな匂いがするもんだから、つい夢中になって、さっきから匂いを嗅いでいたんですよ。
G伯爵の無邪気な告白がおかしかったのでしょうか?
中国人は大きなおなかをゆすって笑い出しました。
いや、ほんとうなんですよ。
私は旨い物を喰うのが何よりも楽みなんですが、とにかく世界に中華料理ほど旨い物はありませんな。
わッはッはッ!
それで私は東京中の支那料理屋へは残らず行ってみましたがね。
実を云うと料理屋の料理でない、たとえばこういう中国人ばかりが会合する場所の、純粋な中華料理 が食べてみたいとこの間から思っていたんですよ。
ねえ、どうでしょう。
甚だどうも厚ましいお願いのようですが、ちょいと今晩あなた方の仲間へ入れてここの内の料理を喰べさせて貰えませんかね。
いつのまにか沢山の中国人たちがやってきてG伯爵を見ています。
みなG伯爵のように太っていてにこにこと笑っていました。
G伯爵のあまりに無邪気であけすけな要求が中国人たちの心を動かしたのでしょうか?
中国人たちはG伯爵を中に入れてくれました。
よろしい!
どうぞ入って下さい。
あなたに沢山中華料理を御馳走します。
この料理は非常にうまいです。
普通の料理屋の料理とは大変に違います。
食べると 頬ぺたが落ちますよ。
さあ。
あなた。
遠慮しないでもいいです。
どうぞ上って食べて下さい。
夢のような心地で中国人たちに家の中に案内されるG伯爵。
家の内部もG伯爵が初めて見るものばかりでエキゾチックです。
さまざまな中華料理の材料。
アヘンを吸うための細かく仕切られた部屋、
部屋の中は料理の煙や、たばこ、料理の水蒸気などで、もうもうとしていて人の顔もわからないほどに濁っています。
G伯爵が見た宴会に出された料理は……
粘土を溶かしたような重い執拗い(しつこい)ソップの中に、
疑いもなく豚の股児の丸煮が漬けてある。
しかしそれはただ外だけが豚の原形を備えているので、
皮の下から出て来るものは豚の肉とは似てもつかない半平のような、
フワフワしたものであるらしい。
おまけにその皮も中味もジェリーの如くクタクタに柔かに煮込んであるのか、
匙を割り込ませるとあたかも小刀でナイフで切取るように、
そこからキレイに捥ぎ取られる。
見る見るうちに、
四方八方から匙が出て来て豚の原形は、
一塊ずつ端の方から失われて行く。
まるで魔法にかかっているようである。
もう一方の中にあるのはそれは明かに燕の巣である。
人々は頻に丼の中へ箸を入れては心太(ところてん)のようにツルツルした燕菜をソップの中から掬い上げている。
むしろ不思議なのはその燕菜が漬かっている純白の色をしたソップである。
こんな真白な汁は杏仁水よりほかに日本の支那料理(中華料理)では見たことがない。
支那(中国)へ行けば奶湯(たいとう)という牛乳のソップがあると聞いていたが、
あれこそその奶湯(たいとう)ではあるまいかと伯爵は思った。
会長さんに断られてしまう
さて四十歳ぐらいのここの会員では一番の年長者らしい紳士が現れました。
陳さんといって、この会館の会長です。
G伯爵を案内してくれた中国人は、G伯爵を陳会長に紹介してくれます。
あなたはG伯爵という方ですか?
ああそうですか。
ここにいる人達は皆酔っぱらっものですから、あなたに大変失礼をしました。
中華料理がお好きならば、それは 御馳走してもいいです。
しかしこの内の料理はそんなに旨くはありません。
それに今夜はもうコック場がしまいになりました。
甚だお気の毒ですが、この次の会の時にまたいらしって下さい。
いや、何もわざわざ私のために特に料理を弁えて頂かなくても結構なんです。
実はその、非常に厚かましいお願いですが、諸君のお余りを食べさせて貰えばよろしいんですけれど、そういう訳には行きますまいかな。
余り物といってもあの連中はあの通り大食いですからとても余ることはないでしょう。
それにあなたに余り物を差し上げるのは大変失礼です。
私は会長としてそういう失礼なことを許す訳には行きません。
陳さんの顔はしだいに不機嫌になり、とてもG伯爵の願いを受け入れてくれそうにありません。
G伯爵が振り向いてみると、新しいごちそうが出てくる最中でした。
もうコック場が閉まったなんて、嘘にちがいありません。
陳会長の料理の秘密
G伯爵を陳会長に紹介した中国人がこう謝ります。
どうも困りました。
あなたに大変済みませんでした。
会長がどうしても許してくれませんから。
いや、僕らが悪かったんです。
僕らが酔っていたものだから、無闇にあなたをこんな 所へ引き擦り込んでしまったんです。
会長は悪い人ではありませんけれども、やかましい男だものですから。
なあに、私こそあなたに飛んだ御迷惑をかけました。
しかし会長はどうして許してくれないのでしょう。
この盛大な宴会の模様をせっかく目の前に見ていながら、どうも甚だ残念ですがな。
会長が許さなければ駄目なのでしょうか。
ここの会館はすべて会長の権力のうちにあるのですから
会長が許さないのは、きっとあなたを疑ぐっているからでしょう。
コック場がおしまいになったというのは嘘なんです。
あれ御覧なさい、まだあの通りコック場では料理をこしらえているのですよ。
それじゃ会長は私を怪しい人間だと思っているんですね。
そりゃあ御尤もです。
用もないのにこの路次へ這入って来て、家の前をうろうろしていたのですから、怪しいと思えば怪しいに違いありません。
私は自分でも可笑しいと思っているくらいです。
しかしこれにはいろいろ理由があるので、説明しなければ分りませんが、実は我々は美食倶楽部というのを組織していましてね。
つまり旨いものを食う倶楽部ですな。
この倶楽部の会員は、旨いものを食わないと一日も生きていられない人間ばかりから成り立っているんですが、もうこの頃は旨いものが無くて弱っているんです。
会員が毎日々々手分けをして、東京市中の旨いものを探して歩いていますけれど、もうどこにも珍らしいものは無くなってしまいました。
今日も 私は旨いものを探しに出たところが、図らずもこの家を見付け出して、普通の中華料理屋だと思って路次の中へ入ってみたのです。
そんな訳で私は決して怪しい者じゃあありません。
先刻差し上げた名刺にある通りの人間です。
たた食い物のことになると、しらずしらず夢中になって、つい常識を失ってしまうだけなんです。
伯爵、私はあなたを少しも疑っていはしません。
われわれ―少くとも今夜この楼上に集まっている人達には、あなたの心持はよく分ります。
美食倶楽部とはいいませんが、われわれがここに集まるのも、実は美食を食うためなのです。
われわれはやは私はアメリカにもヨーロッパにも二三年滞在したことがありますが、世界のどこに行 っても支那料理ほど旨いものはないということを知りました。
私は極端な中華料理の讃美者です。
それは私が中国人だからという訳ではない。
あなたが真のガストロノマア(美食家)で あるならば、この点において、多分私と同感であろうと私は信じます。
あなたは私にあなたの倶楽部のことを打ち 明けてくれました。
そこで私はあなたを少しも疑ぐっていない証拠に、われわれの倶楽部――この会館のことをお話ししましょう。
この会館では不思議な料理が出来るんです。
今あなたが御覧になった、あのテーブルの上に並んでいる料理なんかは、ほんのプロローグなんです。
この後からいよいよほんとうの料理が出るんです。
それはほんとうですか?
あなたは冗談に私をだますのじゃないのですか?
それがほんとうなら、私はもう一遍あなたにお願いします。
私が怪しい人間 でないということを、もう一遍あなたから会長に説明して下さい。
それでも疑いが晴れなかったら、私が美食家であるかないか、会長の前で試験をして下さい。
中華料理でも何でも、今まで日本にあったものなら私は一々その味をあてて見せます。
そうしたら私が如何に料理に熱心な男であるか分るでしょう。
全体、それほど日本人を嫌うというの は可笑しいじゃありませんか。
あなたは美食の会だと云われたようですが、あるいは何か政治上の会合ではないのでしょうか。
政治上の会合?
いやそんなものじゃありません。
しかしこの会では、 政治上の会よりもむしろ遥に入場者の人選がやかましいのです。
この会館で食わせる美食はまるで普通の料理とは違っています。
その料理法は会員以外には全く秘密になっているのです。
今夜ここに集まった連中は主に浙江省の人達ですが、しかし浙江省の人ならば 誰でも入場が出来るという訳ではありません。
すべて会長の意志によるのです。
料理の献立も会場の設備も宴会の日取も会計も何もかも、みんな会長の指図によって行われます。
この会はまああの会長一人の会だと云ってもいいでしょう。
すると一体、あの会長というのはどういう人なんですか。
どうしてあの会長がそんな 権力を持っているんですか。
あれは随分変った人です。
えらいところもある代りに、少し馬鹿なところがあるのです。
馬鹿なところがあるというと?
中国人は多くを語りすぎたことを後悔している、といった顔をしています。
あの人はね、うまい料理を食うことが非常に好きで、そのために馬鹿か気違いのようになるのです。
いや、食うことが好きなばかりではありません。
料理を自分で拾える事も非常に上手です。
それでなくても中華料理というものは材料が豊富であるのに、あの人の手にかいればどんな物でも料理の材料にならないものはありません。
ありとあらゆる野菜、果物、獣肉、魚肉、鳥肉は勿論のこと、上は人間から下は 昆虫に至るまでみんな立派な材料になるのです。
あなたも知っていらっしゃるように、中国人は昔から燕の巣を食います。
熊の掌、鹿の蹄筋、サメのヒレを食べます。
しかしたとえばわれわれに木のを食い鳥の糞を食い人間の涎(よだれ)を食うことを教えたのは、恐らくあの会長が始まりでしょう。
それからまた煮たり焼いたりする方法についても、会長によっていろいろの手段が発明されるようになりました。
従ってソップの種類なぞは、今まで十幾種しかなかったものが、既に六七十種にまでなっているのです。
次に最も驚くべきは料理を盛るところの器物です。
陶器や、磁器や、金属や、それらによって作られた皿だの、碗だの、壺 だの、匙だのというものばかりが食器でないことが、会長によって明らかにされました。
そうして食物は、常に食器の中に盛られると限ったものではなく、食器の外側へぬるぬると塗りこくられることもあります。
あるいは食器の上へ噴水の如く噴き出されることもあります。
そうしてある場合には、どこまでが器物でどこまでが食物であるか分らないことさえないとは云えません。
そこまでいかなければ真の美食を味わうことは出来ないというのが、会長の意見なのです。.
ここまでお話したらば、会長のこしらえる料理というものが、どんな物であるか大概お分りになったでしょう。
そうして、その会に出席する会員の人選を厳密にする訳も大方お分りになるでしょう。
実際こういう料理があまり世間にはやり出したら、アヘンの喫煙がはやるよりももっと恐ろしい訳ですからね。
なるほどよく分りました。
そのお話で大概私にも想像が出来ないことはありません。
そういう美食の会であるとしたならば、政治上の秘密結社よりも余計人選を厳密にするのは当然のことです。
正直を云うと、私が常に抱いている美食の理想は、やはり会長の考えの通りだったのです。
しかし私には如何にして理想の料理を実現したらよいか、その方法を発見することが出来ませんでした。
今夜のこの会場へ這入って来たことは全く私には夢のようです。
寝ても覚めても私が絶えず憧れていたのは、実にその会長のような料理の天才に出で思うことでした。
あなたはさっき、私を少しも疑ってはいないとおっしゃった。
私を信用して居られ ばこそ、いろいろの話をして下すったに違いない。
私がどれほど料理に熱心な男であるかも、お分りになったに違いない。
そうしてあなたは、今一歩を進めて、もう一度私 を会長に推薦して下さることが出来ないでしょうか。
もし会長がどこまでも許してくれ なかった場合には、たとえ食卓に着かないまでも、こっそりと何かの陰にかくれて、せめて宴会の様子だけでも見せて下さる訳には行かないでしょうか?
あなたがそれ ほどにおっしゃるのなら、何とかして宴会の光景を見せて上げましょう。
ですが、会長に紹介したところで、とても許される望はありません。
事によったら会長はあなたを警察の刑事だと思っているのかも知れません。
むしろ会長には知らせずに、そっと見物した方がいいでしょう。
そう云いながら、中国人はG伯爵をアヘンを吸うための小部屋に引っ張っていかれます。
その小部屋には小さな穴があって、そこから覗くと宴会の様子を見渡すことができるのでした。
G伯爵はその晩、小部屋に隠れ、小さな穴から宴会のようすを眺めて、世にも稀なる美食の秘訣を会得したのでした。
G伯爵の不思議な料理
まもなくG伯爵は偉大なる美食家、かつ偉大なる料理の天才として、美食倶楽部の会員たちから無上の賛辞と喝采を得るようになりました。
G伯爵はあの中国人との約束を守り、料理のインスピレーションをどこから得たのかは決して会員に語りません。
と言い張ります。
美食倶楽部では、毎晩G伯爵の主催によって美食の会が催されます。
そのテーブルに現れる料理は中華料理には似ているものの、いままでに全然前例のないものでした。
そのメニューは
清湯燕菜
鵝粥魚
翅蹄筋海参
燒烤全鴨
炸八塊
竜戯球
火白菜
抜糸山薬
玉蘭片
双冬奔
メニューを見た会員たちは、最初は
と思うのですが、実際に料理が出されると、献立によって予想していた料理とは、味はもちろん、外見さえも全く違った新しい料理でした。
さて、ここからはG伯爵の不思議な料理を紹介していきましょう。
鶏粥魚翅(けいしゅくぎょし)
たとえばその中の鶏粥魚翅(けいしゅくぎょし)の如きは、
普通に用うる鶏のお粥でもなければ鮫の鰭でもなかった。
ただどんよりとした、
羊羹のように不透明な、
鉛を融かしたように重苦しい、
素敵に熱い汁が、偉大な銀の丼の中に一杯漂うていた。
人々はその丼から発散する芳烈な香気に刺戟されて、
我れ勝ちに匙を汁の中に突込んだが、
口へ入れると意外にも葡萄酒のような甘みが口腔へ一面にひろがるばかりで、
魚翅や鶏粥の味は一向に感ぜられなかった。
「何んだ君、こんな物がどこがうまいんだ。変に甘ったるいばかりじゃないか。」
そう云って気早やな会員の一人は腹を立てた。
が、その言葉が終るか終らないうちに、
その男の表情は次第に一変して、
何か非常な不思議な事を考え付いたか、
見附け出しで もしたように、
突然驚愕の眼を呼った。
というのは、今の今まで甘ったるいと思われていた口の中に、
不意に鶏粥と魚翅の味とがしめやかに舌に沁み込んで来たのである。
甘い汁が、一旦咽喉へ嚥み下される事はたしかである。
けれどもその汁の作用はそれで終った訳ではない。
口腔全体へ漏漫した葡萄酒に似た甘い味が、
だんだんに稀薄になりながらも未だ舌の根に纏わっている時、
先に嚥み込まれた汁はさらに順になって口腔へ戻って来る。
奇妙にもその噫(おくび)には立派に魚翅と鶏粥との味が附いているのである。
そうしてそれが舌に残っている甘みの中に混和するや否や忽ちにして何とも云えない美味を発揮する。
葡萄酒と鶏と鮫の鰭とが、
一度に口の中に落ち合って醗酵しつつ、
しおからの如くになるのではないかというような感じを与える。
第一、第二、第三、と噫(おくび)の回数が重なるに従って、
それらの味はいよいよ濃厚になり辛辣になる。
「どうだね、そんなに甘ったるいばかりでもなかろう。」
その時伯爵は、会員一同の顔を見渡しながら、
ニヤリと会心の笑みを洩らすのである。
「君たちはその甘い汁を味わうのだと思ってはいけない。
君たちに味わって貰いたいのは後から出て来る噫(おくび)なのだ。
噫(おくび)を味わうためにその甘い汁を吸うのだ。
我れ我れのよう に、常に食物を喰い過ぎる連中は、
まず何よりも噫(おくび)の不快を除かなければならない。
たべた後で不快を覚えるような料理は、
どんなに味が旨くっても真の美食という事は出来ない、
喰えば喰うほど後から一層旨い噫(おくび)が襲って来る、
それでこそ我れ我れは飽く事を知らずにたらふく胃袋へ詰め込む事が出来るのだ。
この料理は、大して変った物でもないが、
その点において君たちに薦める理由があると思う。」
注)噫(おくび)とはげっぷのこと。
火腿白菜
この料理はその日の料理の一番最後に出されました。
まず会員は食卓のそばを離れたうえ、食堂の四方へ散り散りに分かれて立つことを要求されます。
それから室内の電灯がすべて消されます。
どんな灯りさえ漏れてこないように、扉が注意深く密閉されます。
部屋の中は一寸さきも見えないほどの真っ暗です。
その後三十分ほども会員たちは死んだような静かな真っ暗闇の中に放置されます。
冬なのに灯りを防ぐためにストーブの火が消されているのでとても寒い状態です。
そんなときに部屋の隅の方から忍びやかに歩いてくる人の足音が聞こえ始めます。
なまめかしくさやさやと鳴る衣擦れの音。
軽いしとやかなスリッパの音。
どうやら女性のようでした。
その女性は檻に入れられた獣のように、部屋の一方から一方へと歩きまわります。
会員たちの鼻先を横切りつつ、黙々と五六度も行ったり来たりします。
それは二三分ぐらいつづいたでしょうか?
まもなく部屋の右側へ回っていった足音は、ある会員の前で、ぴったりと止まりました。
その会員は、今しも自分の前に泊まった足音の主が想像の如く一人の女性であることを感じました。
というのは女に特有な髪の油や、白粉や香水の匂いがぷんぷんとするからです。
女は会員と差し向いに、顔をすれすれにして立っているようでした。
会員の額には優しい女の前髪が触れ、温かい女の息がかかります。
そうしているうちに女は、柔らかい手のひらによって会員の顔を撫でまわします。
まるで顔のマッサージを受けているようです。
顔中を撫でまわした手は今度は会員の唇をつまんで、引っ張りたりたるませたりします。
それから女の手は、会員の口の両端へ指をあてて、口中の唾液を少しずつ外にだします。
しまいには唇全体がびしょびしょに濡れるまでにその辺いったいへ唾を塗りこくりました。
唾を塗りこくった指の先で、何度も何度もぬるぬると会員の唇のとじ目を擦ります。
会員はまだ何も食べていないのに、すでに何かをほおばっているような気がしてきます。
次第に会員は食欲がわいてきます。
会員がもうたまらなくなって、誘い出されるまでもなく自分からよだれをだらだら垂らしそうになった時です。
今迄会員の唇をもてあそんできた女の手が、突如として会員の口の中に侵入してきました。
その手は人の手にしては、ぐにゃぐにゃとしています。
しかも指の股から甘い汁が出てきます。
それは中華料理のハム(火腿)の味でした。
女の指は、もうねぎのようにくたくたです。
人間の女性の手がいつのまにか、白菜のじくに化けてしまったのでしょうか?
しかしその手だか白菜だかわからないものは、相変わらず人間の手のように動きつづけます。
会員はためしに、その指か白菜わからない物体の、先の方をかじってみました。
それはかつて経験をしたことのないような甘みもある、たっぷりとした水気を含んだ、柔らかな白菜でした。
会員はその美味に釣り込まれます。
会員は思わず五本の指の先をことごとく噛み潰して飲み下しました。
しかし、噛み潰された指の先は少しも指の形を損じておらず、相変わらず動き続けるのです。
会員が腹いっぱいに白菜の美味を貪り喰ったと思ったころでした。
植物性の繊維でできていた手は、人間の肉の感触へともどります。
そして五本の指で、会員の口の中に残っている残りかすをきれいに掃除します。
手は、はっかのようなひりひりしたさわやかな刺激物を会員の歯の間に撒き散らした後、すっぽりと口の外へでていきます。
以上の様に、会員一人一人が、この奇妙な料理を味わった後、灯りがともされました。
そこにはあの不可解な手の持ち主である女性の姿は跡形もありません。
高麗女肉
それは一枚の素敵に大きな、
ぽっぽっと湯気の立ち昇るタオルに包まれて、
三人のボーイに恭しく担がれながら、
食卓の中央へ運び込まれる。
タオルの中には支那風(中国風)の仙女の装いをした一人の美姫が、
華やかに笑いながら横わっているのである。
彼女の全身に纏わっている神々しい羅綾の衣は、
一見すると精巧な白地の緞子かと思われるけれど、
実はそれが 悉く天ぷらのころもから出来上っている。
そうしてこの料理の場合には、
会員たちはただ女肉の外に附いている衣だけを味わうのである。
感想
美食への執念がすごいG伯爵。
食べ物のことに、ここまで情熱をかける彼が笑いを誘います。
ストーリーは雰囲気重視のところがあるかもしれません。
浙江会館の中の怪しい雰囲気。
それにG伯爵を案内した中国人があんまりもったいぶるので、私は読んでいてもっと別の物を期待していました。
これはカニバリズム、人肉グルメの話では……と思っていたので、結末にちょっとなーんだと思ってしまいました。
きっと、読者にそう思わせることを、作者は計算して書いていることでしょう。
こちらの記事もおススメ
谷崎潤一郎のその他の作品について
谷崎潤一郎『鍵』 あらすじ
谷崎潤一郎『富美子の足』ネタバレ