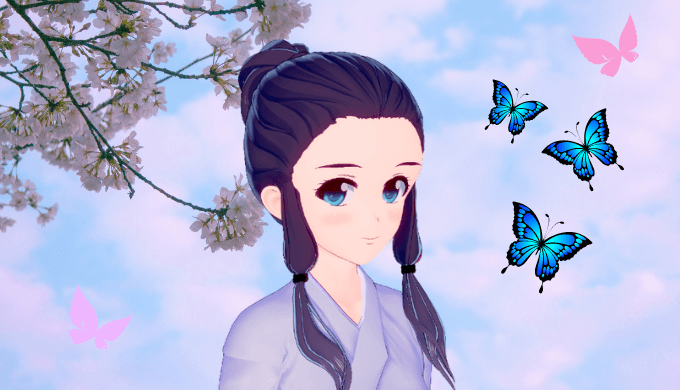二年生になった頃だった。
学友の金栄らが、僕と祝君ができている、
とからかうようになった。
その時、僕は「できている」というのは仲のよい友達という意味だと思った。
うんそうだよ、僕達できているんだ、
と馬鹿みたいに笑いながら無邪気に答えたものだった。
意味がわかるようになってからは恥ずかしくなって教室ではお互いにしらんぷりをして、
人目を避けて会うようになったのである。
祝君は郷里からの便りを、
象牙色の細い指で優雅にくるくると繰る。
いつもながら本当に読んでいるのかと疑いたくなるような速さだ。
右手の束と左手の束が同じぐらいになった時だった。
祝君はあっ、
と笛のような声をだし、
指を止めた。
どうしたのかと聞くと、祝君はなんでもない、後で読むよ、
と束を纏めだした。
今読みなよ、僕はその間、
さっきの所を勉強しているから、
と遠慮した。
しかし祝君は、
いやいいよ、今日はせっかく君と一緒にいられるのだもの、
時間を無駄にしたくない、
と紐をしばり巻物を懐にしまう。
気になったけれど、
祝君の池に張った氷のような美しさに気圧されて、
それ以上聞くことができなかった。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
祝君の飴色の目が宙を泳ぐ。
どこか遠くの、僕には見えない世界を眺めているようだった。
上瞼の端から端までラクダのようにぎっしり生えた睫毛が、
とんぼの羽のように上下に細かく動く。
睫毛の黒と、竹の下で青みがった白い肌の対比が鮮やかだった。
祝君が唐突に、
君は結婚についてどういう風に考えているのか?
と聞いた。
頬の火照りを感じながら、
よくわからない、まだ学生だし考えたこともないよ、
君こそどうなんだよ?
とごまかす。
祝君は一方的に好きな人はいるのだけど、
相手がどう思っているかわからない、
とのこと。
祝君は長く細い首の上に座った、
卵型の顔を僕に真っ直ぐ向ける。
僕をじっと凝視している。
鼻筋には白い光りがすっと通っている。
下瞼から頬の上側にかけては、
頬紅をはたいたかのように赤みがかっていた。
花びらのような唇はしっとりと濡れているようだった。
僕は祝君の隣にいて似合う女の子なんているのかしら、
と思った。
祝君が目をそらして少しはにかみながら言った。
「僕には妹がいるんだ。
僕と同じ顔をしていて、
ちょっと男っぽいのだけど会ってみる気はないかい?」
頬の暑さが益々増し、体全体に広がる。
僕の顔は今きっと真っ赤だろう。
僕は祝君から顔を背けた。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
さわさわと竹の葉がこすれあう音がする。
心臓でどくどくと鳴り響く音が次第に静かになる。
麻の夏服を着た祝君のようなさわやかな風がふいた。
頬の熱も大分ひいてきた。
僕は祝君を振り向いた。
祝君の白目はうるんで黒目が炎の中のガラスのようにグラグラと輝いている。
瞳孔の奥から何か墨色の物が、
矢のように何本も飛んでくる。
寝ぼけて書いたへろへろの字みたいだった。
僕はそれを必死で読み取ろうとする。
けれどもそれは字らしきものへと形を整えるやいなや、
ぐしゃっと潰れてしまう。
頭の中に祝君の声みたいなものが入り込んできた。
それは遠くで聞く囁き声の如く始まり、
除々にはっきりとしてくる。
しかし何とか聞き取ろうとするとすぐに調子が崩れて、
キィンとした耳鳴りの音になってしまう。
 宇美の文学
宇美の文学