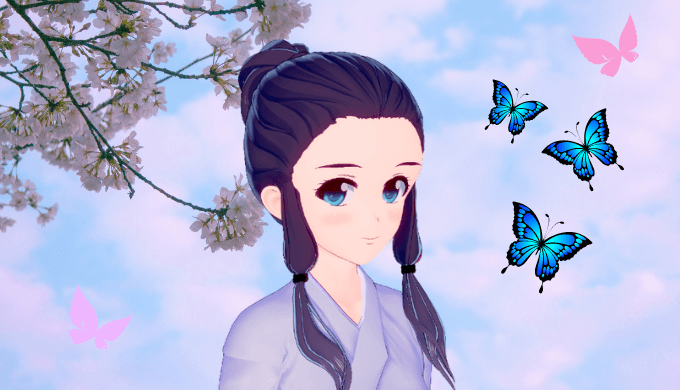後ろから意地の悪そうな笑い声が聞こえた。
振り返れば金栄達だった。
ニヤニヤと歯をむき出して嘲り声を上げている。
悪童達は揃ってしきりに僕の胸元を指さしている。
僕の左手には木簡がにぎられていた。
木簡には六歳の子が書いたみたいな下手くそな字で
上から下までびっしりと、
祝英台、祝英台、祝英台……と書き連ねてあった。
この見覚えのある筆跡は確かに僕のものである。
僕は何か言いたかった。
けれども、ただただ口を半開きにして下顎をあたあた震わせているだけだった。
カチャリと音がした。
落書きが描かれた板切れが、
僕の前に放り投げられていた。
髪を揚巻に結い上げた二人の素っ裸の人間が、
体を変な風に互いに絡ませ合っている。
貧相な絵だった。
このほっそりとした睫毛の長いのが祝君で、
四角い顔に真ん丸く大きな鼻のたれ目の小太りが僕であろう。
二人の口元からは幽霊みたいな吹き出しがついている。
そこにはミミズののたくったような墨の染みで、
台詞が書き殴られていた。
口に出すのも憚られるような淫らなものばかりだった。
体中をどろどろとした熱い溶岩が流れていく。
怒らねば、怒らねば、さあ怒るぞ!
怒鳴り声を出そうとしたのに、
上唇と下唇の隙間に透明な壁があるかのようだ。
言葉が出てこない。
出口を失った憤りの文句は、
また喉に戻り顔に上がって涙となって目から零れた。
ひやかしはカラスの集会みたいで、
刻々とひどくなる。
ああ祝君ならこんな時は高く澄んだ切れ味の良い声で一喝し、
彼らを黙らせるのに!
それでいて最後には皆を笑顔にさせるのに!
やかましいわい!
という雷鳴の如き一声が響いた。
膝近くまである白い顎ヒゲをなでながら
柳老師が教室に入ってくる。
生徒達は水をかけた蟻のように散り、
めいめいの席へと戻る。
柳老師が例の嫌らしい悪戯書きを拾う。
これは金栄君の字だね、
とおっしゃると奴はしなしなと前に進みでた。
僕、梁と祝が相撲を取っているところを描いただけなんです、
それだのに梁の奴が急に怒り出して……
と柳老師を上目遣いで見つめる。
柳老師は今度やったら退学だぞ、
とねめつけると教壇に立ち、
話しだした。
 宇美の文学
宇美の文学