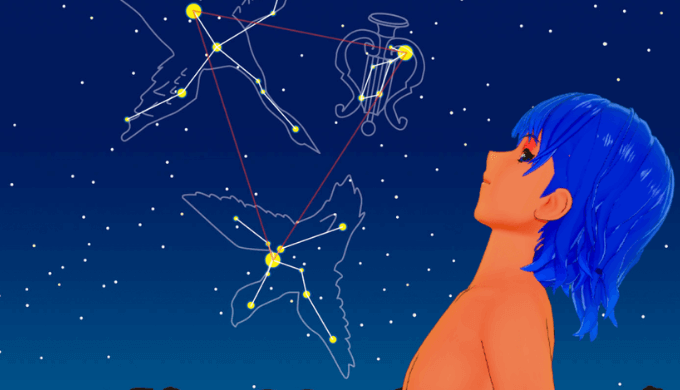僕はキユの居室のあるバンガローに向かった。
キユは少年の頃から相当なナルシストだった。
だけど以前は鏡の中の我が身に見惚れて喜んでいたりするのは人目を避けてのことで、
僕が来ると、急いで鏡を隠したものである。
人に知られても平気で、
堂々と、終日鏡を見ているというのは異常である。
今は短い乾季の真っ只中の、
一年で一番よい季節だ。
そんな時に家に閉じこもって、
自分に見とれているなんて……
そんな自惚れも女とか、
思春期の少年ならまだ可愛いが、
いくら若く見えるといったって彼はもう三十近いのである。
僕が戻ってきたからには何としても外に引きずり出してやろう、
と足音をどすどすいわせながら、
節くれだった丸太の階段を登った。
僕は富士山のプリントされた簾を上げる。
薄暗い中、彼はてるてる坊主形の濁った白の着物を着て、
草を編んだ丸い茣蓙の上に胡坐をかいていた。
原始的な貫頭衣の襟元はボートネックティーシャツに似ていて、
襟ぐりの線に、ほぼ平行にくっきりとした鎖骨が出ていた。
荒っぽい布は、なで肩に沿って直線的に下へと落ちて、
丁度五部袖となっている。
大きく開いた袖口から尖った肘が顔を出している。
その先からは肉を感じさせないが、
しなやかな子供のような腕が伸びていた。
腕の先には、体に対して大きくて平べったい手がついている。
骨ばった細く長い指で、
黒い蒔絵細工の枠の鏡を支えていた。
手を肩幅に開くと、ちょうどぴったりと収まるサイズの鏡を、
両手で車輪を転がすように動かしながら覗き込んでいる。
飴色の目は池の奥深くの珍しい魚を、
興味津々に観察しているようだった。
背を向けたまま、
振り返ろうともしない。
僕は後ろまでいくとキユの目の前に、
ウェストポーチの奥に押し込んであった、
文庫本の『未開部族の神話と伝承』を押し付けてやった。
キユは声変わりしたばかりの少年のような声で、
取ってくれ、と落ち着き払った調子で僕に命じた。
僕は、
「鏡よ鏡、この世で一番のハンサムはだあれ? と聞いているのかい?
そして鏡はそれはおまえだと答えてくれたかい? 」
とからかいながら本をはずした。
キユはいつか話してあげた白雪姫の話を覚えていたようだ。
鏡は僕ではないのだから、
そんなことは言わない、
と唇をさざなみのように震わせて笑う。
では、いったいなんで鏡ばかり見ているのだろう?
 宇美の文学
宇美の文学