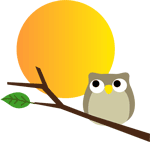あらすじ
プロローグ
ある年の九月のことでした。
主人公(初老の男性、京都の岡本在住)はあまりに天気がよかったので、午後三時過ぎごろからふと思い立って散歩にでかけます。
目的地は水無瀬の宮(後鳥羽院の離宮があった旧蹟)でした。
このあたりは昔、高貴な人が遊びに使ったり、過去にいろいろなことが起こった場所です。
歴史好きな主人公は過去に起こった出来事に思いをはせながら散策をしていていると、時刻はもう夕方の6時。
主人公は帰りに月見もしたいと思います。
うどんやで夕食をとり、うどん屋の主人に
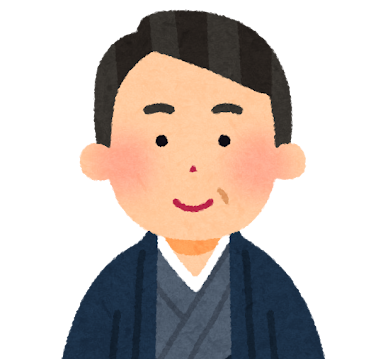 主人公
主人公
それならば直じきこの町のはずれから向う岸の橋本へわたす渡船がござります、
渡船とは申しましても川幅が広うござりましてまん中に大きな洲すがござりますので、こちらの岸から先ずその洲へわたし、そこからまた別の船に乗り移って向う岸へおわたりになるのですからそのあいだに川のけしきを御覧になっては
と教えてくれました。
そこで主人公はうどんやで買ったお酒を持って、舟に乗りました。
主人公は舟の乗って洲で降ります。
洲からの眺めが気に入った主人公は、船頭に
いや、いずれあとで乗せてもらうがしばらく此処で川風に吹かれて行きたいから
と三角形の洲の先っぽに向かって歩いていきます。
蘆の生い茂る水際まで行くとそこでうずくまりました。
ここに座ると川の真ん中に舟に乗っているのと同じように、川の両岸の景色を好きなように眺めることが出来るのです。
歴史好きな主人公はかつてこのあたりを舟に乗って徘徊したという遊女たちのことに思いを寄せたりします。
主人公はよい気分になり詩吟を歌います。
すると近くの蘆の葉がざわざわとゆれて、主人公と同じ年頃の初老の男性が現れました。
風流ですなあ。
私も歌いたくなりました。
よろしかったら聴いて下さい
そんな会話を交わして二人はすっかり仲良くなってしまいました。
主人公は男にこう聞きます。
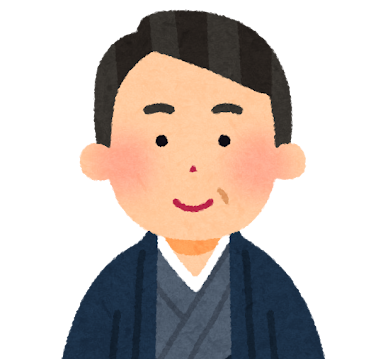 主人公
主人公
 男
男
私は七つか八つの幼いころから毎年十五夜には巨椋池へ月見にまいるのですよ……
そして男は昔話を始めましたが、ここからがこの小説の本題なのです。
少年時代の思い出
男が五歳ぐらいの幼い頃に男の母親は、あの世の人となりました。
男が七つ、八つの頃から、父親は毎年十五夜の晩になると、息子を連れて、月の下の道を二里も三里も歩きます。
そしてたどり着いたところは巨椋池のほとりのお金持ちの別荘でした。
屋敷の前では琴や三味線や胡弓の音色が聞こえます。
父は屋敷の生け垣が少しまばらになっている隙間から中をのぞいて、じっと立っています。
立派な庭には泉があり、泉の上には突き出した小さな建物があります。
そこに五六人の男女がいて、お月見の宴会をしているようでした。
琴や三味線を弾いている女性や胡弓を弾いている男性がいました。舞を舞っている女性もいます。
金屏風が置いてあって、それに蝋燭の火が映っています。
他の人の恭しい様子から、琴を弾いている女性がこの家の女主人らしいのでした。
当時の京都や大阪の裕福な商人の家では上女中には大名や武家の奥女中のような恰好をさせ、礼儀作法もしっかり教育し、芸事を習わせることもありました。
おそらくこの屋敷もそのような裕福な商人の別荘なのでしょう。
そして琴を弾いた女主人はその裕福な商人の奥さんなのでしょう。
生け垣の合間から覗いているので、女主人の顔ははっきりとは見えないのですが、化粧の濃さや着物の色合いなどからまだ若い女性のようです。
女主人の声は
 女主人
女主人
 女主人
女主人
少年は父親に、
 少年
少年
と言った後、
 少年
少年
しかし父は
 父
父
父は無言で随分と長い時間お月見の様子を見つめていました。
お月見が終わってその人たちが座敷をひきあげてしまうまで見ていたのです。
そして屋敷の人がひきあげてしまってから、やっと父と息子はとぼとぼと堤の上を歩いて家に帰ったのです。
父と息子は毎年のように、こうしてこのお金持ちのお月見を覗き見に行きました。
或る年の帰り道、父は息子についに屋敷の女主人の正体について語ってくれました。
あの屋敷の女主人は「お遊様」と言って、かつて父の恋人だったのです。
お遊様
お遊様は大阪の裕福な商家の娘です。
十七歳の年に美貌を見初められて、実家と同格な大阪の裕福な商家に嫁ぎました。
しかし四、五年後、亭主があの世の人となりました。
二十二三の若さで未亡人となってしまったのです。
明治初年のことで、まだ古い風習が残っています。
また実家にも嫁ぎ先にも旧弊な考え方で、口うるさい老人がいました。
またあの世の人となった夫とのあいだには男の子が一人ありましたのでなかなか再婚ということは許されませんでした。
お遊様は嫁ぎ先にぜひ、と頼まれてお嫁に行ったのです。
嫁ぎ先では姑にも夫にもたいへん大事にされて、実家にいたときよりも、我がままにのんびり暮らしていたぐらいでした。
未亡人になってからも時々、大勢の女中さんを連れて物見遊山に出かけていきます。
はたからみても不幸そうではありませんし、本人もとくに自分の境遇に不満を感じている様子には見えませんでした。
父がお游様に出会ったのはそんな時です。
父は当時二十八歳で、当時としては結婚が遅いほうでした。
それは女性のえりごのみが激しいからでした。
父は大名風、御殿風の趣味があって、品のよい貴婦人のような女性が好みでした。
たとえば打掛を着て、几帳の影に座って、源氏物語を読んでいるのが似合う……
そんな女性と結婚したかったのですが、なかなか見つかりません。
ちなみに当時は父も大阪、船場の裕福な商人の息子でした。
お遊様の実家や嫁ぎ先と同格の家の息子だったようです。
当時の大阪の裕福な商人は小さな大名などよりも貴族的なところがあるほどだったので、貴婦人のようなお嫁さんをもらって養うことも父にとっては不可能ではないのでした。
父、二十八歳、お遊様、二十三歳の時でした。
道頓堀に観劇に行ったときに、劇場の桟敷で二人は出会います。
お遊様の女中にものを言うときの、口のききかた、そのほかの態度や物腰の鷹揚な様子から、父は、彼女こそ自分の探し求めていた女性だ、と直感します。
なによりも父のこころを惹いたのはお遊さんの「蘭ろうたけた」ようすでした。
お遊さんという人は、写真を見ますとゆたかな頬をしておりまして、童顔という方の円まるいかおだちでござりますが、父にいわせますと目鼻だちだけならこのくらいの美人は少くないけれども、おゆうさまの顔には何かこうぼうっと煙っているようなものがある、
かおの造作が、眼でも、鼻でも、口でも、うすものを一枚かぶったようにぼやけていて、どぎつい、はっきりした線がない、じいっとみているとこっちの眼のまえがもやもやと翳かげって来るようでその人の身のまわりにだけ霞がたなびいているようにおもえる、
むかしのものの本に「蘭ろうたけた」という言葉があるのはつまりこういう顔のことだ、
おゆうさまのねうちはそこにあるのだというのでござりましてなるほどそう思ってみればそう見えるのでござります。
大体そういう童顔の人は所帯やつれさえしなければわりあいに若々しさを失わないものでござりますがお遊さんは十六、七の時から四十六、七になりますまで少しも輪郭に変りがなくていつみても娘々したういういしいかおをしていた人だと叔母なども始終そう申しておりました。
でござりますから父はその、お遊さんのぼうっとした、いわゆる「蘭ろうたけた」ところに一と眼でこころをひかれたのでござりまして父の趣味をあたまにおいてお遊さんの写真を見ますとなるほどこれなら父が好すいたであろうということが分ってまいるのでござります。
つまり一と口に申しますなら、古い泉蔵いずくら人形の顔をながめておりますときに浮かんでまいりますような、晴れやかでありながら古典のにおいのするかんじ、おくぶかい雲上の女房だとかお局つぼねだとかいうものをおもい出させるあれなのでござります。
父の妹はお遊様の幼友達で、お游さんのことをよく知っていました。
父の妹によると、お遊様には兄弟が沢山いましたが、お遊様が一番両親に可愛がられていました。
どんなわがままでもお遊様なら、許されるという特別あつかいをされていたそうです。
しかしそれを他の兄弟たちはねたんだりせず、あたりまえのように考えていたそうです。
もちろんお遊様が自分から自分を特別扱いしてほしいと言ったり、威張ったり他人を押しのけたりするようなことはありません。
まわりの者がかえっていたわるようにしましてその人にだけはいささかの苦労もさせまいとして、お姫さまのように大切にかしずいてそうっとしておく。
自分たちが身代りになってもその人には浮世の波風をあてまいとする。
おゆうさんは、親でも、きょうだいでも、友だちでも、自分のそばへ来る者をみんなそういう風にさせてしまう人柄
お游様とはそういう人でした。
お遊様は自分の身の回りのどんな細かい事でも自分でやったことがありません。
姉妹たちがまるで腰元のようにお遊さまの世話をやくのですが、それが少しも不自然ではなく、姉妹たちに世話を焼かれているお遊様がたいへんあどけなくみえるそうです。
父は妹からそんな話を聞いて、ますますお遊様が好きになりました。
父の妹はお遊様と同じ先生に琴を習っています。
ある日琴のおさらい会が開かれ、それにお遊様も参加することになりました。
父は妹についてお遊様のおさらい会に行きます。
お遊様は髪をおすべらかしにして、打掛をきてお香をたいて、歌いながらお琴を弾きます。
父はお游様の貴婦人のような姿や美しい琴唄にすっかり感動しました。
父が楽屋を訪ねるとお遊様はまだおすべらかしに打掛姿でした。
そしてこう言います。
 お遊様
お遊様
父はお遊様も自分と同じように御殿風の趣味を持っているのだと知り、ますます自分の妻にすべき人はお遊様をおいてほかにない、と思うようになりました。
父は妹に自分のお遊様に対する思いを伝えました。
しかし、妹は
 妹
妹
というのは妹によれば、お遊様にはこれから養育しないといけない幼い息子がいます。
それも豪商の大事な跡取り息子です。
息子を置いてお遊様がお嫁にいくわけにはいきません。
また嫁ぎ先でも実家でもお遊様をああいう風に甘やかしているのは、そのかわり一生夫に操をたててほしいと思っているからです。
妹は
 妹
妹
お遊様には「おしづ」という妹がいます。
おしづはお遊様の家に月のうち半分は泊まりに行っているぐらい仲良しの姉妹でした。
父親は「おしづ」にはあまり興味はありません。
おしづも美しい娘でしたが、お遊様に特有のお姫様のような気品はありません。
父親は最初「おしづ」と結婚してもしょうがないと思いますが、だんだん心が動きます。
というのは「おしづ」と結婚すればこれからたびたびお遊様に会えるようになるわけです。
またそうでもなかったら、これからめったにお遊様には会えることもないでしょう。
父はそう考えて「おしづ」と見合いをするようになりました。
おしづとの結婚話が合って以来、おしづの仲良しの姉である、お遊様ともたびたび会うようになりました。
もともと本命はお遊様だった父は、縁談をずるずる伸ばします。
ある日お遊様に父はこう言われます。
 お遊様
お遊様
 父
父
 お遊様
お遊様
お遊様にこう言われて父親はおしづと結婚することを決心しました。
おしづの決意
父とおしづは婚礼を挙げました。
新婚初夜となりました。
おしづは夫にこう言います。
 おしづ
おしづ
ですからあなたと夫婦の契りを交わすのは姉さんにすまないと思っています。
私とはうわべだけの夫婦で結構ですから、姉さんを幸せにしてください。
父親はお遊さんも自分を愛していたことを知って驚きます。
おしづはお遊様から自分の夫への恋心を打ち明けられたわけではありません。
ただお遊様の様子や顔色からそうだと確信したのでした。
またおしづは夫のお遊様への恋心も気がついて居ました。
 おしづ
おしづ
あんさんはずいぶん今日までよいえんだんがありながらどれもお気にめさなんだとやらではござりませぬか、
そんなにむずかしいお方がわたしのようなふつつかなものを貰ってくださいましたのはあの姉があるゆえでござりましょう
おしづはこう言います。
 おしづ
おしづ
うわべだけの夫婦でいるのは私たち夫婦の間の秘密にしましょう。
 父
父
それではあなたが可哀想過ぎるではないですか。 私はもうこれからはお遊様のことはただの兄弟だと思うから私と夫婦になってください
ついに父親もおしづに負けて、おしづの言う通りにすることにしました。
つまり二人は肉体関係をむすぶことはありませんでした。
奇妙な関係
お遊様は妹夫婦がそんなことになっているとは知りません。
お遊様は表面的には仲睦まじい妹夫婦を見て、
 お遊様
お遊様
また三人はしばしば、一緒に芝居や遊山にでかけます。
時には遊びに行った先で、一二泊することもありましたが、そういう時は三人は同じ部屋で枕を並べて眠るのです。
お互いの家に泊まることもしょっちゅうです。
ある時お遊様が乳が張ってきたと言い、おしづに吸わせます。
父が
 父
父
 おしづ
おしづ
父はちょっとなめてみて
 父
父
それを見てお遊様はおもしろそうにころころ笑っています。
またおしづは三人だけになると、わざと席を外して、お遊さまと夫が二人きりになるようにします。
また並ぶときは必ず夫をお遊様の隣へ座らせます。
またかるた遊びの時は夫がお遊様の正面になるように座らせるのです。
お遊様が帯をしめてほしいと言ったときは
 おしづ
おしづ
また、お遊様に新しい足袋をはかせるときは
 おしづ
おしづ
おしづは何とか夫とお遊様を近づかせようとするのでした。
ある時おしづはお遊様に、自分たち夫婦の特殊な関係について告白してしまいます。
お遊様は
 お遊様
お遊様
 おしづ
おしづ
そんなことがあってももうすでに仲の良い姉と妹夫婦と近所中に知れ渡っているので、急に疎遠にするわけにもいかず、三人はあいかわらずの関係を続けました。
お遊様は娘の頃からお姫様のように育てられました。
お手洗いの後も、自分で手を洗わないで一人の女中さんがひしゃくで手に水をかけると、もう一人の女中さんが手ぬぐいで手を拭いてあげる、という風です。
お風呂で体を洗う時も、足袋を履くときも自分の手は使わないのでした。
そういう女性でしたから当初は出かけるときはお世話の女中さんがついていったのですが、おしづは
 おしづ
おしづ
そのころから父もおしづもお遊様を「姉さん」ではなく「お遊様」と呼ぶようになりました。そのほうがお遊様の人柄に合っていると二人とも思ったのです。
お遊様もこの呼び方が気に入ったようでした。
そして宿屋に泊まるときは父とお遊様を夫婦ということにして、一つの部屋に寝かせ、自分は女中ということにして、次の間に眠るのでした。
またお遊様を女主人ということにして、おしづが女中、父は執事、あるいは御贔屓の芸人ということにすることもあります。
夫婦そろってお遊様を
と呼んだりするのですが、これもお遊さまにとっては楽しい遊びの一つでした。
お遊様と父の関係はかなり打ち解けた親しいものでした。
ある時お遊様は、父にもういいと言うまで息をしないでくれ、と父の鼻の穴の前に手をかざします。
父は一生懸命我慢しますが、限界となって、息を漏らします。
お遊さまは
 お遊様
お遊様
そんなときのお遊様の顔はもともと童顔なのですが、幼稚園の子供の顔のようにあどけなく見えるのでした。
またある時は両手をついて首をたれたままかしこまっているように父に命じます。
またある時は父の顎の下や横腹をくすぐったり、そこかしこをつねったりして、
 お遊様
お遊様
また
 お遊様
お遊様
父がうつらうつらするとお遊様は目を覚まして、耳の穴に息を拭き入れたり、かんぜんよりで顔中をくすぐったりします。
父とお遊さまの関係は?
さてもともとお互いに恋しあっていた男女がここまで親しかったことを考えると、当然肉体関係を疑ってしまいます。
はたしてお遊さまと父の関係はどこまで進んでいたのでしょうか?
下記は男のことばの引用です。
 男
男
しかし、わたくし、ここでおゆうさんのためにも父のためにもべんめいいたしておかなければなりませぬのはそこまですすんできていながらどちらも最後のものまではゆるさなんだのでござりました。
それもまあ、もうそうなったらそういうことがあってものうても同じことだと申せましょうしないにいたしましたところがなんのいいわけになりはいたしませぬけれどもわたくしは父の申しますことを信じたいのでござります。
父がおしずに申しましたのにはいまさらになってそなたにすむもすまないもないようなものだがたといまくらを並べてねても守るところだけは守っているということを己おれは神かみ仏ほとけにかけてちかう、
それがそなたの本意ではないかも知れないがお遊さまもおれもそこまでそなたを蹈ふみつけにしては冥加のほどがおそろしいからまあ自分たちの気休めのためだというのでござりまして、いかさまそれもそうだったでござりましょうがまたまんいちにも子供ができたらばというしんぱいなぞが手つだっていたかと思われるのでござります。
つまりお遊様と父は男女の関係はなかったわけです。
しかし男はこうも言っています。
 男
男
けれども貞操というものはひろくもせまくも取りようでござりますからそれならといってお遊さんがけがされておらなんだとは申せないかもしれませぬ。
父の在名中に、男は父に桐の箱に入っていたお遊さまの着物を見せてもらいました。
中にはちりめんの友禅の長じゅばんが入っています。
ずっしりと重いものです。
父はこう言いました。
 父
父
このざんぐりしたしぼの上からおんなのからだに触れるときに肌のやわらかさがかえってかんじられるのだ、
縮緬ちりめんの方も肌のやわらかい人に着てもらうほどしぼが粒だってきれいに見えるしさわり加減がここちよくなる、
お遊さんという人は手足がきゃしゃにうまれついていたがこの重いちりめんを着るとひとしおきゃしゃなことがわかった
父は息子に思い出を語った後、長じゅばんを両手で持ち上げて
 父
父
あああのからだがよくこの目方に堪えられたものだ
と言いながら長じゅばんに頬ずりをしたといいます。
別れ
お遊様と父親がこのような不思議な恋を続けていたのはお遊様が二十四五歳のころから三、四年ほどの短い間でした。
お遊様が二十七歳の時です。
お遊様の息子が肺炎で命を落としました。
お遊様は日頃息子を乳母にまかせっきりにしていました。
その癖が抜けなかったのか、息子の看病中も半日ほど家を抜けてでたら、そのあいだに急に様子が変わり、重症になってしまったのです。
そのことでお遊様は「母親に落ち度がある」と世間から非難されてしまいました。
そこでお遊様の嫁ぎ先では、今は跡取りの孫息子もいなくなったし、近頃評判が悪いし、ということでお遊様に実家に帰ってほしいと思うようになります。
お遊様の実家では、両親は鬼籍に入り、お遊様の兄が相続しています。
お遊様は兄夫婦に大切に扱われますが、やはり両親が生きていた時ほど気ままにはすごせません。
おしづが実家にいづらかったら、私の家にいらっしゃいとお遊様にすすめます。
しかし近頃は三人が仲が良すぎることを噂をする人たちもいました。
しばらくは慎んだほうがよい、ということでお遊様は実家で暮らしていました。
それから一年ほどたちました。
お遊様の兄がお遊様に再婚をすすめます。
兄はお遊様とおしづ夫婦の特殊な関係を感づいていてなんとかしたいと考えていたようです。
縁談の相手は、造り酒屋の主人でお遊様よりだいぶ年上でかなりのお金持ち。
造り酒屋は前からお遊様のことを知っていて、その美貌と気品を気に入っていました。
前の嫁ぎ先よりも贅沢に暮らさせてあげる
と言います。
兄は
とお遊様に勧めます。
当時の旧家のことですからお遊様もなかなか断れません。
父はいっそのこと、お遊様と心中をしようかと思います。
おしづも
 おしづ
おしづ
しかし父は
お遊さんのような人はいつまでもういういしくあどけなく大勢の腰元たちを侍はべらせてえいようえいがをしてくらすのがいちばん似つかわしくもありまたそれができる人でもあるのにそういう人を死なせてしまうのはいたいたしい
と考えて心中はとりやめとしました。
そしてお遊様に自分の考えを打ち明けます。
そしてその時のお遊様の態度もいかにも彼女らしい品のよいものでした。
父はそのきもちを打ちあけましてあなたはわたしの道づれにするにはもったいない人だ、
普通のおんななら恋に死ぬのがあたりまえかもしれないがあなたという人にはありあまる福があり徳がある、
その福や徳をすてたらあなたのねうちはないようになります、
だからあなたはその巨椋の池の御殿とやらへ行ってきらびやかな襖ふすまや屏風びょうぶのおくふかいあたりに住んでください、
あなたがそうしてくらしていらっしゃるとおもえばわたしはいっしょに死ぬよりもたのしいのです、
こういったからとてよもやあなたは私がこころがわりしたの死ぬのがこわくなったからだのというようなふうには取らないでしょう、
そんなせせこましいりょうけんが薬にしたくもない人だから私も安心していえるのです、
あなたは私のような者を笑ってすててしまうほど鷹揚にうまれついた人ですとそういったのでござりました。
そうしたらお遊さんは父のことばをだまってきいておりましてぽたりと一としずくの涙をおとしましたけれどもすぐ晴れやかな顔をあげてそれもそうだとおもいますからあんさんのいう通りにしましょうといいましたきりべつに悪びれた様子もなければわざとらしい言訳いいわけなどもいたしませなんだ。
父はそのときほどお遊さんが大きく品よくみえたことはなかったと申すのでござります。
さてお遊様の新しい夫は遊び人でした。
結婚してまもなくお遊様に飽きてしまい、めったにお遊様のいる別荘へよりつかなくなりました。
しかしそれでもあの女は床の間の置き物のようにしてかざっておくにかぎるといいまして金にあかしたくらしをさせておきましたのでお遊さんは相変らず『田舎源氏いなかげんじ』の絵にあるような世界のなかにいたわけでござります
男の誕生
父はお遊様と別れてからだんだん、おしづにあわれをもおよして、夫婦の契りを結びました。おしづは息子を生みます。
数年後おしづは幼い息子を残して命を落とします。
さてお遊様が再婚した頃から、お遊様とおしづの実家も父の家もだんだん落ちぶれていきます。
おしづがあの世の人となった頃には、父と息子は、長屋に住むような暮らしになってしまいました。
おしづが生んだ息子が七、八歳になると、父は十五夜の夜に息子を連れて、お遊様の住む巨椋池の別荘に連れて行くようになりました。
毎年のように親子揃って、お遊さまのお月見を眺めていたのです。
男は幻?
男がそこまで話すと私は男にこう尋ねます。
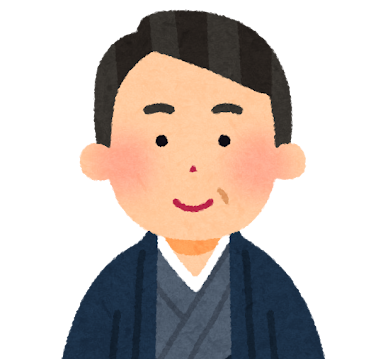 主人公
主人公
男はこう答えます。
 男
男
さようでござります、
今夜もこれから出かけるところでござります、
いまでも十五夜の晩にその別荘のうらの方へまいりまして生垣のあいだからのぞいてみますとお遊さんが琴をひいて腰元に舞いをまわせているのでござります
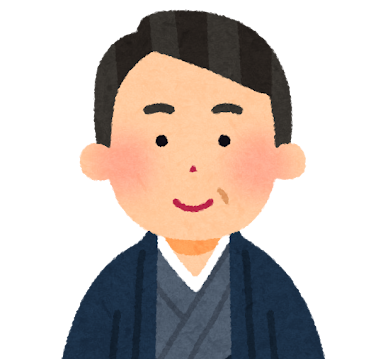 主人公
主人公
ただそよそよと風が草の葉をわたるばかりで汀みぎわにいちめんに生はえていたあしも見えずそのおとこの影もいつのまにか月のひかりに溶け入るようにきえてしまった。
感想
おなじみの「女王様」が登場する谷崎潤一郎らしい作品です。
『卍』と『春琴抄』や『鍵』を髣髴とさせる場面が何箇所かあります。
ただ登場人物が道徳的でヒロインもエキセントリックさがないため上品で、万人受けしそうです。
『卍』や『鍵』はスキャンダル小説ですし、『春琴抄』は文章や描写は美しいけれど、佐助と春琴の関係は異常だし、春琴は決して好ましい女性ではありませんよね。
しかしこの三篇の小説の要素がありつつ、だいぶ薄められている『蘆刈』はストーリー自体が美しい恋愛小説だといえると思いました。
ヒロインのお遊様も現代の価値観には合わないけれども、古風な「お姫様」「貴婦人」としては理想形でしょう。
構成が現在→過去→さらに過去→そして現在となっているというのも面白いですね。
また男が消えていなくなってしまいこの話は主人公がお酒に酔っ払った中で見た幻か?となるのもはかない恋愛小説のラストにぴったりです。
ただ前半は古典や歴史の教養がなかったり、京都大阪の地理に詳しくないとかなり読むのがツライでしょう。
このあたりの古典や歴史に詳しかったり、京都大阪在住の人にはかえって面白いのかもしれませんが、残念ながら、私には退屈で途中で読書を中断してしまおうかとも思いました。
男が少年時代の回想をするところからは俄然面白くなるので、ここまでで読者を脱落させてしまう可能性があるのは、ちょっともったいない気がします。
また、ひらがなが多く句読点が少ない文章なのですが、少し読みにくいです。
後半はストーリーが面白いので気にならなかったのですが、前半はただでさえ読みにくいのに読みにくさに拍車をかけていました。
谷崎潤一郎のまとめページ
https://umiumiseasea.com/tanizaki/
PR
本の要約サービス SUMMARY ONLINE(サマリーオンライン)月額330円で時短読書 小説の要約も多数あり!!谷崎潤一郎 まとめ記事
 谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
 宇美の文学
宇美の文学