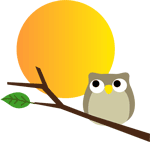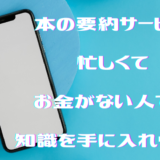はじめに
大正八年の五月のある日、小説家谷崎潤一郎のところに、手紙が届きました。
それは野田宇之吉という、若い画学生からの手紙です。
手紙の内容は画学生のみずからの経験をつづったものでした。
画学生は自分の経験は価値があるから、ぜひ谷崎先生の文才で小説にしてほしいと頼みます。
さて画学生はどのような経験をしたのでしょうか?
細かい女性美の描写が圧巻の足(または脚)フェチ文学です。
ネタバレ
登場人物紹介とその経歴
山形県の片田舎に育った主人公の画学生は、西洋の美術に憧れ、美術学校で西洋画を学ぶために上京しました。
初めて東京へ出てきたとき、他に頼るあてもなかったので、父の紹介状を手に遠い遠い親戚の塚越という老人を訪ねます。
塚越は六十歳ぐらい。
今ではまだまだお年寄りという年齢ではありませんが、この小説が書かれた大正時代では六十歳といえばもうおじいさん、おばあさん。
よってこれ以降、彼を塚越老人と呼びます。
塚越老人は江戸時代から質屋をいとなんでいる家の隠居でした。
塚越老人が始めて結婚したのは二十歳の時でした。
その後三度も妻を取り換えて、三十五歳に三度目の妻と離縁してから、ずっと独身で暮らしていました。
大変な道楽者で花柳界の女性との付き合いはずっと絶えませんでした。
しかし芸者買いをするにも非常に移り気。
一人の女を気に入っても一か月もたたないうちに飽きてしまい、別の女に夢中になるという風でした。
そういったわけで、長年女性との付き合いは沢山あったにもかかわらず、決まった恋人、というのがいないままで六十代に入ったのです。
ところが六十歳の時、富美子というまだ十六歳の柳橋の芸者を好きになります。
塚越老人の富美子への熱の入れかたは普通ではありませんでした。
まだ半玉だった彼女が一人前になるための費用をすべて面倒をみてやったそうです。
しかしそれだけでは物足りなくなって塚越老人は彼女を身請けして妾にしたのでした。
塚越老人は富美子に夢中ですが、富美子の方では決して塚越老人を好いていたわけではありません。
何しろ四十歳以上の年の差があるわけです。
恐らく富美子は塚越老人の財産目当てなのでしょう。
画学生は上京した時に塚越老人を訪ねた後も、年にに三度は塚越老人を訪ねましたが、数年の間は表面的な交際でした。
塚越老人は交際が義理一遍の付き合い以上に密接になったのは、塚越老人がなくなる一年、半年まえぐらいからになります。
塚越老人は明治維新前の江戸の下町に生まれ、江戸時代の古い習慣や伝統を尊び、気障なところがあり、通人ぶったりする下町趣味の老人。
一方画学生は山形県の片田舎の出で西洋の文学や美術に憧れ、将来は洋画家になりたいと考えている若者。
二人の趣味や興味の対象は全く一致しません。
しかしそれでも親しくなったのは、老人が家族に嫌われている、という孤独な境遇が原因でした。
妾の富美子をのぞいては塚越老人と親しいのは画学生ただ一人だったのです。
孤独な塚越はしょっちゅう訪ねて親しくしてくれる画学生が嬉しかったのでしょう。
塚越老人は六十三歳で亡くなりました。
亡くなった時は鎌倉の別荘に住んでいて、店は養子の角次郎に譲っていました。
東京の家族と仲が悪い塚越老人の臨終のときにかけつけたのは一人娘初子のみでした。
そういったわけで、隠居の病気の様子や亡くなる前後のことなどをよく知って居るのは、小間使いと妾の富美子、画学生のみでした。
富美子との出会い
画学生が初めて富美子に会ったのは、塚越老人がまだ東京に住んでいた時のことでした。
画学生が塚越老人の隠居部屋がある、奥まった離れ座敷に通されると塚越老人が
さあ、まおはいり。
さあ、まあずっとこっちへ。
と出迎えてくれます。
江戸っ子特徴の巻き舌で落語家のような滑らかな声です。
塚越老人に対面する形で、一人の見慣れない意気な女が座っていました。
彼女が塚越老人の妾の富美子です。
富美子は
となよなよとなまめかしく挨拶しました。
富美子がどんな美女であるかは次のように事細かに描写されています。
卵なりにすぼんでいる頤の中に、
釣合よく収まるくらいな可愛らしい小いさな口で、
殊に最も可愛らしいのは江戸児の特長ともいうべき受け口の下唇でした。そうです、
あの下唇がもし尋常に引込んでいたとしたら、
あの顔はもっと端厳にはなっても、
あの媚びるような味わいと、
狡猾そうな、
利口そうな趣は失せてしまうだろうと思います。利口といえば何よりも利口そうなのはその眼でした。
パッチリとした、
青貝色に冴えた白眼の中央に、
瑠璃のように光っている偉大な黒眼は、
いかにも利口そうに深く沈んでいて、
ちょうど日光を透き徹している清洌な水底に、
すばしこい体をじっと落ち着けて、
静かに尾鰭を休めている魚のようでもありました。そうして、魚の体を庇うている藻のように、
その瞳の上を蔽うている睫毛の長さは、
眼を瞑ると頰の半ばの所にまでその毛の先が懸るほどでした。僕は今まであんなに立派な、
あんなに見事な睫毛を見たことはありません。あんなに睫毛が長くては、
かえって瞳の邪魔になりはしないかと思われるくらいでした。眼を睜いていると、
睫毛と黒眼との繫がりがハッキリ分らないで、
黒眼が眼瞼の外へはみ出しているようにさえ見えました。殊にその睫毛と瞳とを際立たせているのは、
顔全体の皮膚の色でした。この頃の若い女としては、
(殊に芸者上りの女としては、)
極めてあっさりとした薄化粧の地肌が、
そんなにケバケバしくなく、
曇硝子のような鈍味を含んで、
血の気のない、夢のようなほの白さを拡げている中に、
その黒眼だけがくっきりと、
紙の上に這っている一匹の甲虫のように生きているのです。
画学生はいつもの年は適当に挨拶したらさっさと帰ってしまうのですが、こんな美女がいたため、ついつい長居してしまいます。
その日は朝から午後の二三時ごろまでごちそうになりました。
富美子のおしゃくで塚越老人も画学生もだいぶ酔いました。
お酒を飲んでいい気持ちの塚越老人がこんなことを言います。
宇之さんや、失礼ながら私はまだお前さんの画いた絵というものを見たことはないんだが、西洋画を習っていなさるんだから、油絵の肖像画を画くことなんかはうまかろうね。
すると富美子がこう言います。
うまかろうねだなんて、随分ですわね。
あなた怒っておやんなさいよ。
うまかろうねといったって、何も私は宇之さんを馬鹿にした訳じゃあごわせんよ。
私はご承知の通り旧弊な人間で、油絵なんて物はうまいもまずいも分からない方だもんだから……
(富美子)
まあおかしいこと、分からないなら猶更あなた、そんないい方するッてえ法はありゃしないわ。
こんな風なませた口ぶりで塚越老人の言葉を冷かしたりたしなめたりしている富美子はこの時やっと十七歳でした。
富美子にたしなめらえるたびとごに塚越老人は、目元口元に何ともいえない嬉しそうな微笑みを浮かべます。
その嬉しそうな表情があまりにむき出しなので、画学生はなんだか自分が恥ずかしくなってしまいました。
塚越老人はときどき
と頭をかいてわざと大げさに恐縮してみせます。
その様子がすっかり富美子の手の中に丸め込まれて、好人物になりきってしまっていて、大きな赤ん坊のようにたわいがないのです。
年齢の順は当時の塚越老人の年が六十一、画学生が十九、富美子は十七歳。
三人の中で富美子が一番若いのですが、口の利き方から判断すると、ちょうど順序がその逆であるかのようでした。
富美子の前にでると塚越老人も画学生も子ども扱いにされてしまうのです。
富美子の肖像画を描くことに
さて塚越老人が急に油絵の話を持ち出したのは、画学生に富美子の肖像画を画いてほしいからでした。
うまいまずいは分からないが、油絵の方が何となく日本画よりは本当らしく見えるからね。」
塚越老人はこう言って、できるだけ富美子の姿を生き写しにしてくれと画学生に頼みます。
画学生は自分に塚越老人が満足するような富美子の肖像画が書けるかどうか自信がありませんでした。
けれども、これをきっかけに富美子と懇意になれたら、という思いが先に立って引き受けてしまいました。
ちなみに画学生には富美子とどうにかなってやろうというような野心はありません。
綺麗な富美子さんと今よりちょっとでも仲良くなれたらなあ!
という淡い恋心です。
それ以来、画学生は週に二回ぐらい塚越老人の家に通って、富美子の肖像画にとりかかります。
当初画学生は一般的な半身像の肖像画を画くつもりでした。
しかし塚越老人が画学生に厄介な注文をだすのです。
(塚越老人)
どうだろう、宇之さんや。
ただこう座った形を画いたって面白くもないから、一つこんな具合に、この絵の中にあるような形をさせて、こういう風にした所を画いてお貰い申す訳にゃあ行きますまいか。
塚越老人は古ぼけた草双紙を出してきて、その中に押絵の一つを画学生に見せました。
国貞の絵で若い女性がこんなポーズをとっています。
若い女が、
遠い田舎路を跣足で歩いて来て、
今しもとある古寺のような空家へ辿り着いたところが画いてあるのでした。女はその空家へ上り込もうとして、
縁側に腰をかけながら、
泥で汚れた右の素足を手拭で拭いているのです。上半身をぐっと左の方へ傾げ、
ほとんど倒れかかりそうに斜めになった胴体をか細い一本の腕にささえて、
縁側から垂れた左の足の爪先で微かに地面を蹈みながら、
右の脚をくの字に折り曲げつつ右の手でその足の裏を拭いている姿勢、
──その姿勢は、
昔の優れた浮世絵師が、
女の滑かな肢体の変化にどれほど鋭敏な観察を遂げ、
どれ程深甚な興味を抱いていたかという事を証明するに足るだけの、
驚くべき巧妙さを以て描かれているのでした。僕が最も感心したのは、
女がその柔軟な、
なよなよとした手足を多種多様に捻じ曲げているにもかかわらず、
ただ徒らに捻じ曲げているのみではなくて極めてデリケエトな力の釣合が、
全身に細やかに行き渡っている事でした。女は縁側に腰を掛けてはいるけれども、
決して安定な姿勢で腰かけているのではありません。今もいったように上半身を左方へ傾け、
右の足を外へ折り曲げているのですから、
縁に衝いている左の腕をちょいと引張れば、
すぐに平衡を失ってすとんと転んでしまいそうな危い恰好をしているのです。で、その危さを堪えようとして、
きゃしゃな体の筋肉を針線のように緊張させている点に、
いい尽せない姿態の美しさが発揚されて、
それが全身の至る所に漲っているのでした。例えば落ちかかって来る肩を支えている左の腕の先は、
掌がぴったりと縁側の床板に吸い着いて、
五本の指は痙攣を起したように波打っています。それから地面へ垂れている左の脚も、
ぶらりと無意味に垂れ下っているのではなく、
一杯に力が張られている証拠には、
その足の甲が殆んど脛と垂直に伸び、
親趾の突端が鳥の嘴のように尖っているのでも分ります。中でも一番微妙に描かれているのは折れ曲っている右の脚と、
その足を拭こうとしている右の手との関係でした。こういう姿勢を取った場合には、
必然そうでなければなりませんが、
折れ曲っている右の脚は実は右の手で無理に折り曲げられているので、
もしその手を放したら、
脚はぴんと地面の方へ弾ね返ってしまうのです。従って、手はその足を拭いているばかりでなく、
同時にそれを逃がさないようにと引張り上げていなければなりません。僕はここにも浮世絵師の巧緻な注意と有り余る才能とを認めない訳には行きませんでした。
なぜかというのに、
手がその足を引張り上げるのに、
踝を握るとか甲を摑むとかすれば比較的簡単であるものを、
わざとそうは画かないで、
足の薬趾と中趾との股の間に手を挿し入れ、
わずかに小趾と薬趾と二本の趾を摘まんだだけで、
辛くもその脚全体を持ち上げさせているのです。脚は今にも可愛い小さい手の中から二本の趾を擦り抜けさせようとして、
圧し着けられたぜんまいの如く伸びんとする力を撓めさせつつ、
宙に浮いた膝頭をぶるぶると顫わせています。こう申し上げたら、
僕の説明しようと努めている図面がどういうものであるか、
大概先生にもお分りになったでしょう。美しい姿をした女が、
枝垂柳のようにぐったりと手足を弛ませて、ぼんやりとたたずんでいる所や寝崩れている所も情趣はありましょうけれど、
この絵の如く全身をくねくねと彎曲させて、
鞭のような弾力性を見せている所を、
その特有の美しさを傷ける事なしに描き出すのは遥かにむずかしいに違いありません。
そこには「柔軟」と共に「強直」があり、
「緊張」の内に「繊細」があり、
「運動」の裏に「優弱」があるのです。
たとえば声を振り搾って喉も張り裂けんばかりに囀り続けている鶯の、
一生懸命な可愛らしさとでもいうべきものが現れているのです。
実際、これだけの姿勢にこれだけの美を与えるためには、
その女の手足の一本一本の指の先に至る筋肉にまでも、
十分な生命が籠っているように描写しなければなりません。
この女のこの姿勢は、
強いて嬌態を示さんがために工夫を凝らしたり誇張をしたりしたものでないとはいえますまいが、
しかし決して不自然な無理な姿勢ではありませんでした。
塚越老人はこの押絵と同じポーズを富美子にとらせて、画学生に油絵にしてもらうようにと頼みます。
しかしこんな難しいポーズはまだ修行中の画学生に到底かけるようなものではありません。
画学生は断りますが、塚越老人はなおもしつこく頼みます。
その時の塚越老人の顔つきがちょっと不思議でした。
物の言い方や態度はいつもと変わらないのですが、いつの間に眼の表情がすっかりかわっているのです。
何かじいっと見つめているような、眼が眼窩の底に吸い付いてしまったような一種異様に血走っためつきをしています。
それはたしかに、頭の中が急に乱調子になって気違いじみた神経がそこから覗いている事を暗示していました。
この眼つきの中には、何かしら尋常でないものが隠れているに違いない。隠居が親類の人たちから忌み嫌われる所以のものが、あるいはこの眼つきの蔭に醸されているのかもしれない。
咄嗟に僕はそう直覚しました。
同時に体中がぞっとするようなショックに打たれました。
富美子さんは塚越老人の目の色が変わりだすと、「またか」、というような困った顔をして「ちょッ」と舌を鳴らします。
何ですねえあなた、宇之さんの方で駄目だというものを、そんな無理をいったって仕様がないじゃありませんか。ほんとにあなたみたいな分らずやはありゃしない! 第一座敷のまん中で縁台へ腰かけたりなんかして、そんな面倒臭い真似をするのは私が御免蒙るわ。
すると塚越老人は今度は、今度は富美子に向かってぺこぺこと哀願してお願いだから、このポーズをとってくれと頼みます。
顔はにこにこ笑っていましたが眼は相変わらず血走っています。
富美子はついに我を折って、こう画学生に頼みます。
ほんとに宇之さんにはお気の毒ですけれど、この人は気違いなんだから手が附けられないんですよ。まあ画けても画けないでも構いませんから、当人の気の済むように真似事だけでもしてやって下さいな。
画学生は
そうですか、じゃあともかくもやってみましょう
と同意しました。
座敷の真ん中に夏の涼み台に使うような竹の縁台を持ち出して、そこへ富美子が腰かけて押絵の女と同じポーズをとります。
まもなく画学生は驚きます。
富美子は、押絵の女になりきってしまったのです。
画学生はこんな難しいポーズを見事にこなして、さらに絵の中の女と寸分たがわず美しく艶めかしい富美子にうっとりします。
押絵と富美子を見比べれば見比べるほどどちらが絵でどちらが人間だかわからなくなります。
はては国貞は富美子をモデルにしてこの絵を画いたのでは? とさえ思えてきます。
それにしても塚越老人はなぜ富美子にこのポーズをとらせたかったのだろうか? と画学生は考えました。
もちろんこのポーズをすれば富美子の体の妖艶な趣が平凡な姿勢よりもいっそうよく発揮されるに違いませんが、ただそれだけの理由で塚越老人が、あんな血走った眼をするほど無住になってのぼせ上がるはずがないと思われました。
画学生は富美子の撮っているポーズでは通常のポーズでは現れない女の肉体美の一部が出ていることに気が付きます。
それは、はだけかかった着物の裾からこぼれている脚、脛からつま先までの曲線でした。
実は画学生は、脚フェチ。
子供ころから若い女性の整った足の形を見ることに、異様な快感を覚える性質を持っています。
さてここからの富美子の足の描写がスゴイ!
真直ぐな、白木を丹念に削り上げたようにすっきりとした脛が、
先へ行くほど段々と細まって、
踝の所で一旦きゅっと引き締まってから、
今度は緩やかな傾斜を作って柔かな足の甲となり、
その傾斜の尽きる所に、
五本の趾が小趾から順々に少しずつ前へ伸びて、
親趾の突端を目がけつつ並んでいる形は、
お富美さんの顔だちよりもずっと美しく僕には感ぜられました。
お富美さんのような「顔立ち」は、世間に類がないことはありませんけれど、
こんな形の整った立派な「足」は今までかつて見たことがありません。
甲がいやに平べったかったり、
趾と趾との列が開いていて、
間が透いて見えたりする足は、
醜い器量と同じように不愉快な感じを与えるものです。
しかるにお富美さんの足の甲は十分に高く肉を盛り上げ、
五本の趾は英語のmという字のようにぴったり喰着き合って、
歯列の如く整然と列んでいます。
しんこを足の形に拵えて、
その先を鋏でチョキンチョキンと切ったらばこんな趾が出来上るだろうかと思われるほど、
それ等は行儀よく揃っているのです。
そうして、もしその趾の一つ一つをしんこ細工に譬えるとしたならば、
その各々の端に附いている可愛い爪は何に譬えたらいいでしょうか?
碁石を列べたようだといいたいところですが、
しかし実際は碁石よりも艶があり、
そうしてもっとずっと小さいのです。
細工の巧い職人が真珠の貝を薄く細かに切り刻んで、
その一片一片を念入りに研き上げて、
ピンセットか何かでしんこの先へそっと植え附けたら、
あるいはこんな見事な爪が出来上るかもしれません。
こういう美しいものを見せられるたびごとに、
僕はつくづく、
造化の神が箇々の人間を造るに方って甚だ不公平であることを感じます。
普通の獣や人間の爪は「生えている」のですが、
お富美さんの足の爪は「生えている」のではなく、
「鏤められている」のだといわなければなりません。
そうです、
お富美さんの足の趾は生れながらにして一つ一つ宝石を持っているのです。
もしその趾を足の甲から切り放して数珠に繫いだら、
きっと素晴らしい女王の首飾が出来るでしょう。
その二つの足は、
ただ無造作に地面を蹈み、
あるいはだらしなく畳の上へ投げ出されているだけでも、
既に一つの、
荘厳な建築物に対するような美観を与えます。
しかるにその左の方は、横さまに倒れかかろうとする上半身の影響を受けて、
ぐっと力強く下方へ伸ばされ、
わずかに地面に届いている親趾の一点に脚全体の重みをかけて、
趾の角でぎゅっと土を蹈みしめているのです。
そのために足の甲から五本の趾のことごとくが、
皮膚を一杯に張り切っていると同時に、
またどことなく物に怯えてぞっとしたような表情を見せつつ竦み上っているのです。
(表情という言葉を使うのは可笑しいかもしれませんが、
僕は足にも顔と同じく表情があると信じています。
多情な女や冷酷な人間は、
足の表情を見るとよく分るような気がします。)
それはちょうど、
何物かに脅やかされて将に飛ぼうとしている小鳥が、
翼をひしと引き締めて、
腹一杯に息を膨らました刹那の感じに似ていました。
そうして、
その足は甲を弓なりにぴんと衝立てているのですから、
裏側の柔かい肉の畳まった有様までが、
剰す所なく看取されました。
裏から見ると、
ちぢこまっている五本の趾の頭が、
貝の柱を並べたように粒を揃えているのでした。
もう一本の足の方は、
右の手で地上二三尺ばかりの空間に引き上げられているのですから、
全く異った表情を示していました。
「足が笑っている」といったら、
あるいは普通の人には腑に落ちないかもしれません。
先生にしても、
ちょっと首を捻って変な顔をなさるでしょう。
しかし僕は、
「笑っている」というより外にその右足の表情をいい現わすべき言葉を知りません。
ではその足はどんな形をしていたかというと、
小趾と薬趾と二本の趾を撮まれて宙に吊るし上げられているために、
残りの三本の趾がバラバラになって股を開き、あたかも足の裏を擽られる時のように、
妙なしなを作って捩れているのでした。
そうです、
足の裏が擽ったい時などに、
甲と趾とはしばしばこういう表情を見せるのです。
擽ったい時の表情だから笑っているといったって少しも差し支えはないでしょう。
僕は今も、
しなを作っているといいましたが、
趾と甲とが互いに反対の方角へ思い切り反り返って、
その境目の関節に深い凹みを拵えている形、
──足全体が輪飾りの蝦の如く撓められている形、
それはたしかに見る人の眼に一種の媚びを呈するものだと、
僕は思います。
お富美さんのように踊りの素養があって、
体中の関節が自由にしなしなと伸び縮みするのでなければ、
とてもあんなになまめかしく足が反り返るものではありません。
そこには阿娜っぽい姿の女が、
身を飜して舞っているような嬌態があるのです。
それからもう一つ見逃す事の出来ないのは、
その円くふっくらとした踵でした。
大概の女の足は、
踝から踵に至る線の間に破綻がありますけれど、
お富美さんのはほとんど一点の非の打ちどころもないのでした。
僕は幾度か用もないのにお富美さんの後ろへ廻って、
前からは十分に翫賞する事の出来ないその踵の曲線を、
こっそりと、
しかし頭の中に焼き付けられるまでしみじみと貪り視ました。
下にどういう骨があって、
それにどういう風に肉が纒い附いたら、
こんな優しい、
円ッこい、
つやつやとした踵が結ばれるのでしょう。
お富美さんは生れてから十七になるまで、
この踵で畳と布団より外には堅い物を蹈んだ事がないのでしょう。
僕は一人の男子として生きているよりも、
こんな美しい踵となって、
お富美さんの足の裏に附く事が出来れば、
その方がどんなに幸福だかしれないとさえ思いました。
それでなければ、
お富美さんの踵に蹈まれる畳になりたいとも思いました。
僕の生命とお富美さんの踵と、
この世の中でどっちが貴いかといえば、
僕は言下に後者の方が貴いと答えます。
お富美さんの踵のためなら、
僕は喜んで死んでみせます。
お富美さんの左の足と右の足、
──こんなに似通った、
こんなにも器量の揃った姉と妹とがまたと二人あるでしょうか?
そうして二人は、
お互いに思い思いの姿をして、
その美を競い合っているではありませんか。
──僕はその美を高調するのに余り多くの文字を費しましたが、
最後に尚一と言附け加えさせて貰いたいのです。
それは今いった美しい姉妹、
彼女の二つの足を蔽うている肌の色です。
どんなに形が整っていても、
皮膚の色つやが悪かったらとてもこうまで美しいはずはありません。
思うにお富美さんは、
自分でも足の綺麗な事を誇りとしていて、
お湯へはいる時などに、
顔を大事にすると同じように足を大事にしているのでないでしょうか?
とにかくその肌の色は、
年中怠らず研きをかけているに違いない潤沢と光とを含んで、
象牙のように白くすべすべとしていました。
いや、実をいうと、
象牙にしたってこんな神秘な色を持ってはいないでしょう。
象牙の中に若い女の暖い血を通わせたらば、
あるいはいくらかこれに近い水々しさと神々しさとの打ち交った、
不思議な色が出るかもしれません。
その足は、白いといってもただ一面に白いのではなく、
踵の周りや爪先の方がぽうと薔薇色に滲んで、
薄紅い縁を取っているのです。
それを見ると、
僕は覆盆子に牛乳をかけた夏の喰物を想い出すのでした。
白い牛乳に覆盆子の汁が溶けかかった色、
──あの色が、
お富美さんの足の曲線に添うて流れているのでした。
画学生塚越老人に脚フェチを布教する
脚フェチな画学生は、かつては自分の女性の足に対するこの狂おしいほどの感情を病的なものだと思っていて恥ずかしく感じていました。
なるべく人に知られないようにつとめていましたが、最近になって開き直りました。
というのは近頃心理学の本で、世の中にはFoot-Fetichist といって自分と同類が無数にいることを知ったのです。
それ以来、きっと身近にも自分以外にも一人ぐらい仲間がいそうだと思って気を付けてみていました。
そして、今、富美子にこんなポーズを取らせようとして、必死な塚越老人こそ足フェチ仲間だと直感します。
もちろん江戸趣味の老人である塚越老人が新しい心理学の本を読むわけがありません。
きっとかつての画学生のように、塚越老人は、自分のこの特殊な性癖を忌まわしく思っているに違いません。
画学生は好奇心と仲間欲しさからか、老人の性癖を解放させるためにこんな風に声をかけます。
失礼ですが、この方の足の形は実に見事なものですなあ。
僕は毎日学校でモデル女を見馴れていますけれど、こんな立派な、こんな綺麗な足はまだ見たことはありません。
ねえ御隠居さん、僕はさっき反対をしましたけれど、御隠居さんがこの方にこういう姿勢を取れと仰っしゃったのは、たしかに一理ある事ですよ。
こういう姿勢を取ると、この方の足の美しさが遺憾なく現われますからね。
御隠居さんも満更絵の事が分らないとはいわれません。」
そういわれると最初は塚越老人はきまり悪そうな顔をしていました。
画学生は臆せず、積極的に、足の曲線が女の肉体美の中でいかに重要な要素であるか、を説きます。
美しい足を崇拝するのは誰にも普通な人情であるかを語ります。
すると塚越老人はだんだん安心してきてついにこんなことを言います。
いや、有り難うがす。
宇之さんがそういってくれると私は真に嬉しい。
なあにね、西洋の事ぁ知らないが、日本の女だって昔はみんな足の綺麗なのを自慢にしたものさ。
だから御覧なさい、旧幕時代の芸者なんて者あ、足を見せたさに寒中だって決して足袋を穿かなかった。
それがいなせでいいといってお客が喜んだもんなんだが、今の芸者は座敷へ出るのに足袋を穿いて来るんだから、全く昔とあべこべさね。
もっともこの頃の女は足が汚いから足袋を脱げったって脱ぐ訳にゃ行きますまいよ。
それで私は、このお富美の足が珍しく綺麗だから、どんな時でも決して足袋を穿かないようにッて、堅くいいつけてあるんだがね。
その心持ちが宇之さんに分ってくれりゃあ私は何もいう事ぁごわせん。
絵の出来栄えが悪くったってそんな事ぁ構やあしない。
だからね、もし面倒だったら余計なところは画かなくってもいいんだから、あの足のところだけ丁寧に写しておくんなさい。
普通の男性なら好きな女性の顔だけ画いてくれ、と言うところを塚越老人は足だけを画いてくれ、と言うのです。
これはもう塚越老人も脚フェチ人間に違いありません。
それから画学生は毎日のように塚越老人のもとに通いました。
学校にいても富美子の足の形が始終脳裏に浮かび、勉強がちっともはかどりません。
塚越老人の家に行っても絵の方は適当にごまかして、富美子の足をうっとりと眺めるほうが主目的です。
そして塚越老人と富美子の足への賛美の言葉を交わしあい時を過ごします。
富美子はさぞや気持ち悪かったでしょうが、利口者の富美子はおとなしく二人の脚フェチ男たちの玩具になってしらばくれているのでした。
ただ素足を見せて拝ましてやりさえすれば、それで相手は気が遠くなる程喜んでいるのですから、心の持ちようによってはこんな易しい役目はないのです。
画学生と塚越老人は過去のお互いの脚フェチ話を暴露しあって(画学生は老人に心を開かせるためにかなり誇張して話しました)すっかり意気投合します。
塚越老人によれば、彼は今迄なんどもこの縁台を座敷に持ち出して、そこに裸脚の富美子を座らせました。
そして塚越老人が犬の真似をして富美子の脚にじゃれついて遊んだのだとか……
塚越老人の最後
さてそれから三か月後のその年の三月の末に塚越老人は隠居の手続きをして、質屋の店を娘夫婦に譲り渡し、鎌倉の別荘に移りました。
名目は糖尿病と肺結核がだんだんと重くなってくるので転地療法のため、というものでしたが、本当は世間の人目を避けて富美子と誰はばからずふざけ散らして暮らしたかったからでしょう。
しかし別荘に移るとまもなく老人の病勢は重くなり、転地療法は本当の理由になってしまいました。
夕方になると三十八九度の熱が毎日続き、げっそりとやせ衰えてしまいました。
三度の食事の時以外は寝たきりです。
おりおり喀血をして、本人ももう覚悟しているようでした。
医者は
と言います。
塚越老人は病気が重くなるにつれて塚越は気難しくなりました。
とくに小間使いの作る料理の味が気に入らず叱りつけます。
こんな甘ったるいものが喰えると思うかい?
手前は俺を病人だと思って馬鹿にしていやぁがる……
とか塩が効きすぎるとかみりんが多すぎるとか、持ち前の「通」を振り回していろいろの難題を言います。
しかしもともと体調が悪くて舌の感覚が変わってしまったわけです。
どんな美味しいものを食べさせても塚越老人は気に入りません。
すると塚越老人はますます癇を昂らせて小間使いを叱り飛ばします。
そんな時は富美子がこんな風に塚越老人をたしなめます。
またそんな分らないことをいってるんだね……
喰物がまずいのはお定のせいじゃありゃあしない。
自分の口が変ってるんじゃないか。
病人の癖に勝手なことばかりいっているよ。
──お定や、構わないから打ッちゃっておおき。
そんなにまずいなら喰べないがいい。
すると塚越老人はまるでナメクジが塩をかけられたかのようにすうっと大人しくなります。
こんな時の富美子はまるで猛獣遣いが猛りだした虎やライオンを扱っているみたい。
はたで見ている者はハラハラしてしまいます。
そんな富美子はこのごろ五日に一度ぐらい病気の塚越老人を置き去りにして、どこかへ出かけてしまいます。
ちょいとあたし、買い物がてら東京まで行って来るわ。
と独り言のように言うと、塚越老人がいいとも悪いともいわないうちに、せっせとおめかしをしてぷいと出ていってしまいます。
そして半日も一日も帰ってきません。
富美子は恋人の俳優に会いに行っているのでした。
富美子が出かけてしまうと塚越老人は機嫌が悪くなり小間使いに当たり散らします。
しかし当たり散らしている最中でも富美子の帰ってくる下駄の音が近づいてくると塚越老人は急に小間使いをしかりつけるのを止めて、寝たふりをします。
瀕死の塚越老人のもとを画学生はたびたび訪れ、ときには二日三日泊まり続けることもありました。
画学生はもう便所へも自力で行かれない塚越老人の欲望を満たす手伝いをしたのです。
塚越老人は縁台を自分の枕もとに持ち出させて、そこに富美子を腰かけさせ、画学生に犬の真似をさせます。
そして塚越老人はその光景をじっと眺めているのでした。
画学生は塚越老人の身代わりではありましたが、富美子に顔を踏まれて、当人も至高の悦楽に浸っていました。
塚越老人は画学生は富美子の脚と戯れているのを見ているだけでは満足できなくなりました。
ある日富美子にこう頼みました。
お富美や、後生だからお前の足で、私の額の上をしばらくの間踏んでいておくれ。
そうしてくれれば私はもうこのまま死んでも恨みはい。……
痰の絡まった喉を鳴らしながら、塚越老人は、絶え絶えになった息を喘がせて、微かな声でこんなことをいうことがありました。
すると富美子は、美しい眉根をひそめて、芋虫でも踏んづけた時のような嫌そうな顔をします。
そして塚越老人の青ざめた額の笛に、足の裏を黙って乗せてやります。
まもなくついに塚越老人は危篤となりました。
しかし意識ははっきりしていて、時々思い出しては富美子の足のことを言い続けます。
食欲はもうまったくなくある方法をとった場合のみ食べ物を受け付けます。
それは牛乳やスープを綿の切れ端に浸して、富美子が足の指の股にそれを挟みます。
そして足を塚越口の端へ持って行ってやるのです。
塚越老人は富美子の足の指に挟まれた綿の切れ端を、貪るがごとくいつまでもいつまでも舐っています。
臨終の日はこんな風でした。
その日は富美子も画学生も朝から枕もとにつきっきりでした。
午後の三時ごろに、医者が来てカンフル注射をして帰った後でした。
ああ、もういけない。
……もうすぐ私は息を引き取る。
……お富美、お富美、私が死ぬまで足を載っけていておくれ。
私はお前の足に踏まれながら死ぬ。
富美子は黙って、無愛想な顔で塚越老人の顔の上へ足を載せました。
それから夕方の五時半に塚越老人が亡くなるまで、二時間半の間、ずっと塚越老人の顔に足を載せていたのでした。
立っていてはくたびれてしまうので、枕もとに縁台を置いて、腰を掛けたまま、右の足と左の足を交互に乗せていました。
塚越老人はその間にたった一遍、
とかすかな声で言いました。
富美子が塚越老人の希望通りにしてくれたおかげで、塚越老人は無限の歓喜のうちに息を引き取ることが出来たのでした。
死んでいく塚越老人には、顔の上にある富美子の足が、自分の霊魂を迎えるために空から天降った紫の雲とも見えたでしょう。
その後富美子は塚越老人の遺産を手にして恋人の俳優と結婚しました。
感想
女性美の描写が命の作品。
ストーリーじたいはシンプルです。
また富美子の行動や表情がなかなかリアリティがあって面白いですね。
財産めあてで、もともと好きでもない四十歳も年上の男性の愛人となった富美子の言動は、なるほどこういう状況ならこうなるよな……というものばかりです。
PR
本の要約サービス SUMMARY ONLINE(サマリーオンライン)月額330円で時短読書 小説の要約も多数あり!!谷崎潤一郎 まとめ記事
 谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
 宇美の文学
宇美の文学