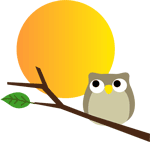はじめに
谷崎潤一郎『鍵』は昭和31年(1956年)に発表された長編。舞台は昭和二十年代後半、三十年代初頭の京都。
(ひたすら男女間のことを書いているので、あまり舞台は重要ではないのですが)
夫は四十代半ばにして、二十代の娘よりも美しく色香のある妻にぞっこんですが、一方妻の夫に対する愛情は微妙。
中年夫婦の性生活と、妻の不倫を日記形式で描いています。
夫と妻がそれぞれ日記を書いています。
物語は夫婦それぞれの日記形式で進みます。
お互い相手に日記を読まれている、という前提で書いているため、日記に書かれていることは果たして真実かどうか……
最後に妻の真実は明らかにされますが、夫の方の真実はわからぬまま……
ミステリ要素もある小説です。
谷崎潤一郎『鍵』 あらすじ
お互いへの性的不満
一月一日(夫の日記)
夫は大学教授五十六歳、妻郁子は四十五歳です。夫はセックスが弱いのですが、一方妻はもともと病弱で心臓も弱いのに、セックスは病的に強いのです。
妻は夫に不足しているわけですが、夫はもしそのために妻が別の男を作るのは絶えられないと考えていました。
夫は妻を愛しているのです。
夫は夫婦の行為は週一回ぐらいでちょうどよく、それも終わった後はぐったり疲れてしまいます。
しかし、いやいやだったり、妻のために義務としてやっているわけでは決してありません。
むしろその方面には興味津々で、ただ体力がついていかないというわけです。
また夫は妻は多くの女性の中でも極めて稀にしかいない「名器」の持ち主だと思っています。
彼女がもし昔の遊女だったら、必ず世間の評判になり、無数の男が競って彼女の客となり、天下の男子はことごとく彼女に悩殺されていたかもしれない、と考えています。
しかし、妻は夫以外の男性との経験はありませんし、夫が妻にそんなことを言ったこともないので、妻は自分が「名器」の持ち主だということは知りません。
また妻は精力絶倫ではあるわけですが、かといって夫婦の行為はあくまでもオーソドックスなものを好み、それ以外を夫に許しません。
彼女は京都の旧家に育ったたしなみぶかい女性で、変わったことをして快楽をもとめる、ということは嫌いなのでした。
例えば妻は美しい足の持ち主なので、夫はそれを愛撫したいのですが、妻は夏の暑い盛りでもいつも足袋を履いていて、見せてすらくれません。
一月四日(妻の日記)
妻も夫に負けじと日記を書きます。一月四日、妻は夫の書斎で鍵が落ちているのを発見します。
妻は夫が長年日記をつけていて、それが入っている引き出し、引き出しの鍵をいろいろな場所に隠していることを知ってい
したが、落ちている鍵を見るのは初めてでした。
しかし妻は夫が隠しているものを読むのはよくないと思っています。
日記帳の中を開けて見たりなんかしたことはありません。
妻は夫が鍵を落としていくなんて、夫が自分に日記を読んでほしいと思っているのだろうか?と思います。こんな複雑なことを考えます。
その夫が今日その鍵をあんな所に落して行ったのはなぜであろうか。しかし妻はどのみち日記を読む気はありません。
何か心境の変化が起って、私に日記を読ませる必要を生じたのであろうか。
そして、正面から私に読めと云っても読もうとしないであろうことを察して、「読みたければ内証で読め、ここに鍵がある」と云っているのではなかろうか。
そうだとすれば、夫は私がとうの昔から鍵の所在を知っていたことを、知らずにいたということになるのだろうか?
いや、そうではなく、「お前が内証で読むことを僕も今日から内証で認める、認めて認めないふりをしていてやる」というのだろうか?………
妻はは自分でここまで、と決めている限界を越えて、夫の心理の中にまではいり込んで行きたくないのです。
私は自分の心の中を人に知らせることを好まないように、人の心の奥底を根掘り葉掘りすることを好まない。といいます。
ましてあの日記帳を私に読ませたがっているとすれば、その内容には虚偽があるかも知れないし、どうせ私に愉快なことばかり書いてあるはずはないのだから。
夫は何とでも好きなことを書いたり思ったりするがよいし、私は私でそうするであろう。
妻も今年から日記をつけ始めました。
私のように心を他人に語らない者は、せめて自分自身に向って語って聞かせる必要がある。のだとか……
ただし私は自分が日記をつけていることを夫に感づかれるようなヘマはやらない。
私はこの日記を、夫の留守の時を窺うかがって書き、絶対に夫が思いつかない或る場所に隠しておくことにする。
私がこれを書く気になった第一の理由は、私には夫の日記帳の所在が分っているのに、夫は私が日記をつけていることさえも知らずにいる、その優越感がこの上もなく楽しいからである。………
その後妻の夫への性の不満がかかれています。
内容は夫とそっくりです。
つまり彼女はセックスが強く、夫がすぐ疲れてしまうのを物足りなく思っています。
また彼女は夫が新奇な方法を好むのに、彼女はあくまでもオーソドックスな方法でしかやりたくないと思っています。
お互い日記を読んでいない割には考えていることが同じすぎて、ある意味気の合う夫婦のような気がしてしまいます。
夫が妻を熱愛しているのに対して、妻は夫をそれほど愛していないようです。
私と彼とは、性的嗜好が反撥はんぱつし合っている点が、あまりにも多い。と書いています。
私は父母の命ずるままに漫然とこの家に嫁とつぎ、夫婦とはこういうものと思って過して来たけれども、今から考えると、私は自分に最も性の合わない人を選んだらしい。
これが定められた夫であると思うから仕方なく怺こらえているものの、私は時々彼に面と向ってみて、何という理由もなしに胸がムカムカして来ることがある。
そしてこのムカムカは今に始まったことではなくて、新婚旅行の時から始まっているというのです。
妻は結婚の第一夜、新婚旅行の晩、初めて眼鏡を外した夫の顔を間近で見て、ゾウッと身震いがしたというのです。
そしてそれ以来今でも夫の顔を明るいところで長い時間眺めているとゾウッとした気分になるそうです。
なるべく夫の顔を見なくてよいように夫婦の行為のとき、明かりを消そうとします。
しかし夫は明るくしたがり、また妻の体をじろじろ見ます。
特に夫は妻の足を見るのが大好きなのですが、妻はああしつこい、あくどい、べたべた、嫌だなあ、と思っています。
木村
一月七日 (夫の日記)
この小説の主要登場人物は四人です。夫、妻(郁子)、娘(敏子)、木村。
敏子は結婚適齢期の娘で、木村は敏子のお婿さん候補です。
木村は夫、妻、敏子の家によくやってきて、妻とも親しく交際しています。
その日は木村がやってきて、妻と敏子と三人で映画を見に行った後、また三人で夜の六時ごろに戻ってきました。
そして木村を交えて家族で食事を始めます。
食事のとき敏子以外はブランデーを少量ずつ飲みました。
その晩は木村がシェリーグラスに二杯半まで妻にお酌をしました。
妻が夫以外の男性からブランデーの杯を受けたのはその夜が始めてです。
夫は妻と木村の関係を疑っています。
木村は結婚相手の候補の敏子よりもむしろ郁子に親愛の情を示す傾向があるのでした。
そして郁子も通常は来客に対して無愛想で、とくに男の客には会いたがらないのに、木村だけには愛想がいいのです。
また妻はジェームス・スチュアートという映画俳優のファンなのですが、木村はジェームス・スチュアート似なのです。
もっとも木村は夫が娘の結婚相手にどうかと思って家につれてきて、妻に二人の様子を見ておいてくれといったのがきっかけで木村と郁子の交際がはじまったわけですが……
また敏子も木村と二人きりになるのを避ける様子なのです。
夫は
と疑っています。
一月十三日(夫の日記)
夕方四時半ごろに木村が来ます。国からカラスミが届きましたから、とお土産をもってきたのでした。
一時間ぐらい話した後帰ろうとするのを夫が引きとめて、夕飯を食べていくように薦めます。
おつまみになるカラスミ、昨日買ってきた鮒鮨があったので、すぐにブランデーになりました。
夫は
夫はもし自分が木村だったら、妻のほうに惹かれるだろう。
妻は年はとっているけれど娘より美人で、色香もある。
しかし木村がどう考えているかなんてわからない。
もしかして木村は敏子を愛していて、敏子が自分との結婚にあまり乗り気でなさそうなので、まず郁子と親しくなって、郁子を通して敏子を動かそうとしている?
夫は去年から木村に嫉妬を感じていました。
しかし夫自ら、木村が郁子とより親しくなるような言動をしてしまいます。
たとえば今日木村に夕飯を食べていくように誘ったのは夫でした。
そしてその理由は自分でもよくわかっていました。
木村が来た日の夜はいつもよりセックスに強くなり久しぶりに妻を満足させられるのです。
木村への嫉妬は満足いく性生活のための刺激剤となるのでした。
夫は木村と妻の関係を
などと考えています。
一月十七日(夫の日記)
酔いを隠して青ざめた顔をしている妻は色っぽくて僕は好き!
妻を酔いつぶして、その美しい足を触りたいがなかなか触らせてくれない。
一月二十日(妻の日記)
夫や木村さんの前で取り乱したことはないが、そろそろ限界だ、用心しなければ……
妻が酒盛りの後昏睡する 妻の昏睡後、夫の楽しみ
一月二十八日(夫の日記)
今夜妻が突然人事不省となりました。また木村がきて夕食後ブランデーの酒盛りとなります。
敏子はブランデーが始まると部屋に引き取ってしまいました。
妻も酔いが過ぎると、時々中座して便所に隠れてしまいます。
妻は今日は一度姿を消した妻が、なかなか戻ってきませんでした。
おかしいと思った木村が敏子を呼んで、二人で妻を探す。
その間夫は食卓で待っていました。
まもなく木村と敏子は、妻を風呂で発見しました。
妻は浴槽のふちに手をかけ、その上に顔をうつぶせにして眠っていたといいます。
敏子が声をかけても返事をしません。
この時点で夫が木村に呼ばれ、風呂場にやってきました。
夫が妻の脈を取ると、脈拍が微弱でした。
一分間に九十以上百近くも打っています。
夫と娘で協力して裸の妻を浴室から出します。
その後木村と夫が協力して裸体の妻の体をふき取りました。
木村は妻の上半身を拭き、夫は妻の下半身を拭きました。
夫が木村に、妻の裸体をぬぐわせたのは、自分の嫉妬心に火をつけるためです。
医者を呼んだところとくに命に別状はないようでした。
一月二十九日(夫の日記)
妻は昨晩の事件いらいこんこんと眠り続けています。医者と木村が帰った後、夫は熟睡している妻のベッドに近づきました。
電気スタンドのシェードの上に被せてあった黒い布覆いを取り除いて室内を明るくします。
そして電気スタンドをベッドに近づけていて、彼女の全身を照らしました。
夫の心臓は激しく脈打ちます。
以前から夢見ていたことが今夜こそ実行できると興奮します。
夫は二階の書斎のデスクから蛍光灯ランプをもってきてベッドの近くに置きます。
夫は妻の着ているものを剥ぎ取ると、フロアスタンドと蛍光灯ランプで妻の裸体をくまなく照らしました。
そして彼女の裸体を地図を調べるように詳細に調べ始めました。
夫はその一点の汚れもない美しい裸体に驚嘆します。
夫は結婚してから二十数年、今日まで妻の裸体をこうもはっきりと見たことがなかったのでした。
妻は夫婦の行為を暗いところでするのを好み、自分の裸体をほんの一部しか見せてくれなかったのです。
夫は裸体の妻を仰向けにしたりひっくり返したりして観察します。
また今までやってみたかったけど妻が許してできなかったこと、たとえば足を舌で愛撫する、などをします。
そうこうしているうちに夫は妻の腹の上に眼鏡を落としてしまいます。
妻は一瞬目を覚ましたかのようでした。
夫は彼女に睡眠薬を飲ませると、また妻は眠ります。
そして夫は半醒半睡の妻と夫婦の行為に及びます。
十分情欲をかきたてた後だったためか、十分に妻を満足させることができました。
しかし妻は行為の最中「木村さん」とうわごとを言ったのです。
夫はこんなことを考えます。
それとも寝ているふりをしていて実はおきていて、夫に「あなたが私にこんな悪戯をするなら私は行為の最中に別の男の名前を言ってやりますよ」といいたいのだろうか……
一月三十日(妻の日記)
おとといの夜のことを思い出している。
私はあの晩ブランデーで悪酔いをして、便所に長い間閉じこもっていたが、その間に体中が便所くさくなった気がして、便所を出て、風呂に入ったのだった。
そしてその後記憶がおぼろげだ。
気がつくとベッドの中にいて、早い朝の日光が寝室を薄明るくしていた。
それ以後ずっと意識がハッキリしつづけていたわけではない。しかし妻はこうも言っています。
私は頭が割れるように痛み、全身がズシンと深く沈下して行くのを感じつつ幾度も眼が覚めたり睡ったりすることを繰り返していた、―――いや、完全に覚め切ることも睡り切ることもなく、その中間の状態を昨日一日繰り返していた。
頭はガンガン痛かったけれども、その痛さを忘れさせる奇怪な世界を出たりはいったりしつづけていた。
あれはたしかに夢に違いないけれども、あんなに鮮かな、事実らしい夢というものがあるだろうか。
私は最初、突然自分が肉体的な鋭い痛苦と悦楽との頂天に達していることに心づき、夫にしては珍しく力強い充実感を感じさせると不思議に思っていたのだったが、間もなく私の上にいるのは夫ではなくて木村さんであることが分った。
それでは私を介抱するために木村さんはここに泊っていたのだろうか。
夫はどこへ行ったのだろうか。
私はこんな道ならぬことをしてよいのだろうか。
………しかし、私にそんなことを考える餘裕を許さないほどその快感は素晴らしいものだった。
夫は今までにただの一度もこれほどの快感を与えてくれたことはなかった。
夫婦生活を始めてから二十何年間、夫は何とつまらない、およそこれとは似ても似つかない、生ぬるい、煮えきらない、後味の悪いものを私に味あわせていたことだろう。
今にして思えばあんなものは真の性交ではなかったのだ。
これがほんとのものだったのだ。
木村さんが私にこれを教えてくれたのだ。
………私はそう思う一方、それがほんとうは一部分夢であることも分っていた。妻は一昨日の晩夫にされたことをほぼ正確に感づいていました。
私を抱擁している男は木村さんのように見えるけれども、それは夢の中でそう感じているので、実はこの男は夫なのだということ、―――夫に抱かれながら、それを木村さんと感じているのだということ、
夫が妻の意識がないのをいいことにいろいろ体をもてあそんだことも、また蛍光灯のことも……妻は夫のことはほぼお見通しなのです。
しかし妻はたとえそれが夢であったとしても木村さんとのセックスに非常に満足しているのです。
それはとても夢とは思えない、生々しいものでした。
そして妻はこう考えます。
それにしても夢で見た木村さんのたくましく美しい裸体は本当はどんなふうなのだろうか?
夢で見たのはただの私の幻想なのだろうか?
それとも本当に木村さんはあんなふうなのかしら??
一度木村さんのハダカを見てみたいわ!
一月三十日(夫の日記)
木村が夕飯にやってきて、酒盛りが始まる。
今日は木村は当初は「お見舞い」という名目でやってきたのだが、夫が「飲みなおそうよ」と言うと妻がニヤニヤして、木村もなかなか腰を上げない。
そしてついにまたブランデーの酒盛りが始まってしまった。
酒盛りが始まると敏子は自分の部屋に引きこもる。
まもなく妻が見えなくなり風呂で倒れている。
そしてその後の夫の行動も一昨日とまったく同じ。
夫婦の行為の最中妻はまた「木村さん」と口走る。
二月九日(妻の日記)
このところほとんど三日置きぐらいに木村さんが来てブランデーが始まり、クルボアジエはすでに二本目が空からになり、そのたびごとに私が風呂場で倒れる(中略)寝室で時々煌々こうこうと電燈が点ともったり、螢光燈ランプが輝いたりする娘の敏子が別居させてくれと母親に言いました。
下宿先は彼女の大学の先生のフランス人の老婦人の家です。
その人の家に空き部屋があるのでそこに住まわせてもらうことにしたといいます。
別居の理由は敏子がいうには「静かに勉強したいから」というものでしたが、妻はこう考えます。
妻の裸体を撮影する
二月十四日(夫の日記)
夫は木村からポラロイド写真機のことについて聞きます。ポラロイド写真機は昭和31年の当時には最先端でした。
夫は「写したものが即座に現像されて出てくる、携帯に便利、長い露出時間がいらないから、三脚を使わないで写せる」などの機能に惹かれます。
当時はアメリカから輸入しなければ入手できないものでしたが、木村の友達が持っているそうです。
木村が「もしお使いになりたいなら借りてきますよ」というのです。
夫はそれを欲しいと思いました。
(妻の裸体を撮影するためですね)
しかしこうも思います。
木村は自分たち夫婦の秘密を知っているのか……
二月十六日(妻の日記)
私は急いで日記を隠したが、日記を隠すときの、紙のぴらぴらという音が夫に聞こえたのではないかと思う。
今後用心しなければならない。
でも狭い家で日記のありかを隠し通せるとは思わない。
今後夫の在宅中は留守にしないようにしようか?
でも木村さんに映画に誘われているからそれは行きたい……
それまでによい方法を考えなければ……
二月十八日(夫の日記)
あれはもううわごとではなくて、うわごとを装っているのだろう。
なんの目的であんなことを言うのだろう?
「私は本当は眠っていない、眠ったふりをしているだけですよ」と僕にわからせるためか?
それとも「私はセックスの相手があなたなのが嫌なのですよ。木村さんだと思いたいのですよ」と言いたいのか?
今日敏子が家を出て、下宿先に移った。
今朝引っ越しの時は妻はまだ昏睡していた。
引っ越しには木村が手伝いに来た。
木村は帰り際にポラロイドカメラを置いていった。
二月十九日(妻の日記)
………敏子の心理状態が私には掴めない。日記が夫に見られたかどうかを確認するために、妻はある方法をとることにしました。
彼女は母を愛しているようでもあり憎んでいるようでもある。
だが少くとも、彼女が父を憎んでいることは間違いない。
彼女は父母の閨房関係を誤解し、生来淫蕩な体質の持主であるのは父であって、母ではないと思っているらしい。
母は生れつき繊弱なたちで過度の房事には堪えられないのに、父が無理やりに云うことを聴かせ、常軌を逸した、よほど不思議な、アクドイ遊戯に耽けるので、心にもなく母はそれに引きずられているのだと思っているらしい。
(ほんとうを云うと、私が彼女にそう思わせるように仕向けたのである)
昨日彼女は最後の荷物を取りに来て寝室へ挨拶に見えた時に、「ママはパパに殺されるわよ」とたった一言警告を発して行った。
(中略)彼女は私の胸部疾患が、こんなことから悪化して本物になりはしないかを、ひそかに心配しているらしくもあるのだが、そうしてそれゆえに父を憎んでいるらしいのだが、でもその警告の云い方が妙に私には意地の悪い、毒と嘲あざけりを含んだ語のように聞えた。
(中略)彼女の心の奥底には、自分の方が母より二十年も若いにかかわらず、容貌姿態の点において自分が母に劣っているというコンプレックスがあるのではないか。
彼女は最初から木村さんは嫌いだと云っていたが、母―――ジェームス・スチュアート―――木村さん―――という風に気を廻して、ことさら彼を嫌っているらしく装っているので、本心は反対なのではないか。
そして内々私に敵意を抱いだきつつあるのではないか。
それは日記をセロハンテープで封じて、テープを貼った場所、テープの幅などを測って記憶しておくのです。
薄い紙なのでテープをはがせば必ずけば立ちますし、貼りなおせば位置や幅がずれるので貼りなおしたことが分かるでしょう。
二月二十四日(夫の日記)
敏子が家を出たというのに、木村は相変わらず二三日置きに家にやってきます。夫からも木村に電話をかけました。
ポラロイドはすでに二晩使用しています。
つまりブランデーで昏睡した妻の裸体を撮影しているわけです。
写真は妻の全裸体の正面と背面、各部分の詳細図、いろいろな形状に四肢を曲げて、折ったり伸ばしたりして最も蠱惑的な角度から撮りました。
妻はこの日記を盗み読みしているに違いないのだから、この写真を見たらどんな反応をするか楽しみだ。
彼女は自分の肉体の美しさに驚くだろう。
また自分がいかに彼女の裸体を見たがっているかを知り感激するだろう。
(四十五歳の妻の裸体を夫が見たがっているというのは稀有なことだ)
また妻が自分のこんな恥ずかしい写真を見ていつまですましていられるか、それも試したい。
といってもポラロイドカメラは映りが悪くぼんやりしているので、不満だからまだ日記に添付はしていない。
二月二十七日(妻の日記)
今日は日曜日でした。妻は木村と敏子と一緒に、朝から映画を見に行きました。
敏子は
自分は一緒に行きたくはないのだが、二人では工合が悪いだろうから、ママのために犠牲になって附き合って上げるというような顔をしています。
僅かに傷がついている。
夫が読んだようだ。
私は自分の胸の内を人に語るのは好きではないから、自分自身に語るために日記を書き始めた。
今人に読まれてしまった以上日記を書くのをやめるべきかもしれないが、やはり続けるつもりだ。
というのは読まれた人、というのが他ならぬ私の夫であるし、今後は日記を書く際、夫に言いたいけど言えないことを書こうと思う。
しかし夫にはもう日記を読まれるのは構わないけど、彼に日記を読んだことは黙っていてほしい。
それから夫には、私が夫の日記を読んでいないことを信じてほしい。
私は旧式な、人の日記など盗み読むことのできないような育ち方をしている。
私は夫の日記帳のありかを知っているし、それに手を触れたり、中を開けたことはあるが、文字は一字も読んだことがないのである。
これは本当のことだ。
二月二十七日(夫の日記)
便所に行くため一階に降りると、雁皮紙をくしゃくしゃさせる音がした。
そして彼女は最近僕の在宅中に外出しない。
そこで疑わしいと思った僕は木村に頼んで、妻を連れだしてもらったのだ。
妻の留守中に茶の間を探すと日記が見つかった。
彼女はもう僕が日記のことを嗅ぎつけたのを知っているようで、セロハンテープで閉じてあった。
セロハンテープを剥がして、日記帳を開いてみたが文字は一字も読んでいない。
僕は妻が日記に木村のことをどう思っているか書いてあると思うとそれを読むのが怖いのだ。
郁子よ、どうか木村への思いを日記に書かないでくれ。
嘘でも木村はあくまでも僕と妻の関係の刺激剤であってそれ以上の何者でもないとしておいてくれ……。
今日、敏子の別居以来、初めて四人(夫、妻、敏子、木村)で夕食の卓を囲んだ。
敏子は先に帰り、妻は酒盛りが始まるといつものようにお風呂で失神。
夜遅く木村が帰るときに僕は木村にポラロイドを返した。
夫「やはり普通のカメラ機の方が撮りよいね。これからは家にあるやつで写すよ」
木村「現像は外にお出しになるのですか?」
夫「君の家で現像してくれないだろうか?」
木村、ちょっと困った顔をして「お宅で現像なさったらいかがでしょう?」
夫「人に見られては困る写真だが、僕の家では現像できない。というのは引き伸ばしてもらいたいのだが、家には暗室を作るのに適当な場所がないんだ。君の家でやってくれなだろうか? 君にだけは見られてもしかたない」
木村「考えておきます」
翌朝、妻がまだ昏睡中木村が家にやってきました。
写真の現像ができるようになったことを伝えにきたのです。
三月三日(夫の日記)
渡すぎりぎりまで本当にこの写真の現像を彼に依頼するか悩んだ。
こんなことをしたら木村を刺激して妻と木村の関係が進んだりしないだろうか?
もしそうなったらその責任を負うのはこんなことをして木村を挑発した僕となる。
また妻がこのことを知ったら妻がどう考えるだろう?
僕がこんなことをしたということは、自分が木村と不義をすることを僕が許したと思わないだろうか?
しかし僕はそこまで想像するといよいよたまらない嫉妬を感じる。
そしてその嫉妬の快感ゆえに、その危険を冒してみたくなるのだった。
三月七日(妻の日記)
今年の正月四日落ちていたのと同じ場所である。
これは訳があると思って引き出しから夫の日記帳を取り出してみたら、私がしたのと同じようにテープで封がしてあった。
これは「夫がぜひ開けてみろ」と言っているのだろう。
私はこのテープをうまく痕跡をつけないではがしてみたい、という好奇心だけで剥がし日記帳を開けてみた。
相変わらず一字も読んでいないが、中に何か女の裸体を撮影したような猥雑な写真が貼ってあるのに気が付いた。
急いで日記帳を閉じたが、あれはなんだったのだろうか?
実は最近私は夜中、睡眠中、夢の中で誰かがフラッシュを用いて私を撮影しつつあるような幻影を見ていた。
また私はときどき昏睡中に自分が裸体にされることをボンヤリ感じている。
あれは夫が私を撮影していたのだろうか?
また夫は以前「お前はお前自身の体がどんなに立派で美しいか、ということを知らずにいる。一度写真に撮って見せてやりたいね」と言っていた。
きっと私が昏睡中、夫は私を裸にして撮影しているのだ。
日記帳に挟んだ写真はきっと私の裸体だ。
しかし私は夫を許そうと思う。
私は夫に忠実な妻の勤めとして、知らないうちにハダカにされることぐらいは忍耐しなければならないと思う。
それに夫はそういうことをしてやっと、私が満足できるようなセックスができるのだ。
わたしは夫の趣味に従うことによって、旺盛な淫欲を充たさせてもらっているわけだ。
それにしても夫はだれに写真を現像してもらったのだろう……
夫の体調がおかしくなる
三月十五日(夫の日記)
僕は中年以降精力減退していたのを、今年になってから木村とブランデーのおかげで妻が満足できるような夫婦の行為ができるようになった。
その上僕は精力の補給をするために、医者に頼んで、月に一回男性ホルモンのデポを用いていた。
それでもさらに不足な気がして、脳下垂体前葉ホルモンを三日か、四日自分で注射している(これは医者に内緒)
そういったもののおかげか、僕は毎晩これまで想像もしたことのないような法悦境に浸っている。
しかし僕はうすうすもこんな幸福はいつまでも続かないと、僕はこの満足のために命を削っているのだ、という予感がしている。
そしてその予感の前触れではないかと思われる現象がすでに発生しつつある。
この間の朝、僕は木村が来たので、ベッドから起き上がって茶の間に行こうとしたとき、奇怪なことが起きた。
起きたとたん、ストーブの煙突、障子、襖、欄干、柱等そのあたりにあるすべてのものがかすかに二重になって見えた。
生活に支障がないからそのままにしているけど、そのなんでも二重に見えるのが今でも続いている。
また時々体が急にフラフラして平行を失い、右か左に倒れそうになる。
また昨日の午後木村に電話をかけようとしたら、毎日のようにかけている彼の学校の電話番号がどうしても思い出せない。
それも一部わからないとかではなく、局番も局名もすべて思い出せないのである。
僕は驚き慌て、今度は木村の勤務する学校名を思い出そうとしたがそれもダメだった。
さらに木村の名前も思い出せない。家で使っている婆やの名前も思い出せない。
妻の亡くなった父や母、敏子が部屋を借りている家の名前、はなはだしきはこの家の所在地の町名が思い出せない。
そんな状態が30分ほどつづいた。
またそんな状態が起きて、今度は30分ではなく、永遠に続いたらどうしよう。
もし妻がこの日記を読んだら僕の体を心配して、夫婦の行為をそれほど求めなくなるだろうか?
いや恐らくそんなことはあるまい。
彼女の理性は制御を命じたとしても、彼女の飽くなき肉体は理性の言には耳を貸さず、僕を破滅に追い込むまでも満足を求めて已まないであろう。
いやそれ以上に僕自身が自分を制御できなくなっている。
三月十四日(妻の日記)
………午前中、夫の留守に敏子が来て「ママに話がある」と云った。何か真剣な顔をしている。何の話かと聞くと、「昨日木村さんの所で写真を見たわよ」と、私の眼の中をじっと視つめた敏子は昨日木村にフランス語の本を借りる約束をしていたというのです。
しかし木村の家に到着すると木村は留守だったので、本棚から約束の本をとって開いてみると、中に母、郁子の裸体写真が挟まっていたのでした。
敏子は木村と母に不義の関係があるのではないか? と疑っているようです。
ママ、あれは一体どういう意味と尋ねる敏子に郁子はこう答えます。
私は実は、世の中に私のそういう恥ずべき姿を撮った写真があるということを、今あなたから聞かされるまでは確かには知らなかったのだ。「どうしてパパがママの写真を木村さんに現像させたのか理解できない」という敏子に、郁子は「パパはママを熱愛していて、きっとママの年のわりに若く美しい肉体を他の男性に自慢したいのよ」と夫をかばいます。
もしそういうものがあるとすれば、それは私が昏睡している間にパパが撮影したもので、木村さんはただその現像をパパから依頼されたに過ぎない。
木村さんと私との間には断じてそれ以上の関係はない。
パパがなぜ私を昏睡させ、なぜそんな写真を撮り、なぜその現像を自分でしないで木村さんにやらせたか、等の理由は想像に任せる。
現在の娘の前で、これだけのことを口にするさえ私には忍びがたい。もうこれ以上は聞かないでほしい。
ただ、すべてはパパの命令に従ってしたことであり、私はどこまでもパパに忠実に仕えることを妻の任務と心得ているので、いやいやながら云われる通りにしたのであることを信じてほしい。
あなたには理解しがたいことかも知れないが、舊式(旧式)道徳で育って来たママは、こうするよりほかはないのである。
ママの裸体写真がそんなにパパを喜ばすのなら、ママはあえて恥を忍んでカメラの前に立つであろう(後略)
郁子はどうして木村さんが、敏子に渡すことになっている本に写真を挟んでおいたのだろうか? と思います。
何か木村さんに思惑があるのでしょうか?
妻、娘の下宿先で木村と酒盛り後昏睡
三月十八日(夫の日記)
夜の十一時過ぎになっても戻らない。
十一時半に敏子から電話で、「パパちょっと来てよ」という電話があった。
敏子に聞くと、敏子の下宿先の家に妻と木村がいて、妻がそこの風呂で倒れたという。
敏子が門の前に立っていて「では私は家の留守番に行きます」と父親と入れ違いに出ていきます。
敏子の部屋に入ると、妻は長じゅばん姿で寝ていました。
いつものとおりの妻でしたが、一つ変わったこととは髪が乱れていたことです。
夫はこんなことを考えます。
木村はこの家の勝手をよく知っているようでした。
妻の脈拍が正常に近づいてきたので、家に連れて帰ることにしました。
夫が妻を抱き起して、木村が長じゅばん姿の郁子(妻)を背負って、タクシーに乗せます。
タクシーで家に帰る途中、夫は妻の髪の中に顔をうずめ、足を握りしめ接吻しました。
家に到着後、木村は帰りました。
敏子は両親が家についたときは玄関にいたのですが、いつの間にか挨拶もせずに下宿に帰ってしまったのでしょうか?
姿が見えません。
その後暁まで一睡もせず夫は夫婦の行為に耽ります。
嫉妬と憤怒が性欲を刺激して、今までにない境地に達したのでした。
妻は「木村さん」といううわごとを繰り返します。
三月十九日(妻の日記)
木村さんが4時半ごろ家に誘いに来た。
しかし敏子が来たのが遅くて5時頃だった。
敏子は「時間が半端だから食事を済ましてからの方がよくはなくって。今日は私が作るから下宿に来てよ」と言った。
その時、敏子が「ここのを寄付してもらうわ」と言って、実家にあったブランデーを下宿先に持っていったのでした。
敏子の部屋についた後、なべ料理になります。
敏子が具材を鍋に少しずつ入れるので、なかなかご飯にならず、ブランデーが進みます。
敏子が「もう今から映画を見に行くのは遅いわね」と言い出します。
そのころ妻はすっか酔っていて、とても映画を見る気分ではありませんでした。
いつの間にか急激に酔いが回ってきたので妻は、いつも家でそうしているように、便所に隠れます。
便所の外から敏子がこう母に声をかけます。
「ママ、今日はお風呂が沸いているのよ、マダムは上りはったからママはいらはったらどう」と、便所の外から敏子が云った。
私は、風呂へはいれば倒れるであろうこと、その場合に抱き起しに来てくれる者は、恐らくは敏子でなくて木村さんであろうことを、すでに朦朧となっていた意識の隅で感じていた。
そして間もなく、ひとりで風呂場を捜しあててガラス戸を開け、着物を脱いたことまでは思い出せるが、それからあとは完全に意識を失ってしまった。………
三月二十四日(夫の日記)
夜12時過ぎに敏子が家に現れ、事情を語ったが、それまで、連絡がくるのを待っているときには期待で胸をワクワクさせていた。
今回は映画の後で木村と郁子と下宿に行って、そこで酒盛りとなったという。
そして昨晩もまた郁子は風呂に入ってそこで倒れた。
僕はこの件は敏子が首謀者であると思っている。
そして、敏子は故意に長い時間木村と郁子を下宿に二人きりにしていのだと考えている。
この前と同じように、妻を家に連れて帰り、夫婦の行為をした。
妻は「木村さん、木村さん」と呼び続ける。
その夜は素晴らしいものだった。
僕は木村に激しく嫉妬しながらも感謝した。
しかし行為の後でものすごいめまいを感じた。
妻の体が二重に見えた。
その後眠ったが奇妙な夢を見た。
空中に妻の体、眼、鼻、唇、頭髪、足、などがばらばらになって極彩色で浮かんでいるのである。
それも目が4つ、鼻が2つ、唇が2つ、など実際の倍の数、各部分が浮かんている。
他にも木村の体から僕の首が生えていた幻影を見た。
木村の体から、木村の首と僕の首の両方が生えている場面も見た。
三月二十六日(妻の日記)
木村さんや郁子に聞いても知らないという。
どうやら夫がこっそり置いていったのか、それとも木村さんや郁子が自分が買ってきたのに知らんぷりをしているのか。
昨晩もブランデーが始まると敏子はほどよい所で席を外す。
(実はこれはこの前もそうである)
私と木村さんは二人きりでさしつさされつしていた。
私は意識を失ってから後のことはよく分らない。
しかしどんなに酔っていたとしても、最後の最後の一線だけは昨夜も強固に守り通したと思っている。
自分にはいまだにそれを蹈み越える勇気はないし、木村さんだって同様であると信じる。
木村さんはそう云った、
―――ポーラロイドという写真器を、先生に貸して上げたのは僕です。
それは先生が、奥さんを酔わして裸になさりたがる癖があることを知ったからです。
しかるに先生はポーラロイドでは満足できないで、イコンを使って写すようになりました。
それは奥さんの肉体を細部に亙って見極めたいという目的からでもあったでしょうが、それよりも、真の狙いは僕を苦しめることにあったのだと思います。
僕に現像の役を負わせて、僕をできるだけ興奮させ、誘惑に堪えられるだけ堪えさせて、そこに快感を見出しているのだと思います。
のみならず僕のこの気持が奥さんに反映し、奥さんも僕と同様に苦しむことを知って、そこにも愉悦を感じつつあるのです。
僕は奥さんや僕をこんなにまで苦しめる先生を、憎いとは思いますけれども、それでも先生を裏切る気にはなりません。
僕は奥さんの苦しむのを見て、自分も奥さんとともに苦しみ、もっともっとこの苦しみを深めて行きたいのです。
―――私は木村さんに云った、―――敏子はあなたから借りたフランス語の本の中に、あの写真が挟まっていたのを見つけて、これは偶然にここに挟んであったものとは思えない、何か意味があるのだろうと云っていました、あれはどういうつもりでしたか。
―――木村さんが云った、―――あれをお嬢さんに見せたら、お嬢さんが何かしら積極的に動いてくれるであろうことを豫期したのです。
僕はこれといって、何もお嬢さんに示唆(しさ)したことはありません。
僕はお嬢さんのイヤゴー的な性格を知っているので、ああすれば十八日の晩のようなことになるのを期待していただけです。
二十三日の晩のことも、今夜のことも、いつもお嬢さんがイニシアチブを取り、僕は黙ってそれに喰(く)っ着いて行ったまでです。
―――私が云った、―――私はあなたと二人きりでこんな話をすることは今が始めてです。
いや誰とでも、夫とでも、こんな話を一度もしたことはありません。あなたと私との関係についても、夫はあまり聞こうとはしません。
聞くのが恐ろしくもあるのでしょうし、今もなお私の貞操を信じていたいからなのでしょう。
私も自分の貞操を信じたいのですけれども、信じても差支えないのでしょうね、それに答えることができるのは木村さんだけです。
―――お信じ下さい、と、木村さんが云った、―――僕は奥さんの肉体のあらゆる部分に触れています、ただ一箇所だけ大切な部分を除いては。
先生は紙一重のところまで僕を奥さんに接着させようとするのですから、僕はその意を体して、それを犯さない範囲で奥さんに近づいたのです。
―――あゝ、それで安心しましたと、私は云った、―――それまでにして私の貞節を完(まっと)うさせて下さるのを有難く思います。木村さんは、私が夫を憎んでいると云われましたが、憎む一面に愛していることも事実です。
憎めば憎むほど愛情も募って来ます。
あの人は、あなたというものを間に入れ、ああいう風にあなたを苦しませなければ情慾が燃え上らない、それも結局は私を歓喜させるためだと思えば、私はいよいよあの人に背くことができなくなります。
でも木村さんはこういう風に考えることはできないでしょうか、私の夫と木村さんとは一身同体で、あの人の中にあなたもある、二人は二にして一であると。………
医者にセックスは控えろと言われるけれど……
三月二十八日(夫の日記)
結果は脳動脈硬化が原因だという。
血圧が非常に高くて相当注意しないといけないそうだ。
ホルモン剤を打つのはやめて、アルコールをやめて、セックスも控えないといけないと言われた。
僕はわざとこのことを日記に隠さず書き、妻のは反応を見ようと思う。
そしてさしあたり僕は医者の忠告に耳を貸さないつもりだ。
いま妻とのセックスはこれまでにない境地にいたっている。
僕はどうしたらこれ以上情欲を駆り立てることができだろうか?
このままではまたすぐに刺激に慣れてしまうだろう。
どうしたら妻の貞操を傷つけることなしに、妻と木村をさらに接近させられるだろうか?
しかし僕がそれを考えるよりも先に、彼らがその方法を考え出さずにはおかないだろう。
彼らというのには、妻と木村だけでなく、敏子も入っている。
現在、僕、妻、木村、敏子の四人が力を合わせて妻を堕落させる、ということに向かって、一生懸命になっているのだ……
三月三十日(妻の日記)
久しぶりに健康な外気を呼吸して非常に爽快な時を過ごした。
三月三十一日(妻の日記)
………昨夜夫婦は酒の気なしに寝に就ついた。
夜中、私は蛍光燈の煌々こうこうとかがやく下で夜具の裾の方から左の足の爪先を、わざとちょっぴり外に出してみせた。
夫はすぐに気がついて私のベッドへはいって来た。
アルコールの力を借りないで、眩まばゆい燭光を強く浴びつつ事を行って成功したのは珍しいことであった。
この奇蹟的な出来事に夫は明らかに異常な興奮の色を示した。………
これは私に彼の日記帳を読ませる余裕を与えるためだと思う。
しかし夫が私に読ませようとすればなお、私は夫の日記を読まない。
しかしそれなら私の方も彼にこの日記帳を盗み読みする機会を作ってやらねばなるまい……。
三月三十一日(夫の日記)
彼女は行為の間中非常に積極的だった。
一体急にどうしたというのだろう。
眩暈があいかわらず激しい。
医者の所に行って血圧の検査をしてもらう。
あまりにも血圧が高いので、なんと血圧計が壊れてしまった。
医者は至急すべての仕事をやめ、絶対安静にする必要があると言う。
妻が木村と二人で会うようになる
四月五日(夫の日記)
どこにいくかは知らない。
敏子が来たときに聞いたが、敏子は「ママも木村さんもさっぱり見えない。どこへ行くのかしら」と首をひねった。
だけど本当は敏子もグルなのだろう。
四月六日(妻の日記)
どうしてそんなことをしているのかというと、私は太陽の下、酒気を帯びていない時に木村さんの裸体に触れてみたかったのだ。
そして現実に確かめた木村さんの裸体は、今年の正月以降、幾度となく幻覚の中で見た通り、美しくたくましいものだった。
木村さんの裸体がまぎれもなく現実のものとなった今、私の中で夫と木村さんは完全に切り離された。
夫の肉体は木村さんのそれのような魅力は一切ない。
ああ、私はなんて自分の好みに合わない嫌な人を夫にもったのだろう。
もし木村さんが夫だったら……とため息がでる。
しかしここまで来ても私と木村さんは最後の一線を越えずにいる。
四月十日(妻の日記)
実は私はもう一二か月前から、夫の様子がおかしいことに気が付いていた。
彼はもともと血色のすぐれない顔つきをしているのだが、最近は特に色つやが悪くて土気色をしている。
階段を上り下りする時にしばしばよろけることがある。
元来記憶力のよい人であったのが、近頃は顕著に度忘れをする。
人と電話で話しているのを聞いていると、当然知っていべきはずの名前が浮かんで来ないで、マゴマゴしていることがある。
室内を歩きながら、突然立ち止まって眼をつぶったり柱につかまったりする。
少し慇懃(いんぎん)な手紙を書くには巻紙へ毛筆でしたためるのだが、字体がひどく拙劣になりつつある。
(書道というものは老年になるほど熟達するのが普通である)
誤字や脱漏が目立って多くなっている。
私が見るのは封筒の上書きだけであるが、日附や番地を間違えるのは始終である。
その間違え方もはなはだ不思議で、三月とすべきを十月としたり、自宅の所番地にとんでもないでたらめを書いたりする
夫は血圧が非常に高く、あと少しで血圧計で壊れそうだったという。
そしてお医者さんがセックスを控えるようにと再三警告したのにもかかわらず、夫はそれを守っていないらしい。
実をいうと最近私も体調が悪い。
おりおり胸が気味悪く疼くし、午後になると毎日のように疲労感が襲ってくる。
もしかして自分には死期が近づいているのではないだろうか?
かといって私と夫が淫蕩のかぎりをつくすことはやめられないだろう。
四月十三日(夫の日記)
この日は妻の外出と入れ替わりで敏子が家にやってきました。そして二人で夕食となります。
夕食中こんな会話となります。
敏子「パパ、ママはどこへ行かはるのか分かってはるの」
父「そんなことはわからないさ、そこまでは知りたくないからね」
敏子「大阪よ」
敏子によると大阪に妻と木村があいびきをする家があるというのです。
敏子「適当な場所があることを私が教えてあげたのよ。京都では人目につきやすいから、京都から遠くない所で、どこかないでしょうかと木村さんが言うから……立ち入ったことを聞くようだけどパパはどう思っているの?」
父「どう思うって、どういうことさ」
敏子「ママが今でもパパに背いていないと言ったらそれを信用するつもり?」
父「ママはお前とそんな話をしたことがあるのか?」
敏子「ママとそんな話はしないわ。木村さんから聞いたのよ。『奥さんは先生に対していまだに貞節を保っておいでです』とあの人が言うのよ。そんな阿呆らしいことを私は真に受けたりしないけれども」
父「御前が真に受けようと受けまいとお前の勝手だ」
敏子「パパはどうなの」
父「僕は郁子を信じる。たとえ木村が郁子を汚したと言ったとしても、僕はそんなことを信じない。郁子は僕を欺くことができるような女ではない」
敏子「ふふ……でも、かりに貞節はまもっていたとしても、それよりもいっそう不潔な方法である満足を……」
父「止めないか敏子、生意気なことを言うのはよせ! 親に対して言っていいことと悪いことがある、貴様こそ汚れた奴だ。用はないならさっさと帰れ!」
父親にそうどやしつけられると、敏子は家を出て行ってしまいました。
夫いよいよ死の淵にたたされる
四月十五日(夫の日記)
正月以来、他の一切を顧みず妻を喜ばすことのみに熱中していたら、いつのまにか淫欲以外のすべてのことに興味を失ってしまった。
読書したり物を思考する能力が全く衰えてしまった。
昼間書斎に籠っている時はたまらない不安に襲われる。
散歩をすると不安がまぎれるけれど、最近では散歩が不自由になってきた。
眩暈がひどくて歩行が困難なことがしばしばなのである。
路上で仰向けに倒れそうになることもある。
脚の力も弱っていて、歩きすぎるとすぐに疲れる。
今日妻が洋装していた。
スカートから除く足は歪んでいて不格好だったがそれがかえって艶めかしく見えた。
僕は妻のスカートから除いた脚を見ながら今夜のことを考えていた。
四月十六日(妻の日記)
十一時頃に家に戻って花をいけていると、夫がようやく起きてきた。
夫はもともと早起きだったが、最近はよく朝寝坊をする。
「今お起きになったの」と聞くと夫は「今日は土曜日だったのか」と言ってから、「明日は朝からでかけるんだろうね」と続けた。
私は肯定とも否定ともつかない返事を口の中でもぐもぐと言った。
二時ごろ指圧の治療師がやってきた。
夫は昔から見知らぬ人に足腰をもませることが嫌いな人で、今まで按摩やマッサージをたのんだことなどなかった。
婆やに聞くと、夫が肩こりがつらくてたまらない、と言っていたので、婆やが知っているマッサージ師を紹介してあげたそうだ。
「えらく凝ってますな、じきに楽にして上げます」と言い、二時間ぐらいした後、
「もう一回か二回で楽になります、明日も来て上げます」と言って帰っていきました。
四月十七日(妻の日記)
夫にとって重大な事件の起った日、私にとっても重大な日であったことに変りはない。木村とのあいびき後、家に帰ると夫は散歩に行っていました。
事によると今日の日記は生涯忘れることのできない思い出になるのではないかと思う。(中略)
私は大阪のいつもの家に行って木村氏に逢い、いつものようにして楽しい日曜日の半日を暮らした。(中略)
私と木村氏とはありとあらゆる秘戯の限りを尽して遊んだ。
私は木村氏がこうしてほしいと云うことは何でもした。
何でも彼の注文通りに身を捻じ曲げた。
夫が相手ではとても考えつかないような破天荒な姿勢、奇抜な位置に体を持って行って、アクロバットのような真似もした。
(いったい私は、いつの間にこんなに自由自在に四肢を扱う技術に練達したのであろうか、自分でも呆れるほかはないが、これも皆木村氏が仕込んでくれたのである)
ばあやに聞くと、妻の留守中に今日もまた指圧師が来て、二時間半ぐらい夫を揉んでいったといいます。
肩がこんなにひどく凝るのは血壓の高い証拠であるが、医者の薬なんぞ利ききはしない、どんなに偉い大学の先生にかかってもそう簡単に直るはずはない、それより私にお任せなさい、請うけ合って直して上げる、私は指壓ばかりでなく、鍼はりや灸やいとも施術する、まず指壓をして利かなかったら鍼をする、眩暈めまいは一日で効験が現われる、などとあの男は云ったという。夫が散歩から戻ってきた後、二人で食事になります。
血壓が高いといっても、神経に病んで頻繁に測るのはよろしくない、気にすれば血壓はいくらでも上る、二百や二百四五十あっても不養生をして平気で生きている人が何人もいる、むやみに気にしない方がよい、酒や煙草たばこも少しぐらいは差支えない、あなたの高血壓は決して悪性のものではないから、大丈夫良くなりますと云ったとやらで、夫はすっかりあの男が気に入ってしまい、これから当分毎日来てくれ、もう医者は止める、と云っていたという。
夫はヒレ肉のビフテキを食べます。
医者からは脂っぽいものは控えるように言われているのですが、それでも夫は精をつけるために食べたがるのでした。
またブランデーも一人で一杯ずつ飲みます。
そして二人は夫婦の行為を始めます。
妻はもう夫を嫌っているのですが、不思議と夫の行為はそれほど嫌ではありませんでした。
私は、愛情と淫慾とを全く別箇に処理することができるたちなので、一方では夫を疎うとんじながら、―――何というイヤな男だろうと、彼に嘔吐おうとを催しながら、そういう彼を歓喜の世界へ連れて行ってやることで、自分自身もまたいつの間にかその世界へはいり込んでしまう。そんなわけで二人が燃えあがっている最中でした。
夫の体がにわかにぐらぐらとして、妻の体の上に崩れ落ちてきました。
私はすぐに異常なことが起ったのを悟った。
「あなた」と私は呼んでみたが、彼はロレツの廻らない無意味な声を出すのみで、生ぬるい液体がたらたらと私の頬を濡らした。
彼が口を開けて涎よだれを滴たらしているのであった。………
夫が寝たきりになっても、木村とのあいびきは続く
四月十八日(妻の日記)
その後夫は昏睡状態となります。妻は敏子を呼びました。
医者を呼んでみてもらうと原因は脳溢血のようでした。
妻との行為が一番の引き金でしたが、二日間も二時間以上強い指圧をしたのもいけなかったようです。
その後、夫は昏睡からは目をさましましたが、口をもぐもぐさせるだけ。
まともに口も聞けない状態です。
食事は牛乳と果汁で、自力で排便もできなくなってしまいました。
看病のために看護婦さんも呼びます。
妻は木村に電話をして夫の様態を知らせます。
木村は、見舞いに行きたいと言いました。
妻は病人を興奮させるといけないから、病室にはあがらず玄関までで帰ってほしいと木村に頼みます。
四月十九日以降(妻の日記)
夫の様子は相変わらずです。
何か言葉を発していますが、不明瞭で聞き取れません。
夫はたまに言葉を発するとき「きーむーら」と言っているように聞こえます。
また「にーき」「にーき」ともいいます。
妻が「日記をお附けになりたいの? でもまだ無理よ」と聞くと、夫は違うと首を振ります。
そして夫は「お前は……お前は日記をどうしている?」と聞きます。
妻は「私は昔から日記なんてつけていません、そんなこと、あなたは知ってはるやありませんか」とごまかしました。
しかし妻は夫が自分の日記に関心をもっていることを知ると危機感を覚えました。
妻はこう考えました。ショートコード
毎晩夜十一時になると、木村が必ず家を訪ねてきて、一時間ぐらいたって帰ります。
(はっきりとは書かれていませんが、日記のふしぶしから、二人はほぼ会話をせずに愛し合う行為をしている、ということがわかります)
夫が倒れてからと言うもの敏子が毎日のように看病にきます。
ある日敏子は母にこう言います。
「ママ、買い物が溜っていはしないの。
………たまの日曜に外の空気を吸うて来やはったらどう?」
妻はこれは木村が敏子に言われてのことではないか? と思って外出し、買い物がてらに木村に会いに行きます。
木村とほんの少し話した後、すぐに愛し合う行為に入り、一時間ぐらいして家に戻ります。
五月一日(妻の日記)
夫が倒れてから三度目の日曜日でした。敏子が家にきて、「買い物かたがた息抜きしてらっしゃい。私の下宿のお風呂が沸いているから、ついでに入っていらっしゃい」と母をねぎらいます。
郁子が敏子の下宿に行ってみると、風呂は沸いていなくて、下宿の女主人は留守。
しかも木村がいました。
木村に聞くと、敏子に「今日は下宿のマダムが留守で、私も家に看病に行くから、すまないけれど二三時間留守番に来てほしい」と言われたというのです。
郁子は木村と半月ぶりにゆっくり話すことができた。
(二人はしばしば会ってはいたのですが、会うたびに、ろくに話もせずに、すぐに愛し合う行為に入っていたので、ゆっくり話せたのは半月ぶりなのです)
郁子が家に帰ると看護婦さんが血色のよい顔で「お嬢さんにお願いして、お風呂へ行ってきました」と言います。
郁子はハッとします。
それにそうなるように仕向けたのは敏子らしい。
日記を敏子に盗み読みされたのではないだろうか?
しかし、いつも盗み読みを心配していた夫が倒れて以来、読まれることを想定していなかったため、セロハンテープの封はしていませんでした。
日記を確かめても、読まれたか読まれなかったのかはなかなか判別がつきません。
日記が敏子に読まれたかどうか気がかりでしかたがない郁子。
婆やに今日の午後自分が外出した後で、誰かが二階の書斎へ上がりはしなかったか? と尋ねます。
婆やは
「はあ、お嬢さんがお上りになりました」と答えます。
婆やによると、妻が出かけてから15分ほどたって看護婦さんが銭湯へ出かけたらしい。
それから間もなくして敏子が二階へ上って行ったそうですが、二三分で下りてきて病室に戻り、夫と何か話している様子だったといいます。
そして敏子は夫としばらく話したのち、もう一度二階へ上って、またすぐ下りてきたといいます。
妻はこう疑います。
ここで一往いちおう敏子の今日の行動を順に並べてみると、―――午後三時、口実を設けて私を外へ出してしまう。
次に小池さんを風呂へ行かせる。
次に病人が自ら眼を覚まして敏子に告げたか、敏子から病人に働きかけたか、そこのところは不明であるが、彼女は私の日記帳が茶の間の用箪笥に入れてあることを知り、それを捜し出して病人の枕元へ持って来る。
病人が、この帳面は四月十六日で終っているが、十七日以後の分も必ずどこかに秘してあるに違いない、己おれが読みたいのはその方であるから捜してくれと云う。
そこで彼女は二階の書棚を探って見つけ出す。
次にそれを病室へ持参して病人に見せる。
あるいは読んで聞かせる。
次に二階へ持って上って元の場所に収めて来る。
小池さんが戻って来る。
夫の死後、いま明かされる真実
さて郁子は五月一日に日記をつけた後、一月あまりも日記を中断していました。そしてその間に夫は亡くなりました。
最後に日記をつけた翌日の五月二日に夫が二回目の発作を起こして倒れ、まもなく亡くなったのです。
(五月三日の午前三時ごろでした)
夫がいない今、郁子はもう日記をつける張り合いをなくしてしまいました。
けれども正月以来、百二十一日もつけてきた日記がポツリと途切れてしまうのも嫌なので、結末として最後の日記をつけることにしたのです。
そしてそこには、夫の生前には書き記すことを憚っていたことを書き加えて締めくくりにするつもりでした。
六月九日 妻の日記
医者は夫がこんなに早く亡くなるとは思ってもいなかったと言う。
脳溢血は十年前でも一度脳溢血にかかるとそれから二三年、もしくは七八年後に二回目の発作に襲われてその時に亡くなることが多いそうだ。
しかしこれも昔のことで、近年は医学の進歩が著しく、一度かかっても二度目にかからなくなったり、二度目、三度目の発作があっても再起して、天寿を全うする人もいるらしい。
医者は夫も今後数年あるいは、うまくいけば十数年は活動できるだろうと思っていたと言ってくれた。
しかし私にとっては、こうなることは予想していたことだった。
そしておそらく敏子もこうなることを予想していただろう。
まず妻は日記には自分は夫の日記を盗み読みしたことなどない、と書いていましたが、これは嘘。
実は妻は夫が日記の入っている引き出しの鍵を書斎に落としておいた正月よりもずっと前の昔から、夫の日記を盗み読みしていました。
妻は夫と結婚したその翌日あたりから、ときどき彼の日記帳を盗み読みしていたといいます。
木村との関係は夫の日記を読んで触発されたのがきっかけでした。
日記を読んで、夫が妻への嫉妬に掻き立てられて初めてまともに夫婦の行為ができると知った妻は、夫のために他の男性にちょっと興味をもってみるのだ、と思い木村に向かい始めます。
ブランデーで酔って「木村さん」とうわごとを言ったときは半分わざとで、半分夢うつつでした。
あの譫語には、「木村サントコンナ風ニナッタラナア」という気持と、「夫があの人を私に世話してくれたらなあ」という気持と、二つの願望が籠っていたに違いなく、それを分って貰うためにあの言葉を云った。妻はこう言っています。
敏子はまだあの時まだ家にいたし、ストーブがごうごうと燃えていたのだから、気づかれないように両親の寝室を覗き、夫が私にしていることを見ることもできたはずだ。
木村が夫にポラロイドを貸したのは、夫の歓心を得るためと、ポラロイドでとっているうちに夫がそれで満足できなくなり、普通のカメラで写すようになり、そして夫が木村に現像を頼むようになる。
そうすれば自分が私の裸体写真を手にいれることができると思ったからだろう。
二月十九日に「敏子の心理が読めない」と日記に書いていたが実際はだいたい掴めていた。また郁子(妻)は四月十日になって、始めて夫の健康が尋常でないことを日記に書きましたが、実際はそれの一二カ月前から、それに気がついていました。
私は彼女がわれわれ夫婦の閨房の情景を木村に洩らしたであろうことは、ほぼ推していた。彼女は木村を、心密(ひそ)かに愛しているのであり、それゆえに「内々私に敵意を抱きつつある」ことも分っていた。
彼女は、「母は生れつき繊弱なたちで過度の房事には堪えられないのに、父が無理やりに云うことを聴かせ」ているのであると解し、その点では私の健康を気づかい、父を憎んでいたのであるが、父が妙な物好きから木村と私とを接近させ、木村も私もまたそれを拒(こば)まない風があるのを見て、父を憎むとともに私をも憎んだ。
私はそれを随分早くから感づいていた。
ただ、私以上に陰険である彼女は、「自分の方が母より二十年も若いにかかわらず、容貌姿態の点において自分が母に劣っている」ことを知っており、木村の愛がより多く母に注がれていることを知っているがゆえに、まず母を取り持っておいて徐(おもむ)ろに策を廻(めぐ)らすつもりでいたことも、私には読めていた。
(中略)
敏子が私を嫉妬していたように、私も内心敏子に対してかなり激しい嫉妬を燃やしていた。
にもかかわらず、私は努めてそのことを人にも悟らせず、日記にも書かないようにしていた。
それは私の持ち前の陰険性のゆえでもあるが、それよりも、自分の方が娘よりも優れているという自信を持っていたところから、その自尊心を自ら傷つけたくなかったからであった。
なおもう一つ、私が敏子を嫉妬する理由のあること―――というのは、木村が彼女をも愛しているかも知れないという疑いのあること―――を、夫に知られるのを何よりも私は恐れた。
(中略)木村は一途に私一人を愛しているもの、私のためにはいかなる犠牲をも惜しまないでいるものと、夫に思わせておきたかった。
そうでなければ、夫の木村に対する嫉妬が生一本で強烈なものにならないからであった。(中略)
「自分が日記をつけていることを夫に感づかれるようなヘマはやらない」―――「私のように心を他人に語らない者は、せめて自分自身に向って語って聞かせる必要がある」―――などと云っているのは、真赤な である。私は夫に、私には内証で読んで貰うことを欲していた。(中略)
では何のために音のしない雁皮紙を使ったり、セロファンテープで封をしたりしたかといえば、用もないのにそういう秘密主義を取るのが生来の趣味であったのだ
夫が自分の健康状態について日記に書き始めたのは三月十日からですから、夫の心身の異変についてについて郁子(妻)のほうが先に知っていわけです。
しかし当初は郁子はそれを夫に気づかせまいとしました。
それは夫がそれに気が付くと房事を控えるようになるからと恐れたからです。
郁子にとって夫の生命の安全よりも性的満足の方が切実な問題でした。
また郁子はこうも言っています。
三月二十六日に私と木村のそらぞらしい門答(「私の夫と木村さんとは一身同体で、あの人の中にあなたもある、二人は二にして一である」というのですね。)が書かれているのは、それをごまかすためである。
しかし三月の下旬に木村と結ばれたとしても、三月中はまだ、夫のために木村を刺激剤として利用しているという意識がどこかにあった。
しかし四月に上旬、四月四,五,六日ころにはそれは無くなった。
その時あたりから私はきっぱりと自分が本当に愛しているのは木村であって夫ではないことを自覚した。
四月十日に自分も体調が悪いことや、自分には死期が近づいているような気がする、と書いたのは全くのウソである。
あれは「私も死を賭しているのだから、あなたもその気におなりなさい」と夫を煽り、夫を一日も早く死なせるために書いたのである。
その後の日記は私の日記はもっぱらその目的のために書かれた。
私は彼を息(いこ)う暇なく興奮させ、その血壓を絶えず上衝させることに手段を悉(つく)した。そして最後に夫の死という結果となったわけでした。
今後は木村と敏子が結婚した、という形式をとって、郁子(妻)、木村、敏子の三人でこの家に住むことになっています。
敏子は世間体を繕うために、甘んじて母のために犠牲になる、と、いうことになっているわけですが………それは表向きのことだろうと
郁子(妻)は疑っています。
敏子のことや木村のことも、今のところ疑問の点がたくさんある。敏子や木村の意図、までは明らかにされずに物語は終わっています。
私が木村と会合の場所に使った大阪の宿は、「ドコカナイデショウカト木村サンガ云ウカラ」敏子が「オ友達ノ或ルアプレノ人」に聞いて教えてやったのだというけれども、ほんとうにそれだけが真実であろうか。
敏子もあの宿を誰かと使ったことがあり、今も使っているのではないであろうか。
PR
本の要約サービス SUMMARY ONLINE(サマリーオンライン)月額330円で時短読書 小説の要約も多数あり!!谷崎潤一郎 まとめ記事
 谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
 宇美の文学
宇美の文学