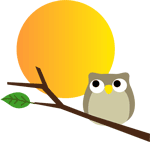『母を恋ふる記』は大正8年に発表された、谷崎潤一郎の短編。
夢を描いた作品ですが、谷崎潤一郎の自伝的な作品です。
谷崎潤一郎の生涯について知りたい方にもおすすめです。
目次
母を恋ふる記のあらすじ
神秘的な冒頭
「母を恋うる記」はこんな冒頭で始まります。
……空はどんよりと曇って居るけれど、
月は深い 雲の奥に呑まれて居るけれど、
それでも何処からか光が洩れて来るのであろう、
外の面は白々と明るくなって居るのである。その明るさは、明るいと思えば可なり明るいようで、
路ばたの小石までがはっきりと見えるほどでありながら、
何だか眼の前がもやもやと霞んで居て、遠くをじっと見詰めると、
瞳が操ったいように感ぜられる、
一種不思議な、幻のような明るさである。何か、人間の世を離れた、
遙かな遙かな無窮の国を想わせるような明るさである。その時の気分次第で、
闇夜とも月夜とも孰方(どっち)とも考えられるような晩である。
そんな中しろじろとした中にも際立って白一筋の街道が、幼い潤一の前にまっすぐと走っていました。
街道の両側には長い長い松並木が目の届く限り続いています。
松並木は時々左の方から吹いてくる風のためにざわざわと枝葉を鳴らします。
風は湿り気を含んでいて、潮の香がします。
きっと海が近いんだな、と潤一は思いました。

なぜ、ばあやは一緒に来てくれなかったんだろう。
ばあやはあんまり僕がいじめるので、怒ってうちを出ていってしまったのじゃないかしら?
潤一はまだ七、八歳。
幼いころからとても臆病な子供でしたから、こんな夜更けに淋しい田舎町を歩くのは心細くてしかたありません。
そんなふうに思いながら、幼い潤一はいつもほどは怖がらないで、夜の街道をひたすら進みます。
潤一の悲運
まもなく潤一の胸の中は夜道の恐ろしさよりも、もっとやるせない悲しみで一杯になりました。
というのは潤一はもともと裕福な家の子供でした。
それが急に家運が傾いて、にぎやかな日本橋の真ん中から、こんな辺鄙な片田舎へひっこさなければならなくなったのです。
潤一はこの前までは
黄八丈の綿入れに艶々とした糸織の羽織を着て、ちょいと出るにもキャラコの足袋に表付きの駒下駄を穿いて居た
という坊っちゃんらしい恰好をしていたのに、いまでは
まるで寺小屋の芝居に出て来る涎くりのような、うすぎたない、見すぼらしい、人前に出るさえ恥かしい姿
手にも足にもひびやあかぎれが切れて軽石のようにざらざら
になってしまっています。
そうです、ばあやがいなくなったのもあたりまえでした。
もう潤一の家にはばあやを雇うほどのお金がないのです。
それどころか幼い潤一すらお父さん、お母さんを助けるために一緒に働かなくてはならない境遇でした。
今の潤一は毎日、
水を汲んだり、火を起したり、雑巾がけをしたり、遠い所へお使 いに行ったり、
というお手伝いに追われているのです。
潤一は日本橋の中心地で何不自由なく暮らしていたころのことを回想してせつなくなります。
もう、あの美しい錦絵のような人形町の夜の巷をうろつく事は出来ないのか。
水天宮の縁日にも、茅場町の薬師様にも、もう遊びに行く事は出来ないのか。それにしても米屋町の美代ちゃんは今頃どうして居るだろう。
鎧橋の船頭の枠の鉄公はどうしただろう。蒲鉾屋の新公や、下駄屋の幸次郎や、あの連中は今でも仲よく連れだって、煙草屋の柿内の二階で毎日毎日芝居ごっこをして居るだろうか。
もうあの連中とは、大人になるまで恐らくは再び廻り思う時はない。
それを考えると恨めしくもあり情なくもある。
しかし潤一の悲しみはそれだけではなくてもっと深いものがありそうでした。
それは潤一にもなんの悲しみであるのかわかりません。
私の胸には理由の知れな い無限の悲しみが、ひしひしと迫って居るのである。
なぜ此のように悲しいのだろう。
そうして又、それ程悲しく思いながらなぜ私は泣かないのだろう。私は不断の泣虫にも似合わず、涙一滴こぼしては居ないのである。
たとえば哀音に充ちた三味線を 聞く時のような、冴え冴えとした、透き徹った清水のように澄み渡った悲しみが、何処からともなく心の奥に吹き込まれて来るのである。
灯りを目指して歩き続ける
潤一の歩く道のわきは最初は畑だったようですが、しだいに海が近くなったのか「ど、ど、どどどん」という波の音が聞こえてきます。
カサカサという声も聞こえますが、音の正体はわかりません。
潤一はもう一時間以上歩いているのに、一切他の人に会いません。
またどちらを向いても人家の灯りらしいものがみつかりません。
どこまで続くかわからない道を歩く潤一。
せめての目標に、潤一は一本の電信柱を追い越すと、一本、二本、三本、と電信柱の数を数えます。
灯りを目指して
七十本目の電信柱を数えた時でした。
遠い街道のかなたにはじめて、一点の灯りがぽつりと見えだしました。
こんどは潤一はその灯りを目標に歩き出しました。
しかし灯りは、近いと見えてかなり遠いようで、なかなかたどりつきません。
灯りの大きさはいくら歩いても提灯ぐらいのままです。
潤一はときおり、

あの灯りは自分と同じ速度で前に進んでいるのでは?
と思います。
数十分ぐらい歩いてやっと灯りは大きくなり、強く鮮やかになりました。
あいかわらずカサカサという音が聞こえます。
灯りに照らされた音の方を見ると、それはあたり一面の古沼で沢山の蓮が植わっていました。
蓮は枯れかかっていて、その葉が風の吹くたびにカサカサという音をたてていたのです。
潤一は古沼を眺めました。
非常に大きな沼のようで、見渡す限りが沼と蓮です。
潤一はその中にたった一点赤い光を発見しました。
あ、彼処に灯が見える。
彼処に誰かが住んでいるのだ。
あの人家が見え出したからには、もう直き町へ着くだろう
幼い潤一は嬉しくなって、明るく照らされた街道から暗い方へと歩き出しました。
500から600Mぐらい歩くと灯りはだんだん近くなってきました。
そこには一軒の茅葺の農家があって、その家の窓の障子から明かりが洩れていました。
潤一はこう期待します。
あのわびしい野中の一軒家には、私のお父さんとお母さん がいるのではないかしら。
彼処が私の家なのではないかしら。あの灯の点っている懐かしい窓の障子を明けると、年をとったお父さんとお母さんとが囲炉裏の傍で粗朶を焚いていて、
「おお潤一か、よくまあお使いに行って来てくれた。さあ上って火の傍にお出で。ほ んとうに夜路は淋しかったろうに、感心な子だねえ」
そう云って、私をいたわって下さるのではないかしら。
期待外れ
家が近づいてくると、おいしそうな食べ物の匂いがします。
みそ汁や、魚を焼く匂いでした。

ああ、お母さんは僕の大好きな秋刀魚を焼いているんだな。
きっとそうに違いない。
早くあそこに行って、お母さんと一緒に秋刀魚とみそ汁を食べたいな。
潤一はついにその家にたどり着きました。
中をのぞくと、潤一の思った通りお母さんが後ろ向きになって手ぬぐいを姐さんかぶりにして、台所で炊事をしていました。潤一はこう考えました。
東京で何不足なく暮していた時分には、ついぞ御飯なぞを炊いたことはなかったのに、さだめしお母さんは辛いことだろう。
お母さんの背中は、丸くなっていました。

まあ、いつの間にこんな田舎のお婆さんになってしまったんだろう?
と潤一は思います。
潤一はお母さんに声をかけます。

お母さん、お母さん、私ですよ。
潤一が帰って来たんですよ。
振り向いたお母さんは髪の毛は白髪交じり、頬にも額にも深いしわが寄っています。
目はしょぼしょぼとしていて、目やにだらけです。

お前は誰だったかね?
お前は私の枠だったかね?

ええそうです。
私はお母さんの枠です。
枠の潤一が帰って来たんです。

私はもう長い間、十年も二十年もこうして忰の帰るのを待っているんだが、しかし お前さんは私の忰ではないらしい。
私の忰はもっと大きくなっている筈だ。
そうして 今にこの街道のこの家の前を通る筈だ。
私は潤一なぞと云う子は持たない。

ああそうでしたか。あなたは余所のお婆さんでしたか。
たしかにこの女性は潤一のお母さんにしては老けすぎです。
いくら落ちぶれて苦労したとしても、潤一の母の年齢でここまで老けてしまうはずがありません。
そうすると潤一の母はいったいどこにいるのでしょう?

ねえお婆さん!
私はわたしのお母さんに会いたくて、こうして此の街道を先から歩いて居るんですが、お婆さんは私のお母さんの家が何処にあるか知らないでしょうか?
お婆さんは

お前さんのおふくろの家なんぞを私が何で知るもんかね
と冷たい態度。
おなかぺこぺこの潤一はお婆さんに食事をめぐんでくれるようにたのみますが、お婆さんは

これは今にわたしの忰が帰ってきたら食べさせるものなんだよ。
お前なんかにやれないよ。
と冷たい態度です。
いくら頼んでも食べ物をわけてくれないので潤一はついにあきらめて家を出ました。
海が近くなる
潤一は再び街道を進みます。
街道のさらに5, 600M先には丘があるようです。
街道はその丘のふもとまでまっすぐに伸びているようですが、丘に突き当たってからはその先の道はどうなっているのかは、潤一のいる場所からはよくわかりません。
丘には松の木が生えていて、街道の脇の松並木と同様に真っ黒です。
大きな松の木の林が丘のふもとから頂上までこんもりと茂っているようでした。
さあっさあっという松風の音が聞こえます。
潤一は丘に向かって歩きます。
もう蓮沼のカサカサという音は聞こえません。
ごうっごうっという海の轟きばかりが鳴っています。
足の下がやけにやわらかくなりました。
歩くたびにぼくりぼくりとへこみます。
道が砂地になっているようです。
道は松の林の間をぬうように続いていて、右に左にしょっちゅう折れ曲がります。
うっかりすると松林にまぎれこんでしまいそうで、潤一はどきどきしてきます。
月
ここであたりの雰囲気がぱっとかわりました。
松林のまばらになっている先に丸く小さな光る月が輝いています。
銀が光っているような鋭い冷たい明るさでした。
「ああ月だ月だ、海の面に月が出たのだ」
潤一はそう思いました。
冴え返った銀光がピカピカと、
練絹のように輝いている。私の歩いている路は未だに暗いけれど、
海上の空は雲が破れて、
其処から餃々たる月がさしているのだろう。見ているうちに海の輝きはいよいよ増して来て、
此の松林の奥へ までも眩しいほどに反射する。(中略)
きらきらと絶え間なく反射しながら、
水の表面がふっくらと膨れ上って、(中略)
海の方から晴れて来る空は、
だんだんと此の山陰の林の上にも押し寄せて、
私の歩く路の上も刻一刻に明るくなって来る。しまいには私自身の姿の上にも、
青白い月が松の葉影をくっきりと染め出すようになる。
丘の頂上は次第に視界の左の方へ遠退いて行きます。
潤一はいつの間にか海の目の前に立っていました。

ああ何と云う絶景だろう
と潤一はは暫く恍惚としてたたずんでいました。
街道は、白泡の砕けている入り組んだ海岸線にうねうねと限りなく続きています。
街道と波打ち際との間には、
雪のように真白な砂地が、
多分凸凹に起伏しているのであろうけれど、
月の光があんまり隈なく照っているために、
その凸凹が少しも分らないで唯平べったくなだらかに見えその向うは、
大空に懸った一輪の明月と地平線の果てまで展開している海との外に、
一点の眼を遮るものもない。(中略)
其の海の部分は、単に光るばかりでなく、
光りつつ針金を捩じるように動いているのが分る。或は動いているために、
一層が強いのだと云ってもよい。其処が海の中心であって、
其処から潮が渦巻き上るために、
海が一面に膨れ出すのかも知れない。何しろ其の部分を真中にして、
海が中高に盛り上って見えるのは事実である。盛り上った所から四方へ拡がるに随って、
反射の光は魚鱗の如く細々と打ち砕かれ、(中略)
その時風はぴったりと止んで、
あれほどざわざわと鳴っていた松の枝も響きを立てない。渚に寄せて来る波までが此の月夜の静寂を破ってはならないと力めるかの如く、
かすかな、遠慮がちな、
囁くような音を聞かせているばかりである。それは例えば女の忍び泣きのような、
蟹が甲羅の隙間からぶつぶつと吹く泡のような、
消えるようにかすかではあるが、
綿々として尽きることを知らない、
長い悲しい声に聞える。その声は「声」と云うよりも、
寧ろ一層深い「沈黙」であって、
今宵の此の静けさを更に神秘にする情緒的な音楽である。.
そんな絶景の中、なぜだか興奮して急ぎ足で歩く潤一。
こんなことを考えています。
私は前にもこんな景色を何処かで見 た記憶がある。
而も其れは一度ではなく、何度も何度も見たのである。
或は、自分が此の世に生れる以前の事だったかも知れない。
前世の記憶が、今の私に蘇生って来 るのかも知れない。
其れとも亦、実際の世界でではなく、夢の中で見たのだろうか。
うっかりしていると、
自分もあの磯馴松や砂浜のように、
じっとしたきり凍ったようになって、
動けなくなるかも知 れない。そうして此の海岸の石と化して、
何年も何年も、あの冷たい月光を頭から浴びていなければなるまい。実際今夜のような景色に遇うと、
誰でもちょいと死んで見たくなる。此の場で死ぬならば、
死ぬと云う事がそんなに恐ろしくはないようになる。
隈ない月の光が天地に照り渡っている。
そうして其の月に照される程の者は、
悉く死んでいる。ただ私だけが生きているのだ。
私だけが生きて動いているのだ
三味線の音
潤一が歩き続けていると、遠くから三味線の音がしました。
それは
天ぷら喰いたい、天ぷら喰いたい
と言っているように聞こえています。
潤一が三味線の音が「天ぷら喰いたい」と言っているように聞こえるようになったのは、まだ日本橋で裕福な暮らしをしていたとき、ばあやが、家の近くを通った弾き流しをしている芸人の三味線を聞いて
ねえ、聞えるでございましょ
と言っていたからでした。

天ぷら喰いたい……天ぷら喰いたい……
という三味線の音を聞きながら潤一は長い間歩き続けます。
もう二年も、三年も、ひょっとしたら十年も歩き続けたような気がしました。
潤一は歩きながら、

私はもう此の世の人間ではないのかしら?
人間が死んでから長い旅に上る、其の旅を私は今しているのじゃないかしら
と思います。
三味線を弾く若い女性の後ろ姿
しだいに三味線の音は大きくなり、潤一はついに三味線を弾く人の人影を認めます。
今や其の三味線の音は間近くはっきりと聞えている。
さらさらと砂を洗う波の音の伴奏に連れて、
冴えた撥のさばきが泉の消滴のように、
銀の鈴のように、神々しく 私の脳に沈み入るのである。三味線を弾いている人は、疑いもなくうら若い女である。
昔の鳥追いが被っているような編笠を被って、
少し俯向いて歩いている其の女の襟足が月明りのせいもあろうけれど、
驚くほど真白である。若い女でなければあんなに白い筈がない。
時々右の袂の先からこぼれて出る、
転診を握っている手頸も同じように白い。まだ私とは一町以上も離れているので、
着ている着物の縞柄などは分らないのに、其の襟足と手頸の白さだけが、
沖の波頭が光るように際立っている。
潤一はこう思いました。

あ。わかった!
あれは人間ではない。きっと狐だ。
狐が化けているのだ。
潤一は、成る可く是音を立てないように恐る恐る其の人影に付いて行きました。
人影は相変らず三味線を弾きながら、振り向きもせずにとぼとぼと歩いています。
しかしあの若い女性がもしも狐だとすれば、潤一に後をつけられているのに気が付かないはずがありません。
きっとわざと知らんぷりをしているのでしょう。
女の後姿は次第次第に近づいて来ました。
女の踵は、――此の寒いのに女は素足で麻裏草履を穿いている。
――此れも襟足や手頸と同じように真白である。(中略)
恐ろしく長い裾である。
其れはお召とか縮緬とか云うものでもあろうか、
芝居に出て来る色女や色男の着ているようなぞろりとした裾が、
足の甲を包んで、ともすると砂地へべったりと引き摺るほどに垂れ下っている。
けれども、砂地がきれいであるせいか足にも裾にも汚れ目はまるで付いていない。ぱたり、ぱたりと、草履を挙げて歩く度毎に、
舐めてもいいと思われるほど真白な足の裏が見える。
狐だか人間だかまだ正体は分らないが、
肌は紛うべくもない人間の皮膚である。月の光が編笠を滑り落ちて寒そうに照らしている襟足から、
前屈みに屈んでいる背筋の方へかけて、
きゃしゃな背骨の隆起しているのまでがありありと分る。背筋の両側には細々とした撫肩が、
地へ曳く衣と共にすんなりとしている。左右へ開いた編笠の庇よりも狭いくらいに、
其の肩幅は細いのである。折々ぐっと俯向く時に、
びっしょり水に濡れたよ うな美しい葛の毛と、
其の毛を押えている笠の緒の間から、
耳朶の肉の裏側が見える。
しかし、見えるのは其の耳朶までで、
其れから先にはどんな顔があるのだか、
笠緒が邪魔になってまるっきり分らない。なよなよとした、風にも堪えぬ後姿を、
視詰めれば視詰めるほど、
ますます人間離れがしているように感ぜられて、
やっぱり狐の化けているのではないかと訝しまれる。いかにも優しい、か弱い美女の後姿を見せて置いて、
傍へ近寄ると、「わっ」と云って般若のような物凄い顔を此方へ向けるの じゃないか知らん。
潤一と三味線を弾く女性
潤一は彼女と並びました。
高い立派な鼻が見えました。
潤一は

大丈夫だ、彼女はきれいな女性だ
と思います。
潤一は非常にうれしく思いました。
彼女は絵のような完全な美しさをもった若い女性でした。
潤一は彼女に話しかけます。
潤一は本当は彼女を「姉さん」と呼びたいと思います。
潤一には姉はいないのですが、美しい姉がほしいといつも思っていました。
きれいなお姉さんがいる友達を非常に羨しく思っていました。
そして潤一はこの女性に、姉に対するような甘い懐しい気持を感じていました。
「小母さん」と呼ぶのは本当は嫌だったけれども、いきなり「姉さん」と呼んでは余り 馴れ馴れしいように思われたので、しかたなく「小母さん」と呼んだのです。
女は返事をしません。
ひたすら三味線を弾きながら、さらり、さらり、と長い着物の裾を砂に敷きながら俯向いて真直に歩いて行きます。
どうやら自分の弾いている三味線の音に聞き惚れているようでした。
潤一は一歩踏み込み、今迄横顔しか見ていなかった彼女の顔を正面から眺めました。
女はふと立ち止まって、俯いていた顔を上げて、月を見上げました。
そしてぽろぽろと涙を流します。

小母さん、小母さん、小母さんは泣いているんですね。
小母さんの頬ぺたに光って いるのは涙ではありませんか。
女は空を見上げながら答えます。

涙には違いないけれど 私が泣いているのではない。

そんなら誰が泣いているのですか?
その涙は誰の涙なのですか?

これは月の涙だよ。
お月様が泣いていて、その涙が私の頬の上に落ちるのだよ。
あれ御覧、あの通りお月様は泣いていらっしゃる。
潤一は女に言われて月を仰ぎます。
しかしお月様が泣いているのかどうかはよくわかりませんでした。
潤一は

僕がまだ子供だからそれがわからないのだろう
と思います。

でもそれにしても、月の涙が女の頬の上にばかり落ちてきて、自分の頬に降りかからないのはなぜだろう
とも思います。
そして女性にこう言いました。

あ、やっぱり小母さんが泣いているんだ。
小母さんは嘘を言ったのだ。

いいえ、いいえ、何で私が泣いているものか。
私はどんなに悲しくっても泣きはしない。
そう言いながらも女は明らかにさめざめと泣いています。
瞼の陰から涙がこんこんと湧き出て、鼻の両側をつたって頤のほうへと糸を引きながら流れています。
声を殺してしゃくりあげるごとに、のどの骨が皮膚の下から痛々しくあらわれます。
女は鼻水をすすり、唇から侵入した涙を呑みこんだのか、ごほんごほんとむせました。

それ御覧なさい。
小母さんは其の通り泣いているじゃありませんか。
ねえ小母さ ん、何がそんなに悲しくって泣いているんです。

お前は何が悲しいとお云いなのかい?
こんな月夜に斯うして外を歩いて居れば、 誰でも悲しくなるじゃないか。
お前だって心の中ではきっと悲しいに違いない。

それはそうです。
私も今夜は悲しくって仕様がないのです。
ほんとうにどう云う訳でしょう。

だからあの月を御覧と云うのさ。
悲しいのは月のせいなのさ。
お前もそんなに悲しいのなら、私と一緒に泣いておくれ。
ね、後生だから泣いておくれ。

ええ、泣きましょう、泣きましょう。
小母さんと一緒にならいくらだって泣きましょう。
私だって先から泣きたいのを我慢していたんです。
潤一もぽろぽろと涙を流し始めました。
女の正体は?

小母さん、小母さん、私は小母さんの云う通りにして、一緒に泣いているんです。
だから其の代り小母さんの事を姉さんと呼ばしてくれませんか。
ねえ、小母さん、此れから小母さんの事を姉さんと云ったっていいでしょう?

なぜだい?
なぜお前はそんな事を云うのだい?

だって私には姉さんのような気がしてならないんですもの。
きっと小母さんは私の姉さんに違いない。
ねえ、そうでしょう?
そうでなくっても、此れから私の姉さんになってくれてもいいでしょう

お前には姉さんがある訳はないじゃないか。
お前には弟と妹があるだけじゃないか。
――――お前に小母さんだの姉さんだのと云われると、私は猶更悲しくなるよ。

それじゃ何と云ったらいいんです。

何と云うって、お前は私を忘れたのかい?
私はお前のお母様じゃないか。
こう云いながら、女は顔を潤一の顔に近づけました。
その瞬間に潤一ははっと思 います。

云われて見れば成る程彼女はお母さんに違いない。
僕のお母さんががこんなに若くきれいな筈はないけれど、それでもたしかに彼女は母に違いない。
どう云う訳か潤一はそれを疑うことができませんでした。
潤一は

自分はまだ小さな子供だ。
だから母が此のくらい若くて美しいのは当り前かも知れない、
と思います。

ああお母さん、お母さんでしたか。
私は先からお母さんを捜していたんです。

おお潤一や、やっとお母さんが分ったかい。
分ってくれたかい。
母は潤一をしっかりと抱きしめました。
母の懐には甘い乳房の匂が暖かく籠っていました。
依然として三味線の音が聞こえます。
月の光と波の音とが身にしみわたります。
二人の頬には 涙が止めどなく流れています。
潤一はふと眼を覚ました。
夢の中で泣いていたと見えて、枕は涙で湿っていた。
眼を覚ました潤一は今年三十四歳です。
そして潤一の母は、一昨年の夏此の世の人ではなくなっていたのです。
母がもうこの世の人でないことを思い出すと、潤一はまたぽたりと涙を落としました。
「天ぷら喰いたい、天ぷら喰いたい」
三味線の音が、まだ潤一の耳の底で響いています。
感想
夏目漱石の『夢十夜』 を思わせる小説。
夢らしい幻想的で美しい光景、ストーリーですね。
幼い子供を主人公にすることによってさらに効果を出しています。
誰でもこれと似たような夢を見たことがあるのではないでしょうか?
私はこの小説を読んで、懐かしいような、切ないような気分になりました。
後半の三味線を弾く厚化粧の女性、は東京の下町出身の谷崎潤一郎ならではのシーンですが、前半の暗い夜道を歩く場面、月が煌煌と輝く海辺の場面などは、万人の心象風景にうったえることでしょう。
よくもここまで、万人に普遍的な心象風景を描き切ったものだと思います。
夢を夢らしく書いた小説としては『夢十夜』以上の大成功だと思います。
目覚めた潤一が、三十代半ばというのがほろりとさせられませす。
夢の世界には時間はありません。
人は生涯、幼い子供の心を持ち続けて生きるのです。
PR
本の要約サービス SUMMARY ONLINE(サマリーオンライン)月額330円で時短読書 小説の要約も多数あり!!谷崎潤一郎 まとめ記事
 谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
 宇美の文学
宇美の文学