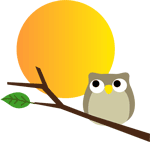はじめに
『異端者の悲しみ』は大正六年(1917年)に発表された、谷崎潤一郎の自伝的小説。
太宰治の『人間失格』の系統の自分のダメっぷりを暴露するような、自虐的自伝ですが、随所に谷崎らしい個性があふれています。
鬱屈とした青春、殺伐とした家庭が目の前にみえるかのように見事に描写されています。
谷崎潤一郎『異端者の悲しみ』あらすじ
おかしな独り言
章三郎は貧乏大学生。
日本橋、八丁堀のせせこましい裏長屋に住んでいます。
家の外から見える景色には何一つ美しい物はありません。
と悔しく思っています。
ところで章三郎は最近へんな一人ごと言うくせがついてしまいました。
一つは
という妙に威勢のいい、誇大妄想的なもの。
もう一つは
というものです。
もう一つは
というものでした。
お浜ちゃんというのは、章三郎の初恋の女性です。
恋愛関係にありましたが、二三年前に別れて以来、章三郎は今ではお浜ちゃんが、今どこで何をしているのかすら知りません。
村井と、原田というのは章三郎の中学時代の同級生で二人とも級中きっての美少年でした。
章三郎は二人に同性愛的な感情をもっていましたが、引っ込み思案の章三郎は話しかけることもできず、章三郎は二人と特に親しくなることはありませんでした。
今では章三郎は村井とも原田ともつきあいはありません。
また章三郎はこの二人を殺したいと思ったことは一度もありません。
さてこの
「楠木正成を討ち、源の義経を平らげ……」
「お浜ちゃん、お浜ちゃん、お浜ちゃん」
「村井を殺し、原田を殺し……」
という自分でも意味がわからない、独り言を章三郎は知らず知らずのうちに何度も繰り返すようになってしまいました。
しかし、そのうち人前で、あるいは往来のど真ん中で口走るようになったらどうしよう!
きっと人は僕を狂人扱いするに違いない……
と章三郎は心配でなりません。
章三郎がこんなふうになってしまったのは、彼自身理由がわかっています。
それは章三郎の恵まれない現状によるものでした。
章三郎の家庭は困窮していて、八丁堀の貧しい地域の裏長屋に住んでいます。
そして章三郎にはお富、という治る見込みのない肺病の妹がいました。
病身の妹
章三郎にはお富という、妹がいました。
年齢は十五歳ぐらいです。
お富は肺病にかかっていて余命は一二か月と医者に言われています。
そんな妹が家にいて、章三郎をじっと見ているのです。
章三郎はお富と会うと恐ろしい気持ちがするのですが、狭い家の中ですから、便所に行くたび彼女の姿を見ないわけにはいきません。
章三郎は医学を学んでいる友達から「脳が悪かったら便秘に気を付けないといけない」と忠告されて、なるべくたくさん湯水を飲んで、できるだけ頻繁に便所にいくように心がけています。
そして便所の中でいろいろとりとめのない黙想にふけります。
例えば白楽天のこととか、または哲学者ベルグソンのこととか……
そしてこんなふうに誰かに自慢したくなります。
もし人が僕の思想を外から見ることができたら、近所の人々は僕の頭の中の学問にびっくりするだろう。
章三郎が便所に長い間引きこもっていると、妹のお富が目ざとく見つけて、こんな生意気を言います。
まあなんて長い便所なんだろう。
兄さんが二三度便所に行くと、大抵日が暮れてしまうじゃないの。
ほんとに江戸っ児にも似合わない。
もう少し早くできないもんかねえ。
……ねえかあちゃん、かあちゃんてば!
妹は自分の残された命が短いのを悟っているのでしょうか?
何となく悲しかったり、心細くて溜まらなかったりするときに、不意に甘えるような声をだして、
と台所にいる母親に話しかけるのでした。
かあちゃんたらほんとにつんぼだねえ。
さっきから呼んで居るのに、いくら用をしていたって聞こえそうなもんじゃないか。
と我儘なのですが、
母親はお富の残された命の短いことを思うと、不憫に思い、わががままを聞いてやっているのでした。
しかし兄である章三郎にはお富の生意気な口のききようが、小面憎くてなりません。
そんなところに今日のような小言を聞かされて、腹がたった章三郎はお富をにらみつけました。
お富は、瀕死の彼女に独特な凄惨な目で章三郎を睨み返します。
すると章三郎はもうなにもいえなくなるのでした。
今妹と喧嘩をすると、あの怪しげな、じっと自分を視詰めている瞳が、やがて彼女の死んだ後まで長く此の部屋に残って居て、夜な夜な彼を睨みつけるに極まって居る。
そう考えると章三郎はお富に言い返すことが恐ろしくなり、ぐっとこらえるのでした。
蓄音機のエピソード
さて章三郎はそんな状況で押入れにしまってある、蓄音機を取り出そうとします。
当時蓄音機は高級品。
貧しい章三郎の家にはそんなものはありません。
この蓄音機は章三郎の裕福な叔父の家から借りてきたものでした。
章三郎の父が日に日に没落していくのに対して、章三郎の叔父は日に日に繁栄していき、今では日本橋の大通りに立派な雑貨商の店を営んでいます。
叔父は章三郎の学費やお富の医療費を援助してくれます。
蓄音機の持ち主は叔父の娘のお葉でした。
お葉は、
という理由で当初は貸すのを嫌がりました。
しかしお富の母親が
という理由で頼んだところ、なんとか貸してくれたのでした。
そんな大事な借り物の蓄音機を、家庭内ではそそっかしやと評判の、章三郎がとりだそうとしているのです。
お富も母親もハラハラします。
(お富)
兄さん、勝手にそんなものを引き擦りだしちゃいけなくってよ。
その蓄音機はお葉ちゃんが私に貸してくれたんじゃないの。
乱暴な真似をして音譜に瑕をつけたりすると、あたしが怒られるから止して頂戴よ。
(母親)
……その蓄音機はお葉ちゃんが大事にして居て、瑕を付けられると困るからって、貸すのを嫌がって居たんだけれど、お富が聴きたがるもんだから私が漸く借りて来てやったんじゃないか。
ほんとうにお前ののような乱暴者が、針のつけ方も知らない癖に無理な真似をして壊しでもしたらどうする気だい?
内じゃあお富より外に、お父つぁんだって私だって、その機械に手をつけた事はありゃしないんだよ。
しかし章三郎は
と根拠のない強がりを言い、お富と母親をやきもきさせます。
この蓄音機は両親の喧嘩のたねにもなりました。
蓄音機を借りて来た当初、父親はこう言って怒りました。
壊しでもしたら仕様がねえから、明日でも早速返してしまいねえ。
母親はこう言い返します。
何もお前さん、断るものを無理やりにでも借りて来たんじゃあるまいしさ。
父親はまた言い返します。(しゃべり方が、いかにも東京の下町風ですね)
貸せと云やあ向こうだって断る訳にゃ行きゃしねえ。
だから此方で好い加減にして置くがいんだ。
それでなくたって散々世話になっているのに、嫌がるものまで借りて来なくっても済む事だろうが……
母親の反撃
其れが悪けりゃ世話にならないでも済むようにしてくれるがいい。
自分がほんとに、人の世話にでもならなけりゃあ追付かないようにして置きながら、何かというと此方の所為にばかりして居る。
困らないようにさえしてくれれば、何も好き好んで肩身の狭い思いなんぞしたかないんだから、……
家計の切迫した状況ではささいなことが夫婦喧嘩の種になります。
家の中はいつもこのような殺伐とした雰囲気でした。
実は、章三郎の家庭はもともと裕福だったのです。
章三郎の母が家つき娘で、父親は養子に来たのでした。
父親は別に放蕩したりして身代をつぶしたわけではありません。
養子の分際を守って真面目に先代からのやり方でやっているうちに、時勢遅れの引っ込み思案になり、少しずつ商売がうまくいくなり、没落していったのでした。
夫婦喧嘩は決まって
という母の言葉で母が勝利します。
けれども母も、喧嘩に勝ったからといって、嬉しそうではありません。
母親も父親を責めながらも、自分の今の境遇が情けなくなってしまい、泣き出してしまいます。
夫婦喧嘩は、いつもこんな湿った雰囲気で終わるのでした。
ところで、お富はお葉に蓄音機の操作方法をよく習っていたので、上手に蓄音機を鳴らすことができました。
お富の操作で蓄音機を鳴らすと
やっぱり義太夫と云う物も、斯うして聞くといいもんだなあ。
と父親もご機嫌そうです。
当初は蓄音機を借りたことに反対していた父親も、まもなく蓄音機に夢中になります。
二十枚ばかりのレコードをお富にかわるがわるにかけさせて、その音色にうっとりと聞きほれます。
傷々しく瘦せ干涸らびた病人の少女が、重そうなどてらを被いで蓐の上に起き直って、静かに円盤を廻して居ると、其の傍に父と母とが頭を垂れて謹聴して居る光景は、どう考えても一種の奇観であった。
その時の娘の顔は、恰も不思議な妖術を行う巫女のように物凄く、親達は又、その魔法に魅せられた男女の如く愚かに見えた。
そうして蓄音機と云う物が、凡人の与り知られぬ霊妙神秘な機械の如く扱われて居た。
次第にお富の病状は悪くなり、今では蓄音機の操作をするのは難しくなりました。
家庭内には、お富以外には、蓄音機を操作できるものはいません。
蓄音機は押入れにしまいっぱなしとなりました。
そんな大事な蓄音機を家庭内では「そそっかしや」と言われている、章三郎が取り出そうとしているわけです。
母親も妹も必死で止めようとします。
しかし人生がうまくいかなくてやけっぱちな章三郎は、母親や妹に必死にとめられるとかえってそれに反発して、ますます蓄音機を取り出したくなるのでした。
章三郎はこんな簡単な機械に対して、大騒ぎをする母や妹のけち臭い態度が、癪にさわってたまらなかった。
なんだ馬鹿馬鹿しい!
今時蓄音機なんぞ珍しくもないのに、まるで腫れ物へ触るようにおっかながって居る。
そんなに心配するくらいなら、借りて来なけりゃいいじゃないか。
それに又貸す方も貸す方だ。
此れんばかりの道具を貸すのに、やれ瑕を付けるなとか、弾条(ぜんまい)を強く捲くなとか、世界に一つしかない貴重品でもあるかのように、勿体振らずともよさそうなもんだ。
どうせ使えば、少しぐらい傷むのは当たり前だ。
それが嫌ならこんな物を買わないがいいんだ。
―斯う腹が立って来ると、章三郎は邪が非でも其の機械を持ち出して、思うさま使い減らしてやらなければ胸が治まらなかった。
しかし実際自分で蓄音機の操作にトライしてみると、なかなかうまくいきません。
しかしあの生意気な妹に操作方法を聞くなんて癪にさわる。
なんとか自分で頑張ってみると、うまい具合に、蓄音機が鳴り始めます。
どう云う弾みか、好い塩梅に針が滑りそうなので、「清元北洲、新橋芸妓小しづ」と書いてある音譜を掛けて鳴らし始めた。
「霞のころも衣紋坂、衣紋つくろう初買いや」……ななめかしい、濃艶な女の肉声が、途方もない甲高な音を立てて、歓ばしげに威勢よく歌いだすと、章三郎は腕組みをしたままうっとりとなった。
母親と妹も声をひそめて、俄かに静粛になってしまった。
(章三郎)
そらどうだ。
蓄音機ぐらい誰にだって掛けられるんだ。
ざまあ見やがれ!
わっはっはっ!
しばし、おおいばりの章三郎でしたが……
しばらくすると、蓄音機は
「……柳桜の仲の町、いつしか花もチリテツトン……」という所へ来て、だんだん響きが悪くなり止まってしまいました。
章三郎は試しにゼンマイを五六回捲いてみましたが、蓄音機は牛の唸るような奇声を発して、少し動いてすぐにまた止まってしまいます。
いつの間に家に帰ってきた父親に章三郎は、こう責められます。
お前やり方を知りもしねえで、好い加減な真似をして機械を壊しちまったんじゃねえか。
え、おい、章三郎。
父親はお富にに機械を見てもらうように章三郎にすすめますが、
章三郎は
とか
とか言いますが、内心はびくびく。
とうとう己(おれ)は打っ壊してしまった!
何と弁解したところで、己(おれ)のした事に違いないんだ。
定めしお袋が真っ青な顔をして、壊れた道具を後生大事に日本橋へ担ぎ込んで、「お葉ちゃん、まことに申訳がないけれど、お前さんがあれ程大切にして居たものを、内の章三郎の奴が此れ此れでねえ、……」とか何とか、平身低頭して詫びるであろう。
そうしたら、あのお葉が何と云うだろう。
己に対してどんな考えを持つだろう。
―そんな事まで想像すると、章三郎は今更寝覚めが悪くなって、他人のけちんぼを嘲るよりも、人の借り物を内緒で使おうとした自分の根性の卑しさが、ありありと見え透くような心地がした。
ここで騒ぎを知ったお富からアドバイスが入りました。
お富によるとぜんまいの巻きが足りないのが原因でないかというのです。
と章三郎は言いますが、ぜんまいをぐいぐいとねじを巻き上げると、レコードはスムーズに回転をはじめて、ふたたび美しい音色をかなでるようになりました。
お富が
と得意げにすると章三郎はムカムカ。
喉元過ぎれば熱さ忘れるで章三郎はこう思います。
その後章三郎は昼寝をしてしまいました。
章三郎は大学にもいかず、家で昼寝をしているか外で酒を飲むか、女遊びをしている、というしょうもない二十五歳の若者です。
友の訃報 借金
そう父親に臀部を足で蹴飛ばされて章三郎は目を覚ましました。
章三郎は父親に反発して、ごろごろしたまま、まだ寝ていると、父親は
「ふん」と章三郎はそっけない返事をして、父親の手から電報を受け取ります。
章三郎は友達の死に驚くよりも、先ず第一に、自分あての電報を勝手に開封した父親の無法が癪にさわりました。
電報には
「スズキ、ケサ九ジ、シンダ」
と書かれていました。
亡くなったのは章三郎の学友の鈴木でした。
鈴木は茨城県の豪農の息子で、品行方正、友情に篤く、頭脳の明晰な学生でした。
友人の間で鈴木ほど徳望のある、鈴木ほど尊敬され愛慕される青年は他にありませんでした。
章三郎は鈴木に借金をしていました。
大学に入った秋の末、章三郎は五円の金が用立てできずに困っていました。
彼はその晩の午後六時までにどうしても中学の同窓会へ五円の会費を調達して出席しなければならなかったのです。
もっともそんなことになってしまったのは章三郎が原因でした。
本当はもっと安い店で同窓会をするはずだったのですが、幹事の章三郎が
いつも一円ぐらいな会費で、鮨や弁当を喰って居るなんて不景気じゃないか。
今度は一つ芸者でも上げて盛んに騒ぐとしたらどうだい。
なあに君、会費の五円も奮発すりゃあ沢山なんだから
と調子のいいことを言ったのでした。
そして
そんなら下谷の伊予紋にしよう。柳橋はどうも一向不案内だが、下谷となると我れ我れ大学生の縄張りの内だからね。
そう得意げに言った時点で、章三郎は自分には五円の会費が払えないことをわかっていました。
また実際には金のない章三郎は伊予紋のような高級料亭に行ったことなど、いちどもありません。
といい加減に考えていました。
そんな時に章三郎は往来で鈴木に出くわします。
鈴木は章三郎に会うとにっこり。
あいかわらずいい人そうです。
二人でしばらく街歩きをしたのち、ちょうど別れるというときに、章三郎は鈴木に借金を頼みました。
(章三郎)
鈴木君、君すまないが五円あったら僕に貸してくれないか。
(鈴木)
そうさねえ、丁度ここに五円ある事はあるんだが、……
貸してあげてもいいけれど、来週の金曜までに是非共(ぜひとも)返してもらわないと困る金なんだ。
(章三郎)
ありがとう。
来週になれば都合して持って来るよ。
何しろ今日は急だもんだから、奔走している隙がなくってね。
―それじゃ君、失敬。
まるで簡単に返せるようなことを言っていますが、本当は章三郎には来週の金曜日までに金をつくるあてなんかありません。
とうとう五円借りだしてしまった。
来週の金曜までに己(おれ)は此の金を返せるのか知らん。
又あの男と、絶交するような不愉快な事にならなければいいが。
……己(おれ)には何と云う悪い癖があるのだろう。
しかしまもなくこう考えなおします。
それまでのうちにはどうにかなるし、ならない所で一月か二月きまりの悪い思いをするだけだ。
どうせうやむやに済んでしまうんだ。
―最もまずく行ったとしても、絶交されるだけの話だ。
こうあきらめると、章三郎はたちまち肝が据わって少しも心配に思わなくなりました。
それからすぐに同窓会に行きます。
酔っ払って芸者を揚げているうちに、だんだん面白くてたまらなくなりました。
そしてこう考えます。
来週の金曜日になれば自分の詐欺が暴露するのに、どうしてそれが心配にならないんだろう。
恐らく世の中に、自分程道徳に対して無神経な人間はあるまい。
自分は全体意思が薄弱なばかりではなく、生まれつき道徳性の麻痺して居る、一種の狂人に違いあるまい。
借金を返す約束の金曜日が来るまでに章三郎は一二度、鈴木の下宿に遊びに行きました。
しかし、水曜日になると学友たちの前から、ふっつりと姿を消してしまいます。
そして約束の金曜日になると自宅の二階に蟄居していました。
当分の間学校は行けそうにありません。
学友に出会いそうな、本郷の往来をぶらつくこともできません。
鈴木から借金の催促のハガキが二三度きました。
章三郎は返事をしないでおきました。
章三郎はこう考えていました。
騙されたのを憤慨してこのことを友だちの間にいいふらすようなことはしないだろう。
章三郎はそう自分に都合よく解釈し、自分の悪事があいまいに葬られることを祈っていました。
しかし事実は章三郎の思い通りにはなりませんでした。
鈴木は、章三郎が約束の日に姿を消し、ハガキで催促しても返事をしないことに強くショックを受けたようです。
鈴木は章三郎の不義理を学友たちに話します。
すると学友たちは口々にこんなことを言います。
道理でこのころさっぱり顔を見せないと思っていたが、奴さん又そんな事をやって居たのか。
一時は毎日のようにやって来て、洲崎だの吉原だのって散々僕を引っ張り廻したが、勘定なんか一遍だって払ったことはありゃしない。
残らず人になすりつけて、おまけに明日返すからって僕から十五円借りて行ったきり、幽霊のように消えてしまったんだからなあ。
実際間室にゃあ馬鹿を見たよ。
間室にそんな事をされて、黙って居るには及ばないじゃないか。
こっちからあいつの家へ押しかけて行って、厳重に談判したらよさそうなもんだ。
君たちが行きにくいなら、俺が代わりに行ってやるぜ。
ここである学生がこう言います。
あいつの家というのは八丁堀の裏長屋でひどく貧乏でこまっているらしいよ。
とてもそんな哀れな所へ、押しかけて行かれたもんじゃないよ。
一人の学生は実際に章三郎の家まで借金の督促にでかけたことがあるのでした。
ちょうど去年の冬だったがね。
……僕は東京をあんまりよく知らないけれども、あんな下町のごたごたした所へ始めて行ったよ。
何だか細い路地を幾つも曲がった、ひどくわかりにくい裏の奥だったが、『此の長屋で大学に行く者は間室さんの子息(むすこ)より外にない。』と云って、近所の人が教えてくれたのでやっと見付かったのさ。
行って見ると君の云う通り、そりゃむさくるしい汚い内(うち)でね、貧民窟に毛の生えたような住居だから、談判する勇気も起りゃしない。
(中略)間室も馬鹿な男じゃないんだから、あれだけは止めてくれるといんだけれど、実際奇妙な男だなあ。
時々遠廻しに忠告してやるんだが、会うと話が面白くって、いつも呑気で居るもんだから、つい哀れになって付き合って居るがね
鈴木は皆の話を聞いた後、人格者らしくこう言いました。
僕は五円の金なんぞ惜しくはないけれど、こんな事であの人と絶交するのは気持ちが悪いから、いつでも都合のいい時に返してくれるように、会ったらそう云ってくれ給えな。
章三郎は鈴木との約束を破ってから一月ぐらいは学友たちの前から姿を消していました。
一月ぐらいすると、章三郎は学友の一人、政治科のNのところへ、のこのこ遊びにいきます。
しばらくは章三郎はNといつもどおり冗談まじりのお喋りを言いあいます。
友達の人物評をしたり、文学上の議論をしたり……学生らしい会話を続けます。
章三郎はお喋りがとても上手で友達を楽しませるのです。
Nも当初は何食わぬ顔をしていますが、帰りがけに章三郎にこう忠告します。
(N)
そういえば君、鈴木に金を返してないらしいじゃないか。
なんとか都合して早く持って行ってやりな。
(章三郎)
ああ、二三日うちに返しに行くよ。
ほんとに明後日返すのかい。君の云うことはあてにならないから……
なあに返すよ、きっと返すよ
しかし明後日になると章三郎はケロリと忘れて終日二階で講釈本を読み暮らしています。
それでも平気でNの家に遊びに行きます。
行くたびに章三郎とNの
早く返さないと鈴木が気の毒じゃないか?
友達のSが怒っていたぜ。
あんまり君が返さないようだったらS(鈴木から章三郎のことを聞いて憤慨していた学友)が君のうちに押しかけてなぐりにいくぞ
二三日内にきっとかえすよ
というようなやりとりが繰り返されます。
そのようにしてだらだらと鈴木に金を返すじまいのうちに悪性の腸チフスが流行して、鈴木がこれに感染します。
そしてついに鈴木は、今日の朝、亡くなってしまったのです。
章三郎は鈴木の様態が思わしくないことを聞いても見舞いには行きませんでしたが、Nにもし鈴木が死んだら、知らせてくれと頼んでありました。
鈴木の訃報はNから来たものでした。
「とうとう死んでしまったのか、己の友達で且つ債権者であった一人が、とうとう死んでしまったのか。」
そう思う事が不人情であると知りつつ、彼は内々胸の奥で私語することを禁じ得なかった。
亡友に対する哀悼よりも、寝覚めの悪い自己の幸運を、不思議がる心が先に立った。
Nの部屋に大学の制服をつけた四五人の鈴木の友達たちが集まってきました。
彼らは今日、昨日亡くなった鈴木の遺骸を、国元から上京した鈴木の家族と一緒に、火葬場まで送り届けました。
それが終わったあと、皆でNの部屋に集まったのです。
そんなところに
と章三郎が入ってきました。
葬式は鈴木の故郷で行われるのですが、大人数で鈴木の実家に押しかけたら、鈴木の家族にかえって迷惑です。
そこで、誰か一人が代表して鈴木の故郷に行こうという話になります。
それはSという学生になりそうでした。
ここでOという学生が
と言い出します。
Oがそう思ったのは、今日火葬場で美しい鈴木の妹に会ったからでした。
鈴木の妹にはSも興味があるようです。
Sは
とOも鈴木の故郷に行く気になってくれたことが嬉しいようです。
そんな学友らの話を聞いて章三郎はしょんぼりしてしまいました。
いつも女の話になると恐ろしく元気付いて、誰よりも先にぺらぺらとしゃべり出さずには居られない章三郎は、さすがに競争の仲間に加わる資格がないと考えたのか、口をむずむずやらせながら、黙って三人の話を聞いて居た。
単に人格が下劣なばかりでなく、境遇から云っても、章三郎は到底鈴木の妹などと結婚出来る身分ではない。
乞食にも等しい裏店の娘でなければ、彼の所へ嫁に来る女は居そうもない。
そう思うと、彼は三人の富裕な身の上が羨ましかった。
(中略)自分だって、OやNやSのように相応な財産のある家へ生れ、何不自由なく学問を修めて行くことが出来たなら、こんな卑しい品性にはならなかったろう。
(中略)彼等に対して自分が持って居る弱点の原因は、悉く金の問題に帰着するのである。
金さえあれば、学識の広さでも頭脳の鋭さでも、自分は決して彼等に劣って居るのではない、況んや自分には、彼等の到底企及し難い芸術上の天才がある。
章三郎がむっつりとしていると、友人の一人がこう、章三郎に声をかけます。
妹といえば君の妹も長い間わずらっているそうじゃないか?
どうだい、ちっとはいい方なのかい。
妹の話題が出ると章三郎はとっさにこんなでたらめを言います。
実際そりゃあ好い女だよ。
妹の器量を褒めるのもおかしいが、あんな顔だちはちょっと珍しいね。
章三郎は今迄一度も、妹のことを「珍しい器量」とも「芸者にする」とも考えたことはありません。
章三郎はこう思っていたのです。
学友たちは、うまく面白がってくれました。
何しろ兄貴が兄貴だから、間室の妹も芸者になったら定めし辣腕を振うだろうなあ。
あははははは。
章三郎の言う事を面白がる学友らをみると章三郎は、
と期待を持ちます。
さかんに駄洒落や冗談を飛ばして、学友たちを笑わせます。
学友たちの反応はとてもよいものでした。
あはははは!
久し振りで会って見ると、相変わらず間室は面白い事をいうなあ。
学友たちは
付き合って見ると間室の奴も気のいい男だ。
なあに彼奴だって腹からの悪人ではなし、唯もう呑気でずべらな為めに信用をなくして居るのだから、考えると可哀そうな人間なんだ。
ああ云う男には、此方(こっち)が始めから金を貸さないように用心してさえ居れば、面白く付き合って行けるのだ。
と考え、また章三郎と友達づきあいを再開してくれるようになりました。
章三郎と友人たちの関係は表面的な物です。
友人たちは章三郎を信用していませんが、まるで太鼓持ちのように一緒にいれば面白いのでつきあっているのです。
章三郎も友人たちとの関係はうわべだけのものと割り切っています。
お富の最後 そして天才小説家の誕生
お富の病状はますます悪くなります。
母親はいまより有名な医者にみてもらって、よい医療を受けさせたいと思っています。
一方、父親は「助からないと決まっているのに、借金してまでできない」と言います。
(父親はお富に愛情がないわけではないのですが、合理的な考えではこうなるのでしょう)
相変わらず貧乏で、章三郎は鬱屈とした毎日を送ります。
ちかごろの章三郎の唯一の救いは酒。
ちょっとでも金があると酒を手にいれて飲みます。
金がない場合は台所の調味料として使う酒を飲みます。
章三郎は深夜に家族に気が付かれないように台所にしのびこみます。
そして調味料用の酒をラッパ飲みするのです。
じつは章三郎はマゾヒストでした。
そのころ、章三郎は、なんでも彼の要求を聞いてくれる一人の商売女をみつけだしました。
その女に会いたさに章三郎はあらゆる手段を講じて遊蕩費を調達します。
そして三日にあけず蛎殻町(かきがらちょう)の曖昧宿を訪れます。
金は授業料だの教科書だのという名目で、日本橋の裕福な叔父からもらうこともありました。
せっかく友情を回復した友人たちにまた不義理を重ね、挙句のはては借りた本を売り飛ばしてまで、金を作って、章三郎は女に会いにいくのでした。
六月の末、降り続いた雨が珍しく晴れ渡ったある日でした。
四五日前から特に様態が悪くなったお富が出勤する父を呼び止めて、例になく悲しい声で甘えます。
お父ちゃん、何だか私(あたい)、今日は淋しくって仕様がないから何処へも行かずに居ておくんな。
ねえお父ちゃん。
この頃お富は、めっきり気力が衰えて、また言動も幼くなりました。
晩になると独りで寝るのが嫌だと言って、父親の腕に抱かれて眠ります。
かつての生意気ぶりは見る影もありません。
父親もお富が哀れになり
と優しく言います。
章三郎はその日は女のところに泊まっていました。
正午に起きて、ふと直感します。
はてな、事に依ると今夜あたり妹が死ぬのじゃないか知らん。
曖昧宿の勘定をすませた、章三郎は、
と予感しながらも、酒を飲んだり、浅草に活動写真を見に行ったりと街をふらふら。
結局、章三郎が家に戻ったのは夜の九時頃でした。
家の戸をあけると、母の潤んだ声がします。
章三郎かい? 早くおいで。 早くおいでよう!
狭い六畳の部屋の中に、両親を始め日本橋の叔父家族がギッシリと詰まっています。
叔父の娘、お葉もいました。
お富ちゃんや、お富ちゃんや、兄さんが帰って来ましたよ。
しかし不思議なもんだねえ。
いつも帰りが遅いのに、今夜に限って章三郎が早く帰って来るなんて。
お富は危篤なのでした。
病人には其れ等の話がよく聞き取れるらしかった。
が、もう唇が硬張ったのか一と言も物を云う事は出来なかった。
彼女は唯、賢い犬のように瞳を上げて、じっと章三郎の顔を見入った。
お富、お富、なんでお前は己をそんなに睨めるのだ。
此の間己がお前を叱ったのは、ほん の一時の腹立ち紛れに過ぎないのだ。
どうぞそんなに睨まないで、もう好い加減に免してくれ。
己はお前の兄じゃないか。
己だって今日は胸騒ぎがしたのだ。………
死に瀕したお富を囲んで、遣る瀬無い、呼吸の詰まるような苦しい時が無言のまま一時間ぐらい過ぎていきました。
突然お富の唇が動いて言葉を発しました。
かあちゃん、……あたい糞こがしたいんだけれど、此のまましてもいいかい。
母は死にゆく娘の最後のわがままを、こころよく聴き入れてやります。
ああいいともいいとも、そのままおしよ。
あああ、あたいはほんとに詰まらないな。
十五や十六で死んでしまうなんて、……だけど私(あたい)は苦しくも何ともない。
死ぬなんてこんなに楽な事なのか知ら………
これがお富の最後の言葉でした。
こうしてお富は短い生涯を終えたのです。
それから二月程すぎて、章三郎はある短編の小説を文壇に発表しました。
彼の作品は当時世間に流行している自然主義の小説とは、全く傾向の違うものでした。
それは彼の頭に醗酵する妖しい悪夢を材料にした、甘美にして芳烈なる芸術でした。
PR
本の要約サービス SUMMARY ONLINE(サマリーオンライン)月額330円で時短読書 小説の要約も多数あり!!谷崎潤一郎 まとめ記事
 谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
谷崎潤一郎|おすすめ作品|代表作品|日本近代文学の最高傑作たち
 宇美の文学
宇美の文学